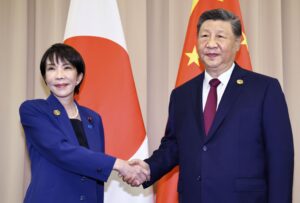Commentary
中国はなぜ米中関税戦争に勝利したのか?
中国の貿易相手の多角化が奏功

中国外交部(外務省)は2025年4月29日、史上初となる映像による広報を発表した。「跪(ひざまず)かず、退かず」と題されたこの広報映像では、冒頭に1980年代の「プラザ合意」や「日米半導体協定」、さらに21世紀に入ってからのフランス・アルストム社CEOの逮捕(2013年)、ファーウェイ副会長の孟晩舟逮捕(2018年)といった映像資料を用い、米国の覇権主義的行動に対する批判を展開した。これに対し、中国は国家主権と世界の正義を守るために、「跪かず、退かず」に戦うことを誓い、さらには各国にも共闘を呼びかけた。
「やられたらやり返す」米中報復関税
トランプ政権は大統領令に基づき、2025年2月4日および3月4日より、中国からの全ての輸入品に対し、それぞれ10%ずつ、合計20%の追加関税を課す措置を実施した。さらに4月5日からは、世界各国に対し「ベースライン関税」として10%を、また4月8日からは57カ国に対し、米国の対外貿易赤字に基づく計算により、「相互関税」と称する追加関税を導入した。これにより、ベースライン関税を含めて、例えばEUには20%、日本には24%、中国には34%の関税が課されることとなった。これに加えて、鉄鋼、アルミニウム、自動車に対しては、一律25%の輸入関税も上乗せされた。
各国は米国に対し、速やかに交渉を申し入れたが、中国のみは、米国から関税が課されるたびに、ほぼ同等の報復関税を即座に発動した。トランプ政権は2018年の第1次関税戦争と同様、中国に対し強硬姿勢をとったが、今回はその関税率をさらに引き上げ、第2次関税戦争では、相互関税34%を一挙に125%へと引き上げた。中国もこれに即応し、同率の125%へと報復関税をやり返した。
以上より、2025年4月時点までの米中関税戦争の構図は、米国側が中国に対して課した2月・3月の合計20%および4月の相互関税125%で合計145%、中国側が米国に対して課した2月・3月の主要輸入品への10~15%および4月の相互関税125%で合計135~140%に達した。
中国外交部は、かかる高率関税が実質的に禁輸レベルに達したとし、トランプ政権によるさらなる引き上げには応じる意味がないとして、これを無視する方針を声明した。さらに中国政府は、米国高官およびトランプ本人からの接触・交渉の申し入れに一切応じず、「中国と接触している」「電話をした」などの情報についても、「事実無根」と公然と否定し、相手国が屈辱と感じることをも厭(いと)わず、あえて米国を「干上がらせる」戦略を採った。1か月後の5月9日から、中国の何立峰副首相はスイスおよびフランスを訪問中に、5月10日および11日に同地を訪れたスコット・ベッセント米財務長官と第3国で会談する形式を採用し、5月12日には両国により「米中ジュネーブ経済貿易協議共同声明」が発表された。それにより、米中双方は「相互関税」を125%から34%へと引き下げ、その34%のうち24%分の実施を90日間延期し、その間にさらなる交渉を行うことで合意した。以上の結果、5月12日以降における米中間の上乗せ関税は、4月時点の米国による対中関税145%、中国による対米関税135~140%から、それぞれ約30%対20~25%へと大幅に低下した。
さらに、第1次米中関税戦争期(2018–2020)において、2020年2月に発効した『第1段階米中経済・貿易協定』に基づく関税率も勘案する必要がある。同協定では、相互の平均関税率が19.3%であったとされる(出典:https://forum.j-n.co.jp/narrative/7876/)。これを加味すると、2025年5月時点での米中間の平均関税率は、概ね49.3%対39.3~44.3%となる。