Commentary
改革開放初期の中国における「新権威主義」
1980年代、「権威」はいかに議論されていたか
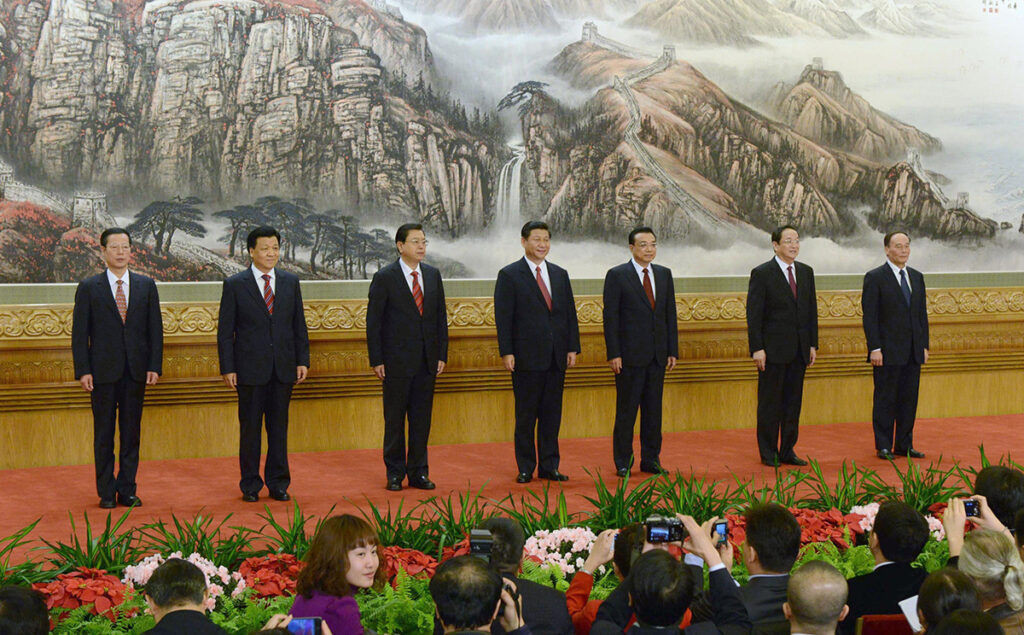
その代表的な議論として、例えば、呉稼祥は改革の障害となる「中間的社会構造」を打破するために新しい権威の必要性を説いた。中間的社会構造とは、「鉄飯碗」(親方日の丸的雇用の保障)を特徴とする従来の「単位」体制と、地方保護主義を特徴とする「諸侯経済」に代表されるような市場経済に背を向ける利権構造とのことを指す。そして、呉氏は、市場メカニズムの形成を導くためには集権的手段をもってこのような地域、集団エゴを崩さなければならないと主張したのである。
それに対して、蕭公秦は逆に「非自治性的社会人格」といういわゆる国民性の視点から、民主体制の樹立までに中国の国民の政治文化水準に見合った過渡的な権威主義の必要性を強調した。さらに、王滬寧は、中国社会のことを前近代的な特徴を持つ「村落家族文化」が依然としてその機能を発揮し続けている複合社会として捉え、中国社会の不均衡性から出発し、「権威」を重んじる「集中現代化」論を展開した。彼にとって、公共権力が権威を持って社会を調整し管理する体制を構築し合理的な資源配分を進める役割を果すことは何よりも重要だからである。
このように、権威への強調は改革を志向しつつも秩序と安定を重視することと、逆に改革の挫折を乗り越えるために強力な指導を求めることとによるものであったが、その場合、権威の強調そのものは目的ではなく、権威の創出と保持という方法をとおして改革を前進させたいという思惑は改革派の間で一致していたといってよい。
いうまでもなく、近代化、市場経済、民主主義を目指すために権威を強調することは内に論理的な緊張を抱えており、「権威」を強調する主張に反対する声が数多く上がった。権威重視の論者自身もその副作用を認識していた。その意味においては、「新権威主義」などの「権威」を重視する主張は過渡的な性格が強い。もちろん、過渡といっても、一時的な現状対策を意味するのか、それとも1つの長期的な「初級段階」として考えているのかは論者によって異なっている。
また、新権威主義が唱えられた背景として、ハンチントンの『変革期社会の政治秩序』が広く読まれていたという点も無視することはできない。「人間が自由を伴わなくとも秩序をもちうることはもちろんであるが、秩序をともなわなければ自由はもちえない」(注3)というハンチントンの言葉が、論者たちの心を間違いなく捉えたのである。
「下」から「自治」の意識を養成しなければならない
たしかにこれまでの40数年の間に、「上」から権威を持って改革を推進し大きな実績を上げてきたといえることは疑いえないであろう。しかし、他方で、基層社会の「大衆」・「百姓」たちが「下」から「自治」の意識を養成するのはやはり根本的に重要な課題であるはずである。
中国は超大社会だからこそ、基層社会の人々(「百姓」)たちをただ指導されるべき客体として扱うのではなく、「百姓」たちの自治の習慣の養成がとくに重要であるのではなかろうか。それを最終的に実現するために、党は権威を持って大衆のために「代行」する代わりに、大衆をサポートしていくという「役」の転換が求められていると思われる。
そもそも、権力と社会との乖離、権力の疎外を避けるために、「大衆の中から大衆の中へ」という「大衆路線」が共産党にとっての「宝」だと強調されている論理も、ここに求められるはずである。現在、基層社会においても党の指導が強調されているが、基層社会の大衆・百姓と乖離した存在にならないように、党は行政や官僚制と一体化したものではなしに、「大衆路線」を真に実践し、官僚制に対する牽制となる存在になって、初めて人民の代表としての党の正当性を体現することができるのではなかろうか。
(注1)中国共産党の建党百年の2021年に党の第19回中央委員会第6回全体会議で採決された「中共中央関於党的百年奮闘重大成就和歴史経験的決議」を参照されたい。
(注2)「大鳴、大放、大弁論、大字報」という自由の名の下で、大衆が壁新聞やデモなどの大衆運動をとおして政治過程にかかわること。
(注3)内山秀夫訳、サミュエル・ハンチントン『変革期社会の政治秩序』(上)サイマル出版会、1972年、9-10頁。






