Commentary
改革開放初期の中国における「新権威主義」
1980年代、「権威」はいかに議論されていたか
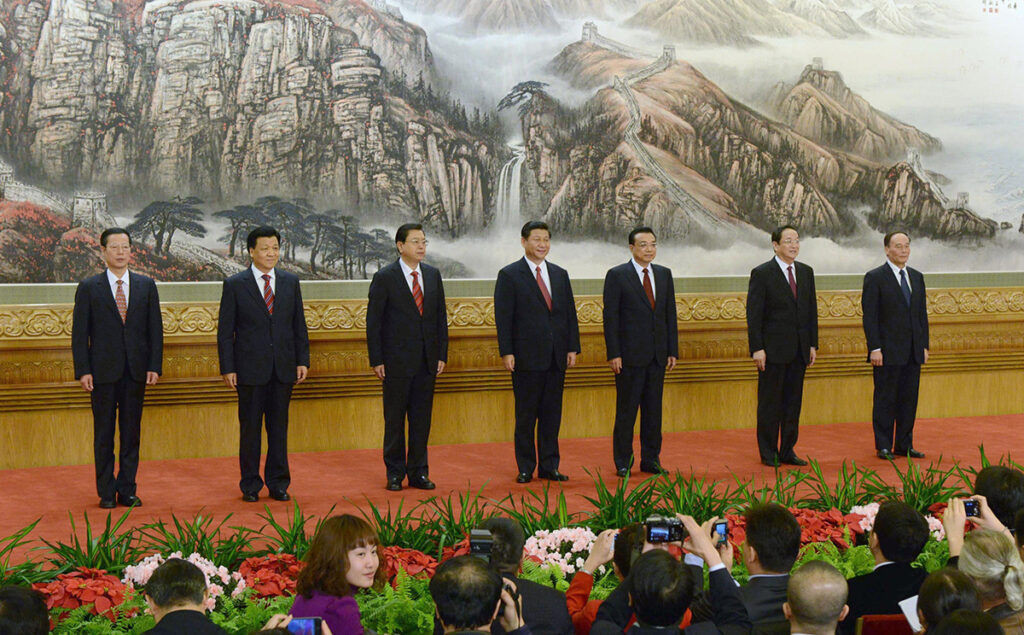
中国の改革開放が始まって以来、40年余りの年月が経ったが、現在の「習近平新時代」はその延長上にある。というのは、習近平政権下で、改革開放が「当代中国の前途の運命を決めるカギとなる一手」だとされており、改革開放路線が定められた1978年の中国共産党第 11期中央委員会第3回全体会議(11回3中全会)が1つの画期として、そして、「全面的に改革を深化させる」という目標を掲げた2013年の第18期中央委員会第3回全体会議(18回3中全会)が「改革開放の新局面を切り開いた」もう1つの画期として位置づけられているからである(注1)。
であるならば、権威の強調と権力の集中とが進められている現在の中国について考えるときに、改革開放の初期の1980年代の中国において、「権威」がいかに議論されていたかを確認することは重要だといってよい。
近代国家への移行を追求し、思想解放が活況を呈した時代
1980年代という時代には、中国の人々が自国の政治発展を展望する際にいくつかの共通した前提があったように思われる。
まず、近代国家への移行を追求し、実現しようという共通の悲願があった。戦争、革命、政治運動が繰り返された後、ようやく近代以来の「富強」という課題が再び国家発展の中心に据えられ、追求されるようになったのである。
次に、終結したばかりの10年間の「文革」の「大民主」(注2)や個人崇拝がもたらした政治的、社会的混乱に対する反動と、鄧小平の「白猫黒猫」論に象徴される脱イデオロギー化があった。「四つの現代化」という目標はそれまでの時代に別れを告げた宣言にほかならなかった。
さらに、思想が一元的に規定されていた従来の政治的状況がある程度開かれたものになり、思想解放が活況を呈するようになった。20世紀初頭の受容からしだいに形成された社会主義の伝統をはじめ、自由主義の伝統、そして、儒教の伝統を受け継いだ「新儒家」など、新しい時代の中国を構築しようとした人々は多くの伝統を自分たちの思想的資源として活用した。中国の長い文化的伝統と近代以来の紆余曲折を経た道とが現代中国の人々の思考を規定する一方で、人々に豊かな思想的資源を提供した。このような相対的に自由な思想的状況の中で、人々は中国の近代化の道をそれぞれの視点から探索した。そのことが、この時代の中国思想界の活発な議論を生み出したのである。
その中で、とくに注目に値する議論の1つとして、「新権威主義」をめぐる論争が挙げられる。
権威主義は現在、専制主義に近い意味合いで使われ、ネガティブないし否定的に捉える論調が多くみられるが、1980年代半ばごろに中国で提起された「新権威主義」は逆に政治体制の正統性を主張する言説としてポジティブに唱えられていた。改革を急進的に推し進めようとする一部の中国の改革知識人と、逆に安定を重視する穏健な立場から強力な政治的リーダーシップが必要だと考える人々とが、それぞれの立場からいずれも「権威」の強化を主張していた。急進的な改革者たちは改革を妨げる保守的勢力の抵抗を突破するためにストロングマンを求め、一方の穏健な改革者は安定重視の立場から強い指導力を強調したのである。そして彼らはモデルとして、とくに権威主義体制の下で経済成長を遂げた韓国や台湾などのアジアNIESを挙げている。
もちろん、「新権威主義」の主張は多くの批判を招いた。批判者たちはアジアNIESの成功経験をある程度認めたものの、これらの国や地域の状況が中国と異なっていると指摘したのみならず、さらにこれらの国や地域における民主化の潮流に注目し、権力集中を批判して中国の政治的民主化を主張したのである。
論争は繰り広げられたが、「新権威主義」論者とその批判者との間に政治的民主化という目標についてはコンセンサスがあった。そもそも「新権威主義」の論者たちが「権威主義」の頭にあえて「新」をつけたのは、強力な指導者を求めることは個人の自由発展の障害を取り除き、個人の自由を保障するためだと強調しようとしたからである。
価格改革の挫折、社会的な混乱で低下した「権威」
経済改革とともに政治的民主化改革を望んだ改革派が「権威」をことさらに強調したのは、1978年以来進めてきた改革が1つの曲がり角に差しかかったからにほかならなかった。1980年代に始まった請負制を特徴とする経済改革は、まずは農村で、その後は都市部で巨大な成功を収めた。しかし、やがて、経済をさらに発展させるためには従来の経済体制を変革しなければもはや改革を前進させることができないという課題が改革派に突きつけられるようになった。
その象徴の1つが価格改革である。改革の初期には、過渡的な措置として計画経済システム下の公定価格と市場経済システム下の市場価格とが併存する「双軌制」がとられていた。このような二重価格制は結局、両者間の価格差を利用して利益を求める「官倒」(官僚ブローカー)の横行を招くようになり、一般の人々の間に大きな不満を募らせることになった。そのため、不合理な価格統制を自由化して価格を市場に決めさせることを目指す価格改革が断行された。しかし、改革はインフレを引き起こし、1988年にさらに社会的混乱を招くことになって、結局挫折した。
一方で、その前年の1987年に「社会主義初級段階」論が提起された。経済的改革を成功させるために、「党政分離」を旨とする政治体制改革の目標が掲げられ、大きな一歩が踏み出されようとしたのである。
1988年の価格改革の挫折と社会的な混乱とは、改革を断行しようとした指導部の権威の低下を招いた。市場経済に向けての価格改革と「党政分離」の政治体制改革とが挫折するのではないか。そのような危機感から出発して、一部の改革派知識人はそれぞれの立場から「新権威主義」(またはそれと相似した)主張を提起したのである。
その代表的な議論として、例えば、呉稼祥は改革の障害となる「中間的社会構造」を打破するために新しい権威の必要性を説いた。中間的社会構造とは、「鉄飯碗」(親方日の丸的雇用の保障)を特徴とする従来の「単位」体制と、地方保護主義を特徴とする「諸侯経済」に代表されるような市場経済に背を向ける利権構造とのことを指す。そして、呉氏は、市場メカニズムの形成を導くためには集権的手段をもってこのような地域、集団エゴを崩さなければならないと主張したのである。
それに対して、蕭公秦は逆に「非自治性的社会人格」といういわゆる国民性の視点から、民主体制の樹立までに中国の国民の政治文化水準に見合った過渡的な権威主義の必要性を強調した。さらに、王滬寧は、中国社会のことを前近代的な特徴を持つ「村落家族文化」が依然としてその機能を発揮し続けている複合社会として捉え、中国社会の不均衡性から出発し、「権威」を重んじる「集中現代化」論を展開した。彼にとって、公共権力が権威を持って社会を調整し管理する体制を構築し合理的な資源配分を進める役割を果すことは何よりも重要だからである。
このように、権威への強調は改革を志向しつつも秩序と安定を重視することと、逆に改革の挫折を乗り越えるために強力な指導を求めることとによるものであったが、その場合、権威の強調そのものは目的ではなく、権威の創出と保持という方法をとおして改革を前進させたいという思惑は改革派の間で一致していたといってよい。
いうまでもなく、近代化、市場経済、民主主義を目指すために権威を強調することは内に論理的な緊張を抱えており、「権威」を強調する主張に反対する声が数多く上がった。権威重視の論者自身もその副作用を認識していた。その意味においては、「新権威主義」などの「権威」を重視する主張は過渡的な性格が強い。もちろん、過渡といっても、一時的な現状対策を意味するのか、それとも1つの長期的な「初級段階」として考えているのかは論者によって異なっている。
また、新権威主義が唱えられた背景として、ハンチントンの『変革期社会の政治秩序』が広く読まれていたという点も無視することはできない。「人間が自由を伴わなくとも秩序をもちうることはもちろんであるが、秩序をともなわなければ自由はもちえない」(注3)というハンチントンの言葉が、論者たちの心を間違いなく捉えたのである。
「下」から「自治」の意識を養成しなければならない
たしかにこれまでの40数年の間に、「上」から権威を持って改革を推進し大きな実績を上げてきたといえることは疑いえないであろう。しかし、他方で、基層社会の「大衆」・「百姓」たちが「下」から「自治」の意識を養成するのはやはり根本的に重要な課題であるはずである。
中国は超大社会だからこそ、基層社会の人々(「百姓」)たちをただ指導されるべき客体として扱うのではなく、「百姓」たちの自治の習慣の養成がとくに重要であるのではなかろうか。それを最終的に実現するために、党は権威を持って大衆のために「代行」する代わりに、大衆をサポートしていくという「役」の転換が求められていると思われる。
そもそも、権力と社会との乖離、権力の疎外を避けるために、「大衆の中から大衆の中へ」という「大衆路線」が共産党にとっての「宝」だと強調されている論理も、ここに求められるはずである。現在、基層社会においても党の指導が強調されているが、基層社会の大衆・百姓と乖離した存在にならないように、党は行政や官僚制と一体化したものではなしに、「大衆路線」を真に実践し、官僚制に対する牽制となる存在になって、初めて人民の代表としての党の正当性を体現することができるのではなかろうか。
(注1)中国共産党の建党百年の2021年に党の第19回中央委員会第6回全体会議で採決された「中共中央関於党的百年奮闘重大成就和歴史経験的決議」を参照されたい。
(注2)「大鳴、大放、大弁論、大字報」という自由の名の下で、大衆が壁新聞やデモなどの大衆運動をとおして政治過程にかかわること。
(注3)内山秀夫訳、サミュエル・ハンチントン『変革期社会の政治秩序』(上)サイマル出版会、1972年、9-10頁。






