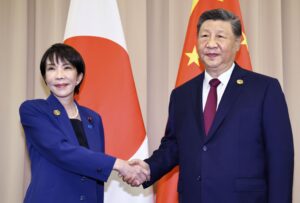Commentary
「三冠王」中国の課題
「自信を支える底力」に求められる改革

その1.大衆資本主義→「白菜価」モデル→世界制覇の方程式
丸川知雄は、中国経済、さらには世界経済を変貌させたのは中国の国家資本主義ではなく、「大衆資本主義」(『チャイニーズ・ドリーム』筑摩書房、2013)であると位置づけている。
1990年代後半にもさかのぼれるが、関満博は、中国製造業の特徴を「百円ライターモデル」として提示した。すなわち、かつて日本では千円の汎用(はんよう)品から数万円の高級品まで多様なライターが生産されていたが、中国の中小企業が市場に参入することで、それらは瞬く間に使い捨ての「百円ライター」に取って代わられ、日本のライター産業自体が姿を消した。関はその後、自動車産業にも同様の現象が及ぶ可能性を早くから指摘していた。
それから30年を経た現在、中国製の自動車は実際に同クラスの欧米メーカー車の半額以下で販売されている。今日の中国社会では、「白菜価(バイツァイジァ、常識外れの安値)」という言葉が慣用化し、「中国企業が参入すれば、すべてが白菜価になる」といった言説が一般的に語られている。最近の一例として、平均年齢20代の若者数十人が、高コストとされる生成AI開発において、米国企業の約6%のコストで同レベルの「DeepSeek」を開発したことが挙げられる(編集部:丸川知雄「DeepSeekの衝撃」「DeepSeekの衝撃(続)」もご覧ください)。
全国人民代表大会常務委員であり北京大学教授でもある賈慶国は、中国メディア(『北京青年報』、2025年5月6日)に対して、「米中の製造コストにはおよそ5〜10倍の差がある。関税によってその差を埋めることは不可能であり、結局は米国企業および消費者のコストを引き上げるだけだ」と述べた。また彼は、「トランプは19世紀型の二国間貿易観にとどまり、21世紀の多国間サプライチェーンに基づく統治構造を理解していない」とも批判し、「現在、米国が中国から輸入している製品のうち、およそ3割はiPhoneのような米国企業の製品であり、他国企業の製品にも最大で6割においては中国製の中間財が組み込まれている」と指摘した。
このように、中国政府の上層部は米中間における産業コストの大きな格差を正確に把握している。丸川の言う「大衆資本主義」が、モノづくりの「白菜価」モデルを作り出し、国内市場はもちろん、国際市場においても中国製品が圧倒的な競争力を発揮する構図が生まれている。トランプ政権による関税措置であっても、中国製造業の「白菜価」には太刀打ちできない。それこそが中国の「自信を支える底力」なのである。
理論を離れ、具体的な日常の実例に目を向けてみよう。手元のスマートフォンでオンラインストアの「拼多多(Pinduoduo)」と、その海外版である「Temu」に並んでいる製品の価格を比較すると、同一製品であっても海外の「Temu」の定価は「拼多多」の約5倍である。これをさらに欧米の市街地にある実店舗で購入しようとすれば、「Temu」の価格の2倍以上、つまり「拼多多」と比べて10倍以上の価格となる。このような価格構造の中で、2025年4月に導入されたトランプ政権の対中関税(最大145%)も、「拼多多」基準で見ればわずか1.45倍の価格上昇に過ぎず、10倍の価格差を前にしては無力である。「白菜価」の中国製品が、米国のオンラインおよびオフライン市場に流入するのを阻止することは極めて困難である。
『日本経済新聞』(2025年5月23日)はEUの事例を報じている。EUは2023年10月より、中国製電気自動車(EV)に対する関税を合計で17.8%〜45.3%に引き上げた。しかし、2025年4月の登録台数において、中国製EVは前年比59%増を記録し、これに対し欧州・日本・韓国・米国のメーカーは26%の伸びにとどまった。中でもBYDは初めてテスラを抜き、登録台数で第1位に躍進した。
確かに、アマゾンやウォルマートなど米大手企業が2025年4月に中国からの輸入を一斉に停止し、米国の港湾が空となる事態も発生した。5月に関税が49.3%へと引き下げられても、依然として「価格転嫁は避けられない」とする米国企業の姿勢は変わらなかった。トランプはこれに激怒し、「今まで儲けすぎていたのではないか。関税分は自分たちで吸収すべきだ」と一喝した(『日本経済新聞』2025年5月18日など)。トランプの「一喝」の意図は不明ながら、ここで言う米国企業とトランプの争いは、いずれにせよ、中国企業が関税分の価格差をもう負担しない、値下げしないという前提での争いである。それは少なくとも、中国の輸出企業の交渉力が強まっていることを意味しているだろう。
前述(「中国はなぜ米中関税戦争に勝利したのか?」)の通り、米中間でかかる関税は、現状では通常の関税と上乗せ関税を合計すると、米国は中国からの輸入に対して49.3%、中国は米国からの輸入に対して39.3%〜44.3%である。米国側の関税は中国製品の流入を阻止するには不十分である一方、中国側の関税は米国製品の輸入をほぼゼロにする効果を持ち得る。現状においても、米国からの輸入は、米国企業が関税を支払っているか、中国側の米中関係への「配慮」によって成立しているに過ぎない。
その2.ギリギリのタイミングで米国発のAI革命に追い付く
1.機器製造、IT製造、AI開発の「三冠王」
周知の通り、約300年前に始まった機械使用による産業革命、1990年代から本格化したIT革命、そして2020年前後より台頭したAI革命が、連続的に展開されてきた。
中国の歩みを俯瞰(ふかん)すると、前近代においては、個人による営農と農業市場経済を2000年以上にわたり営み、結果として経済・版図両面で世界最大の国となった。この豊かさゆえに機械の使用を必須とは捉えず、近代において約100年の後れを取り、列強による侵略の対象ともされた。
しかしその後、「貧者は変を望む」(毛沢東)。中国は西側諸国に追い付こう、追い越そうとした結果、2025年現在、機器製造、IT製造、AI開発のすべてにおいて世界的な主導権を握りつつある。他方で、西側諸国は製造業の空洞化が進み、故にIT化が遅延し、AI分野においては米国のみが中国と並び立つ状況にある。
中国は半導体分野においては未だ遅れているとの反論もあるが、実際には、世界最大の半導体輸入国であると同時に、最大の製造国・輸出国でもある。中国は最先端に次ぐ成熟プロセス半導体を大規模に量産しているが、それらは最も需要が高い汎用半導体である。2024年、中国における半導体の生産量は4,514億枚で前年比22.2%増、輸入は5,492億枚(3,856億ドル、1ドル=約150円として約58兆円)で9.5%増、輸出は2,981億枚(1,595億ドル)で16.9%の増加を記録した。
国際半導体製造装置材料協会(SEMI)の予測によれば、2024年および2025年の中国の半導体製造能力は、月産885万枚および1,010万枚に達し、いずれも世界全体の約3分の1を占めるとされる。量産能力において中国は世界一であり、これに続くのは台湾、韓国、日本、米国、EUであるが、日本と米国はそれぞれ世界シェアの10%前後、EUは5%未満にとどまっている。
このようにして、中国は2025年という「関税世界大戦」の開戦年に間に合う形で、「二冠王」に加え、AI革命においても先導的なポジションにある。これを可能にした要因は、以下のようなロジックによりある程度説明が可能である。
2.「世界システム論」から見た中国の「中心」入り
筆者は1990年当時、「従属論」を恒川恵市氏に、「世界システム論」を田中明彦氏に学んだ。両氏は当時、米国から帰国したばかりの新進気鋭の政治学博士であった。
世界システム論によれば、世界は「中心」「準周辺」「周辺」の三層構造から成り、常に先進国が中心的役割を担う。例えば、ラジオの普及を達成した先進国において初めて、テレビという次世代製品に対する新たなアイディア、需要が生まれる。これにより、先進国は常にイノベーション、資本、人材、研究開発、製造、流通、販売の全プロセスを担う世界の需要と供給の中心となる。他方、「準周辺」および「周辺」の国々は、中心国のために働く「従属」という地位に置かれる。
この構造に基づけば、1970年代から80年代にかけてカラーテレビや家電、自動車などを普及させた先進国において、1990年前後にパソコンや携帯電話といったIT化の新たな需要が生まれた。これに対し、当時の中国は依然としてカラーテレビや白物家電の普及段階にあり、大きく後れを取っているように見えた。
しかしながら、次世代製品が研究開発から量産・普及に至るには相応の時間を要する。例えば、白黒テレビの発明からカラーテレビの普及までは半世紀を要した。このような「先進国の停滞期間」こそが、準周辺国が中心国に追い付く機会、すなわち「歴史的チャンス」であると世界システム論は指摘している。
3.日本と中国の「中心」入りの比較
この理論に照らせば、1970、80年代に「中心」入りを達成したのは日本であった。当時、日本は最高水準の機械化を実現した上、IT革命の初期段階において半導体、パソコン、携帯電話などの製品開発と量産を主導した。その結果、西側諸国では「ジャパン・バッシング」が吹き荒れ、「プラザ合意」「日米半導体協定」などの「経済摩擦期」と呼ばれた対日関税戦争、経済戦争が繰り広げられた。レーガン政権下では、日本のパソコンやテレビに対して100%の関税が上乗せされた。当時の中曽根康弘首相は、かろうじて日本車への上乗せ関税100%の適用を免れたと後に述懐(じゅっかい)した。これに比べれば、2025年のトランプ関税(20%台)は「関税戦争」より、まだ穏当と言えるかもしれない。
一方、中国は1980年代より改革開放を進め、約30年後の2010年にGDPにおいて日本に追い付き、機器製造による産業革命を完成させた。そこで進行中のIT革命の「最終電車」に間に合い、続いてAI革命のスタートラインに「中心」諸国と肩を並べて立つことに間に合った。
そして、2025年1月21日のトランプ大統領就任式に合わせて発表された中国製AIモデル「DeepSeek」は、トランプ政権による新関税発動の直前という絶妙なタイミングでの象徴的成果となり、中国がAI分野においてもフロントランナーになったことを内外に印象づけた。
対照的に、インドは中国より十数年遅れの1990年代から改革を開始し、試行錯誤のうちに機械化が未完成に終わり、IT化とAI化の「終電」に乗ることはできなかった。
4.中国の発展の特異性と「三冠王」国の課題
総じて、中国の発展は過去40年間において工業革命、IT革命、AI革命の三つを一気に最前列に進めた点において特異である。これは、西側のように段階的な「工業化→脱工業化→IT化→AI化」という直線的な発展過程とは異なり、中国がこれらを並行的かつ統合的に進めて来たことを意味する。
さらに、中国は近年流行している言葉で言えば「広土巨族」(文楊『広土巨族』中華書局、2019)である。「広大な国土並びに巨大な民族」という意味で、発展をやり遂げると、世界中の需要にこたえるだけの製品を作る能力を持ちうる、という自己認識が表れている。要はお馴染みの「米国例外主義」に並んで「中国例外主義」もあるという語りである。ちなみにジョセフ・ナイは米国例外主義について、「例外」とは言えない「自由」と「宗教」を挙げた後に、「我らの例外主義は米国の尋常でない広大な国土とその地理的条件に由来する」と書き記した(ジョセフ・ナイ『国家にモラルはあるか』早川書房、2021年、25-29頁)。結局のところ、ジョセフ・ナイの例外主義の根拠は広大な国土だけであり、だとすると、トランプがカナダとグリーンランドを併合しようとする意識は、この米国例外主義にあるのであろうか。
これに比べると、中国にはもう一つ、14億人の「巨大な民族」もある。しかも、2025年現在において、中国は「世界システム」の中心に位置する唯一の「三冠王」である。
もっとも、この「三冠王」は、各国にとっては生産財、消費財、公共財の供給者として魅力的であると同時に、雇用や市場をも席巻する「経済的巨人」としての脅威ともなり得る。しかしこの「巨大な民族」が、少子高齢化という現代的課題に直面し、その「万能性」を今後どこまで維持できるかは、依然として未知数である。
致命的な弱点──国内の需要側改革と消費拡大を取り巻く難局
2024年の中国における社会消費財小売総額は、前年比3.5%増の6.8兆ドル(48.8兆人民元=約1000兆円)であった。また、同年の輸出入総額は前年比5%増の5.9兆ドル(43.85兆人民元)に達した。中国の対米輸出額は4,389億ドルに上り、これは中国の国内消費の約6%に相当する。裏を返せば、仮に国内消費が6%以上増加すれば、対米輸出の減少分を代替できる計算になる。しかし、2024年における中国の国内消費の伸び率は3.5%にとどまった。2025年第1四半期には5.3%まで上昇したものの、依然として楽観できる水準ではない。
米中関税戦争において、中国側が取るべき根本的かつ決定的な政策は、対米交渉ではなく、国内における需要側の構造改革と消費拡大にある。これは単に通商問題に限らず、中国経済が健全に発展するためにも不可欠な道筋である。
しかしながら、消費拡大の実現は中国にとって極めて困難であり、この点は過去40年間の日本および韓国の内需拡大の実績を見ても明らかである。欧米においては、所得以上の過剰消費が経済問題や社会問題を引き起こしているが、日中韓ではむしろ過剰な貯蓄が経済活力を抑制している。日本と韓国の貯蓄率は常に30%を超え、中国においては40%を超え、時に50%をも上回る驚異的な水準にある。1952年から2023年までの中国の平均貯蓄率は37.2%、最高値は2010年の50.7%であった(出典:https://www.ceicdata.com/ja/indicator/china/gross-savings-rate)。2024年には、中国が43.8%、韓国が34.2%、日本が29.8%であったのに対し、米国はわずか16.9%に過ぎない。
この現象の主要因は、しばしば言及されるような所得水準や福祉政策といった経済・社会制度ではなく、文化・文明的要因にあると考えざるを得ない。
日中韓に共通する文明的背景は、儒教文明である。四季のある農耕地帯において、長きにわたる家族的営農と相続制度のもとに形成された儒教的価値観は、収穫物の貯蓄および世代間の財産継承を「徳」とみなし、それに反する浪費や無責任は「不徳」「敗者」として否定される。この文化的枠組みのもと、中国では多くの親世代が、子どもの一生を保障する財産をコツコツと蓄え、それが達成されると今度は孫のための貯蓄を開始する。このような傾向の中で、自らの消費にはなかなか金を回さない。加えて、中国には相続税や贈与税が存在せず、これは政府がその徴収に対する儒教文明からの反発を恐れているためだとも解釈される。
日本では2019年に高齢者世帯が豊かな老後を送るためには2,000万円の貯蓄を準備したほうがいいという政府の審議会の試算が示されて物議をかもしたが、これは欧米諸国から見れば不可解に映るであろう。
中国政府の掲げる消費拡大策には、「剛需」(リジッド・デマンド)すなわち「必需的消費」の充足が強調されている。しかし、「剛需」とは本来、施策がなくとも自然に生じる消費であり、これを超えるいわゆる「裁量的消費」や「浪費的消費」こそが消費拡大に不可欠であるという価値観、経済論理がまだわかっていない。
過去十数年にわたり、中国は「供給側改革」に注力してきた。「モノづくり」は日中韓に共通する文化的美徳の一つである。確かに米中二つの超大国の競争という国際環境があって、中国は「中国製造2025」ビジョンを掲げ、供給体制の強化に成功し、その結果、製造業、IT、AIの分野において「三冠王」の地位を確立し、対米競争において有利な立場を築いた。しかし、2025年の今日に至っても、政府は「需要側改革」というスローガンを公式には打ち出していない。
大規模な需要側改革なくして、消費拡大は望めない。需要側改革を経済政策の第一義に据え、消費に対する価値観の転換、消費システムの抜本的改革、さらには金融改革、消費拡大を後押しする金融制度への転換が不可欠であろう。
また、過去数十年にわたる日中韓の内需拡大の失敗の経験から、文明の枠組みに根差した行動様式を変えるには、幾分かの強制力を伴う政策が不可欠であることも示唆される。この点、中国共産党は、党員に率先垂範を求めることで体制的「優越性」を発揮し得る。例えば、現在、中国で最も落ち込んでいる分野である恋愛、結婚、出産・育児といった行為は、どれを取っても消費倍増をもたらす行為である。これらの領域に対しては、かつて党組織が積極的に関与していたので、その伝統を再興することは有効な方策となり得る。この点は、同じ儒教文明圏にあるシンガポールの与党が採った政策にも通じるものである。
果たして2025年、中国政府は真に「需要側改革」の必要性を認識し、その実行に踏み切るのであろうか。それは中国の運命を左右する重大な分岐点となるであろう。