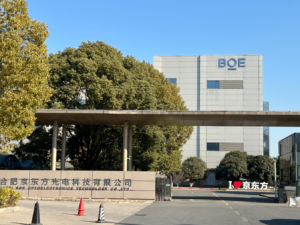Commentary
エネルギー消費が巨大化した中国の脱炭素の行方
原油も石炭も世界一の輸入量、CO2排出量も最大

さらに図を見ると、折れ線は2000年時点での各国のエネルギー消費量の総計を示しており、2022年の水準と比較すると中国がこの四半世紀足らずの期間でエネルギー消費量を激増させてきたことがわかる。ほかの途上国の国々、とりわけインドのエネルギー消費量もかなりの成長となっているが、中国は群を抜いている。
中国は2000年当時、米国に次ぐ世界第2位ではあったが、米国の半分程度のエネルギー消費量にすぎなかった。それが2022年には米国の1.7倍もの消費量へと増大したわけで、この期間、絶対量の大きさもさることながら、その成長速度の速さからも中国のもたらす影響が大きかったことがうかがえる。
ちなみに先進各国はこの四半世紀、いずれもエネルギー消費量をほとんど増やしておらず、とくにわが国は大幅な省エネルギーを達成している。
「CO2排出量のシェアはさらに高い」という不都合な事実
前ページの図で各国のエネルギー構成を見ると、中国とインドでは石炭が主要エネルギーとなっていることも注目に値する。いずれもエネルギー消費全体に占める石炭の比率は6割程度となっている。
中国の1次エネルギー消費に占める石炭の比率は2010年代に急速に低下し、2007年の72.5パーセントから2021年には56.0パーセントとなっている。それでも依然、押しも押されぬ主要エネルギーである。また国内の1次エネルギー消費に占める比率こそ低下傾向であるが、消費量そのものは2010年代後半の一時期を除いて増加し続けている。翻って先進国、とくに欧州では石炭の消費量が1990年代以降減少傾向を続けてきたため(ただし近年底打ち感がある)、中国の石炭消費が世界全体に占める比率は上昇してきた。2022年には中国の石炭消費量は世界の54.8パーセントにまで達しており、1990年の23.7パーセントから大幅に上昇した。
巨大なエネルギー消費を抱える中国が世界最大のCO2(二酸化炭素)排出国となっていることも理の当然といえるだろう。中国が世界のエネルギー消費に占める比率は26.4パーセントであり、エネルギー起源のCO2排出に占める比率は30.4パーセントとなっている。エネルギー消費のシェアよりもCO2排出のシェアが高いのは、エネルギー構成に占める化石燃料、とりわけ石炭の比率が高いことによるものである。これは中国にとっては不都合な事実といえるかもしれない。
2015年のCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)でパリ協定が合意されて以降、欧米諸国は産業革命以前と比べての気温上昇を1.5度以内に抑えるべく、国際交渉で化石燃料、とりわけ石炭の撤廃を強く働きかけてきた。化石燃料を代替するエネルギーとして風力や太陽光などの再生可能エネルギーが挙げられているが、その投資コストの高さ、自然任せで出力コントロールができないなどの点から、途上国が再生可能エネルギーを中心にエネルギーシステムを構築することは、実際のところ困難である。180カ国余りの国々のエネルギー消費量を足し合わせた以上のエネルギーを消費している中国と米国がどう対策するかが圧倒的に重要であり(インドも合わせ、この3カ国によるCO2排出量は世界の52.3パーセントに及ぶ)、多くの途上国が高いコストを負担しながら上位3カ国と比べれば微々たるCO2排出量を削減することに意味があるのか、率直に疑問に思う。
中国は、CO2排出量自体は多くとも1人当たりで見ると決して多くはない、という主張を従来掲げてきた。しかし世界銀行のデータによれば、2020年時点で、中国の1人当たりCO2排出量は7.8トンで世界平均の4.7トンを大きく上回る。米国の13.0トンや、高所得国の平均8.7トンよりも少ないが、OECD平均の7.7トンを上回り、中国が該当する上位中所得国の平均5.9トンと比べればかなり大きい。
中国は2030年までにCO2排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラル実現を目標として掲げているが、より厳しいCO2排出削減を求められるべきかもしれない。しかし現実には、化石燃料に依存した巨大なエネルギー消費量を抱える中国が脱炭素を進めていくためには、相当困難な道をたどらざるをえないのである。