Commentary
監修者に聞く――川島真さん
周俊宇著、川島真監修・校訂『日本の植民地統治と台湾人認識』(東京大学出版会、2025年8月)
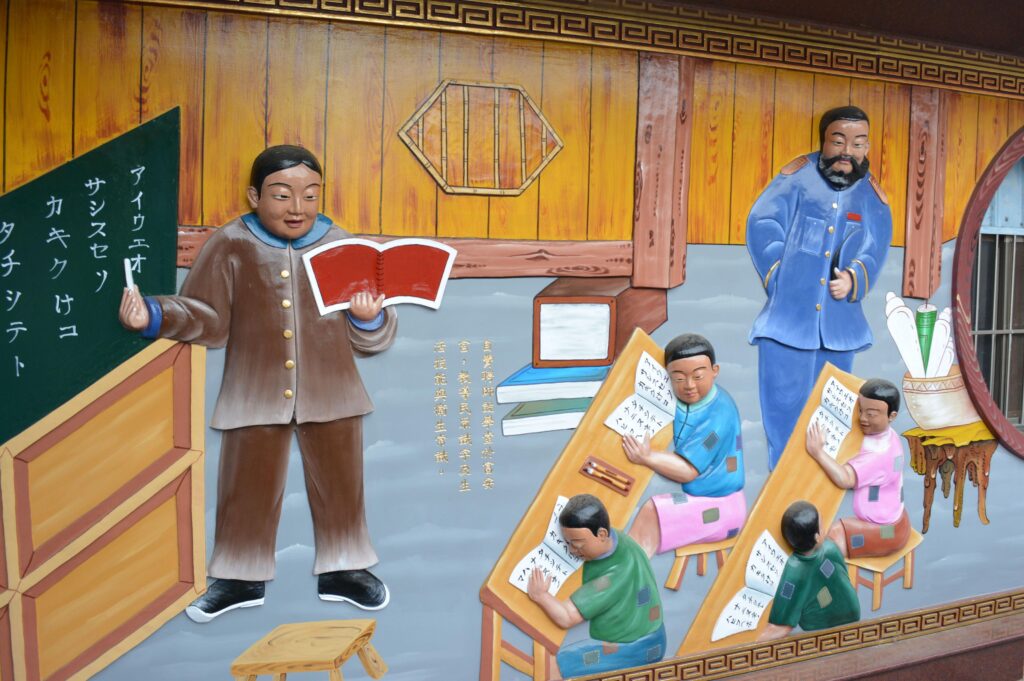
問4 「支那民族性」という言葉を手掛かりに日本統治期の台湾を描こうとした著者は、1945年以後、また1949年以後をどのように見ていたのでしょうか。日本から台湾への視線、台湾自身の自己認識との面で日本統治期の論点や課題はどのように継承、断絶されたのでしょうか。あるいは忘却されたのでしょうか。
(川島)すでに記しましたとおり、周さんがこの課題に取り組んだのは、1920年代とされる台湾における台湾アイデンティティの形成過程と、近代日本の台湾認識との間の相互関係を明らかにするためでした。近代日本の台湾認識についての考察を踏まえた周さんが次に取り組むはずであったのは、おそらく台湾人アイデンティティの形成過程との関係性に関する考察でしょう。
ただ、もともと周さんは、戦後台湾において「中華民国がいかにして国民を作り上げていったのか」という問いに取り組んでいたわけですから、戦後についても関心がないはずがありません。もちろん、周さん自身は中華民国、そして日本という統治者側の視点だけで議論が足りると思っていたわけではないはずです。台湾人自身の台湾アイデンティティの形成と近代日本の台湾認識との相互関係を議論しようとしたのがその表れでしょう。
このことを踏まえれば、周さんは博士論文を刊行した後、1920年代に形成された台湾人認識と近代日本の台湾認識との相互関係を検討し、その上でその台湾アイデンティティが、戦後にはどのように継続/変容し、それが中華民国の台湾認識といかなる相互関係を有したのか、という点について議論を深めようとしたのではないかと考えられます。
問5 最後に、特に日本と台湾との歴史的な関係に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)に対して、本書の刊行を通じてどのようなことを期待されるでしょうか。
(川島)最近、台湾については「台湾有事」が話題になったり、また日本との関係でも台湾は「親日」などと言われたりすることがあります。そうした話題に関心を持つことはいいのですが、よく聞く議論の「枠組み(フレーム)」にばかりとらわれずに、本書のようにしっかりと一次史料、あるいはエビデンスを踏まえた議論をすることが大切でしょう。例えば、本書を読み進めると、台湾の人たちは「親日か反日か」というフレームそれ自体に疑問を持つようになるでしょうし、またそもそもどうして台湾は「親日」だなどと言われることになったのか、ということ自体に関心を持つかもしれません。そうした疑問を大切にして、自ら調べて、エビデンスに基づく思考を持ってくれる読者がいるとしたら、周さんもきっと幸福を感じることでしょう。
若くして世を去った台湾の研究者が、命を削って上梓(じょうし)した著作が何を訴えようとしているのか。ぜひ本書を手に取って見ていただければと思います。

川島さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、植民地台湾の歴史に興味を持たれた方は、ぜひ『日本の植民地統治と台湾人認識』を手に取ってみてください。






