Commentary
監修者に聞く――川島真さん
周俊宇著、川島真監修・校訂『日本の植民地統治と台湾人認識』(東京大学出版会、2025年8月)
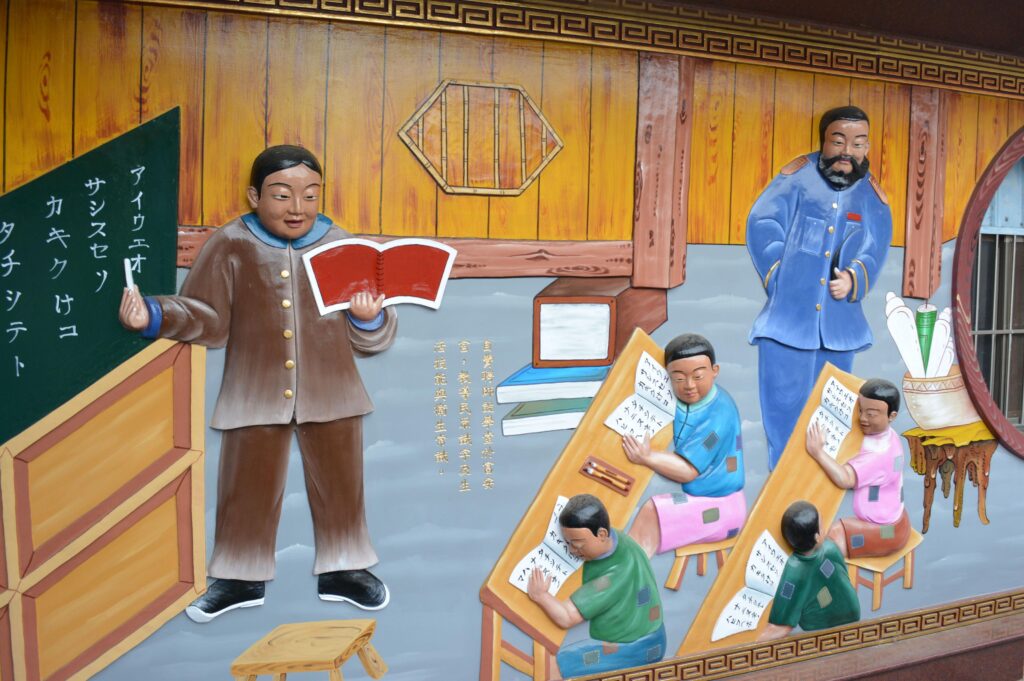
問3 「支那民族性」というキー概念について伺います。「支那民族性」は日本の中国認識をめぐる議論でよくみられるものです。日中関係史研究でこの言葉が重要になるのはわかりますが、台湾史研究、あるいは日本の植民地史研究にとってこの「支那民族性」というキーワードが重要になった背景は何でしょうか。そして、「支那民族性」という言葉を補助線にして日本の台湾支配を考察する場合、時期や局面に応じてどのような論点が析出され、どのような時期的な変化がみられるのでしょうか。
(川島)近代日本では西洋由来ではありながら「支那民族性」という認識が人口に膾炙(かいしゃ)し、日本版オリエンタリズムと言うべき世界観がみられました。このことは日中関係史ではしばしば指摘されますが、日本の台湾統治に対してもその世界観が関わっているのではないか、と周さんは考えたわけです。これは指導教員である私自身とのやり取りの中で出てきた論点という面もありましたが、周さん自身が史料を読む中で、台湾領有前後の日本では台湾の漢族を「支那民族性」という色眼鏡を通して見ていることが見出されていたということがあります(編集部:関連記事として、金山泰志・高柳峻秀「著者に聞く⑩(前)『近代日本の対中国感情』」、同「著者に聞く⑩(後)」もご覧ください)。
次に、例えば日本が1920年代以降に国際連盟などの場において、日本領有以前から台湾に存在していたアヘン吸引の習慣が、日本の統治を経る過程で次第にその習慣がなくなっていったことを強調していることがありました。これらからヒントを得て、「支那民族性」という色眼鏡を通して台湾を見ていた日本も、台湾統治が進むにつれて、次第に台湾の漢族と中国の漢族との違いを強調しなければならなくなるのではないか、という論点を見出していったのです。これも論理的に考えて得られた議論という面もありますし、史料を通して得られた知見という面もありました。少なくとも1920年代くらいまで、近代日本における「支那民族性」は基本的に否定的に捉えられるものでした。
しかし、1930年代の半ば以降状況が変わることを周さんは史料を読み進める中で気づきます。すなわち、日中戦争が勃発すると、確かに皇民化運動などで台湾人に対する「日本人」同化政策が強化される反面、日本の中国や南洋への侵出、統治に際して、日本人たる台湾人が通訳や案内人、時には現地の行政官にも抜擢されるなどするようになると、台湾人の「支那民族性」こそが有用であるということが、日本により発見されるということ、そう言ったことを周さんは見出したのです。ここでは従来否定的に捉えられた「支那民族性」が肯定的に捉えられるようになったとも言えるでしょう。1920年代に台湾人アイデンティティが形成されるということとは裏腹に、近代日本の台湾人認識は中国の漢族とは異なると言いながらも、中国の漢族と重なりがあることがむしろ有用だと思われるようになったということなのです。
このようにして、周さんの博士論文は「支那民族性」という言葉を縦軸にして、近代日本の台湾認識とその変遷を見出すとともに、その変遷が近代日本の中国人に対する「支那民族性」論と強い関係があることを指摘していったわけです。






