Commentary
著者に聞く⑨――島田大輔さん
『中国専門記者の日中関係史』(法政大学出版局、2025年3月)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は日中関係史・メディア史の専門家で、『中国専門記者の日中関係史』の著者である島田大輔さんにお話を伺いました。
問1 まず、本書の主人公と言える太田宇之助について伺います。そもそもなぜ太田宇之助という人物に興味を持たれたのでしょうか。また本書の着想を得たきっかけを教えていただけますか。
(島田)本書のテーマのきっかけは、修士課程までテーマとしていた昭和戦前期日本のイスラーム政策の研究が博士課程入学後、史料的な理由で行き詰まったことにあります。
新しい研究テーマに悩んでいたところ、指導教員の劉傑先生(早稲田大学教授)より「戦前期の雑誌を徹底的に読みなさい」とアドバイスをいただきました。早稲田大学図書館の書庫に籠もり、『中央公論』に始まり、『改造』『文藝春秋』『日本評論』『外交時報』『支那』などを片っ端から読みました。そうした作業の中で、戦前の雑誌の中では中国評論、つまり中国とどういうふうに付き合っていくのかとか、中国が今後どうなるのかといった評論が非常に多いことに気付きました。また、書き手の中に中国問題を専門とする新聞記者がかなり多いことも引っ掛かりました。
何名かの記者が視野に入りましたが、その中でも「これは!」と思った人物が東京朝日新聞記者であった太田宇之助(1891~1986年)でした。太田の評論は、雑誌を散読、乱読していてしばしば目に留まりました。何故なら、彼は、中国が今後どうなるのか、そして日本と中国の関係はどうあるべきかということに関して、ユニークにして、確固たる持論を有していたからです。当時の論壇で主流だった「中国非国家論」(中国人には近代国家形成能力、統治能力が欠如していると決めつける議論)と一線を画す議論を展開していた太田はまさに異色の存在であり、彼の足跡を辿(たど)るのに夢中になったことを覚えています。それが2011年の夏頃で、そこから本研究がスタートしたのです。
ただ、それ以前のことから考えると、学部3回生だった2003年に中国(北京、大連、瀋陽、長春、ハルピン、上海)を旅行したことが大きいかもしれません。特に、上海ではまだ昔の建物が多く残っていた旧共同租界の日本人居住地区(虹口)を歩き回り、日本人居留民に関心を持ちました。ですので、卒業論文は当初、戦前期上海の日本人居留民を研究テーマとしていたのですが、こちらも史料的な理由で行き詰まり、2001年の同時多発テロをきっかけにイスラームへの関心が高まっていたことから、戦前期日本のイスラーム政策にテーマを変更した、という経緯がありました。太田は上海に特派員、支局長として長年駐在した居留民の一人であったので、学部の時に出来なかった研究がやっと博士論文で出来たという考え方も出来ます。
問2 戦前日本の中国専門記者とはどのような存在なのでしょうか。また太田宇之助は、たとえば尾崎秀実などと比較して、どのような点で異彩を放っているのでしょうか。
(島田)中国専門記者とは、中国問題を専門とした新聞記者のことです。戦前期日本の新聞社・通信社は、本社に支那部・東亜部という専門部局、そして、中国大陸に独自の通信網を有していて、そこに属する中国専門記者は、それぞれの中国取材・駐在経験に根ざした報道・言論活動を展開していました。彼等は、中国駐在特派員と本社の中国関連ポストを往復し、中国に関する報道に携わりました。また、その執筆活動は、自社の新聞に止まらず、総合雑誌・専門雑誌等に署名記事を積極的に掲載していました。
土屋礼子先生(早稲田大学教授)によると、現在日本の大手新聞社内で中国関係の部署の地位は必ずしも高くないけども、中国問題が顕在化した1920年代から40年代に関しては、中国専門記者は社内でかつてない程勢力を伸ばしたそうです(土屋礼子「毎日・朝日の二大新聞社における『東亜』の組織と記者たち」『Intelligence』第15号、2015年)。そして、その活動は次第に記者の活動の枠を越え、政府関係の嘱託に就任したり、昭和研究会(近衛文麿のブレーン・トラスト)へ参加したりするなど、様々な形で時局に積極的に関与するようになっていました。当時のメディアを紐解(ひもと)けば、中国専門記者は、中国情報の供給源として非常に大きな位置を占めていたことが分かります。彼等は、陸軍、外務省、実業界の中国通と並んで、戦前期日本の中国通の重要な一要素でした。
この中で、太田が異色だったのは、問1で述べた通り、論壇で主流だった「中国非国家論」から一線を画していたことがあります。太田は、中国を近代化可能な普遍国家と観察し、相互不信に代わり相互信頼の必要性を説きました。そして、日本は中国の国家統一を積極的に援助せよ、との論陣を張りました。これは陸軍の認識とは異なったものであり、論壇の中でも傍流の考えでした。しかし、中国ナショナリズム、国家建設の動向・要望を偏見なく紹介し、日本の中国政策の転換を勧める、太田の中国統一援助論は、中国国民政府と「対話」するためのあるべき「日中相互理解の基盤」とは何か、日本の朝野に警鐘を鳴らすものであり、『大公報』など当時の中国メディアでも好意的に取り上げられたのです。
尾崎秀実との違いは、中国の統一主体をめぐる見解の相違にあります。平たく言えば、太田は中国国民党、国民政府を、尾崎は中国共産党を、それぞれ中国統一主体として着目していたという違いです。両者は、ともに日本国内に蔓延していた「中国非国家論」、そしてそれをもとにした中国侵略政策に批判的であったものの、その中国認識は相容れないものがありました。太田は、早稲田大学在学中の1916年に孫文一派による第三革命に参加しています。そこから太田は大の中国国民党びいきになっています。これは生涯を通じて変わることはありませんでした。特に1930年代には、中国国民政府の統一事業を心から応援するようになります。
問3 関連して、特に参考にした先行研究や史料はありますでしょうか。
(島田)特に参考にした先行研究は、研究を始める頃に出版された、馬場公彦先生(当時、岩波書店)の『戦後日本人の中国像――日本敗戦から文化大革命・日中復交まで』(新曜社、2010年)がまず挙げられます。
同書刊行後に、劉傑ゼミに馬場先生がいらっしゃって、ご著書について報告されたのですが、私から「戦前期はどんな状況だったのか?」と質問をしたんです。そしたら、「それは貴方がやってみたら如何ですか?」と仰っていただいて、それが本書の研究に繋がっています。馬場先生の研究は、雑誌が主体で、私は記者個人が主体という手法の違いはありますが、中国認識研究というものを強く意識したきっかけとなりました。本書でも、太田の戦後を論じる上で、同書に依拠して論じております。
他には、西村成雄先生(大阪大学名誉教授)の「日中戦争前夜の中国分析―『再認識論』と『統一化論争』」(岸本美緒編『岩波講座 「帝国」日本の学知 第三巻 東洋学の磁場』岩波書店、2006年)も参考になりました。これは、1936~37年の中国統一化論争、中国再認識論という中国認識刷新の論壇状況を分析したもので、その中の一人として太田にも言及されています。太田を取り巻く論壇状況を知る上で非常に参考になりました。
太田の史料として、『横浜開港資料館紀要』に2002年から10年にかけて連載されていた、「太田宇之助日記」1940~45年分(望月雅士翻刻)、太田自身の回顧録である太田宇之助『生涯――一新聞人の歩んだ道』行政問題研究所出版局、1981年があり、特に参考になりました。後者は、国立国会図書館にも所蔵がない貴重書です。古書でもほとんど出品されることがありません。太田と私の母校である早稲田大学の図書館には、私の方から寄贈をさせていただきましたが、全国の大学図書館などでも6箇所しか所蔵しておりません。ですが、太田自身の回想録ということで大変参考になりました。後年に書かれた回顧録(二次史料)なので、その記述の信憑性は当然問題になるのですが、太田が戦前期・戦後期に執筆・発表していた新聞記事・雑誌評論や、前述の日記などと突き合わせて慎重に内容を精査した結果、回顧録の記述は信用できるという結論に達しました。
太田の書いた様々なものを読んでいると感じるのですが、彼は非常に正直で真面目な人なんです。だから損することも非常に多いのですが、そうした人柄も回顧録を読むと分かります。拙著と合わせて読んでいただきたいと考えています。これが入手困難というのは残念ですので、どこかの出版社が復刊してくれるといいのですが、太田の知名度の問題で難しいのではないかと考えています。国会図書館にも所蔵されていないので、今後「国立国会図書館デジタルコレクション」に入る可能性もありませんし、太田が1986年まで長生きしていたので、著作権が切れるまでかなり時間が掛かります。
問4 ご研究により、太田の中国認識が、中国と日本をめぐる情勢の変化によって変質していったことも明らかになってきました。その特色と限界について、どのようにお考えでしょうか。
(島田)太田の中国認識は、確かに情勢の変化に応じて変化しています。1920年代には、孫文の唱える中央集権・武力統一に異議を唱え、中国の統一方法として聯省自治論(各省が憲法を制定して独立し、それを単位に聯省政府を作るという、一種の連邦制論)を主張しています。1920年代末の国民革命の躍進とともに、中国国民党の統一事業を応援するようになり、日中全面戦争の開戦(1937年)まで続きました。
しかし、日中戦争の長期化の中で、日本との和平の道を模索する汪兆銘(精衛)政権に期待するようになり、日本陸軍・汪兆銘政権に協力しました。ただし、これは、中国国民党・三民主義を主体とする汪政権を自主独立の政権として強化することで、重慶の蔣介石政権との争点をなくし、全面和平を成し遂げるという目的でなされた方針転換でした。戦後は、国共内戦に伴う中国国民党勢力の敗退と中華人民共和国の成立(1949年)によって、太田は中国情勢に対して定見を失いました。両岸関係に関して中立的な分析に終始し、かつ、論壇からも執筆依頼がなくなり、生きながら忘却されていくことになります。
太田宇之助が目にした中国は常に分裂した中国でした。太田が記者生活を始めた1917年の北京政府と広東政府の南北政府分立に始まり戦後に至るまで、中国国内の政治対立や日本の策動などで、常に何らかの地方政権、あるいは反中央武装勢力が存在し、また、中国が単一国家として完全に統一された時期はほとんどないと言っていいでしょう。しかし、太田はそのような状況において、常に中国統一の重要性と必要性を説きました。そして、太田は日中の平等互恵関係樹立に心を砕き、日中戦争にあたっても、理想を掲げて現地に飛び込み、日中全面和平を達成しようと奔走した人物でした。
太田が中国に対する偏見を持たず、対中国強硬論に陥らなかったのは、第一に、両国の問題を日本本位に考えなかったこと、第二に、中国を特殊国家ではなく普遍国家として日本と同一視したこと、第三に常に双方の利益を考え、「互信互譲」の精神を遵守したことに理由があると考えます。しかし、朝野の中国蔑視は根強く、太田の中国認識が広く受容されるには至りませんでした。ですが、蔑視を超克した中国理解のあり方を一貫して示した太田は、近代日本の中国認識の多様性と可能性を考える上で重要であると考えます。以上が、太田の中国認識の特色です。
対して、太田の限界については、自らの主張を実行に移す政治力、実力を欠いていたことが第一に挙げられます。如何に素晴らしい考えを持っていても、それが実行に移されることがなければ、日中関係は好転しません。日中戦争中の日本陸軍への協力は、そうした状況の改善を求めて、現地に飛び込んだ結果でありました。現地陸軍には太田に好意的な将校もいたにはいたのですが、彼等の賛同をもとに成立した太田肝煎(きもいり)の中国政策も、東京の中央部の反対により頓挫しています。
また、一旦醸成された既成事実を批判せず、その既成事実を所与の前提として立論していったため、その中国認識はある意味では一貫していましたが、ある意味では変質を余儀なくされていた点もあります。特に、日本陸軍が行った満洲事変や華北分離工作に対しては、太田は批判的でありましたが、それら事変・工作によって作られた既成事実そのものは批判しませんでした。
それから、太田が中国共産党を一貫して敵視していた点も限界と言えるでしょう。1936年12月の西安事変の結果としての第二次国共合作に関して、日中戦争が始まるまで否定的でしたし、日中戦争が始まってからも、真の敵は中国共産党と述べ、その撃滅と国共分離を主張しています。太田は、反共リベラルと言ってよい思想的傾向がありました。しかし、個人的な思想はともかく、中国分析にまで中国共産党嫌いが反映されるというのは、中国への見方を歪(ゆが)めるものだったと思います。戦後の中華人民共和国の成立に対応できなかったのは当然と言えるでしょう。
問5 最後に、この記事をご覧の方に、特に近現代の日中関係史に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。
(島田)この中国学.comに先日寄稿された、中村元哉先生(東京大学教授。本書のもとになった博士論文の副査を務めていただいてもいます)の記事「中国近現代史研究者への逆風と活路――一次史料をめぐって」でも述べられていた通り、近年中国では、かつて閲覧が出来た一次史料が閲覧不可能になる、という状況になっています。一方、「抗日戦争与近代中日関係文献数拠平台」のように、かつて、中国国家図書館などでマイクロフィルムをめくるしか閲覧方法がなかった、近代中国の雑誌・新聞などがウェブで閲覧できるなど、利用状況が著しく改善している分野の史料もあります(2025年9月現在。今後こちらも閲覧できなくなる可能性はなくはないと思われます)。
特に、雑誌・新聞などのメディア史料は、日中関係史において、研究のフロンティアと言っていい状況にあります。日本語の雑誌・新聞も、各種OPACやCiNii、そして、「国立国会図書館デジタルコレクション」により、検索・入手が容易になってきております。たとえば、日本の外務省が後援していた戦前期北京の中国語新聞『順天時報』(1901~1930年)は、筆者も参加している「順天時報の会」(世話人は青山治世・関智英両氏)によって、ようやく研究が進んできております。
檔案などの一次史料のアクセスが困難な現在、研究が手薄なメディア史料を用いた研究はもっと増えていっていいと思います。不鮮明な印刷もないではないですが、基本的に活字で記されているので、読解に苦しむこともありません。本書の研究成果も、そうした研究のフロンティアに挑んだ結果でもあります。そういうアプローチもあるんだ、ということを本書から感じ取っていただけると望外の喜びです。
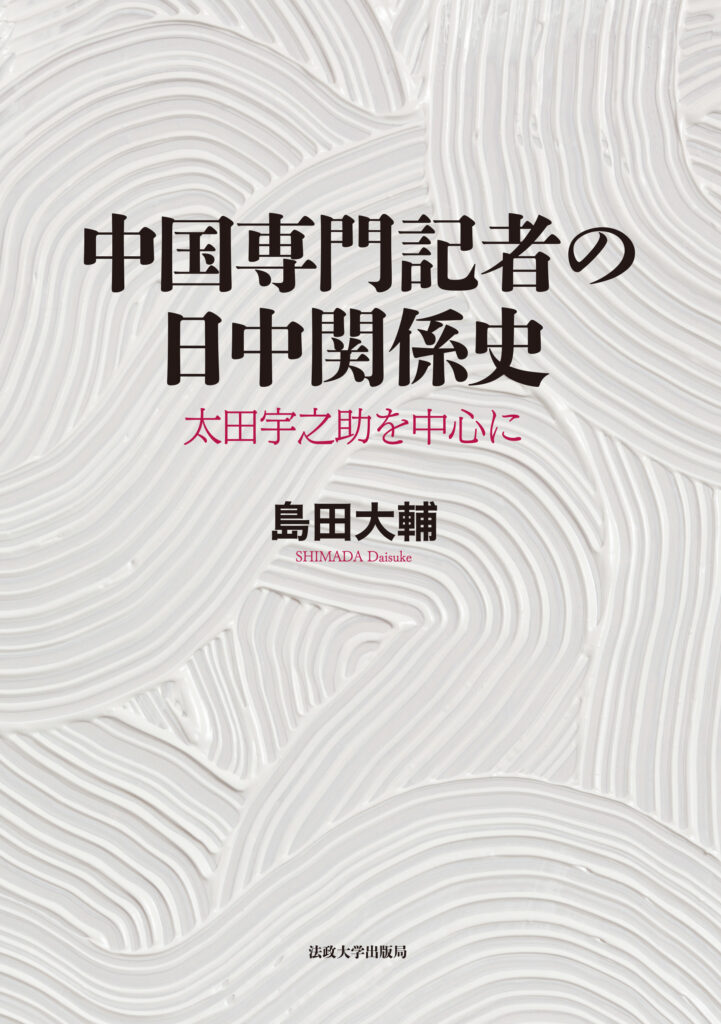
島田さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、中国専門記者という存在に興味を持たれた方は、ぜひ『中国専門記者の日中関係史』を手に取ってみてください。






