Commentary
著者に聞く⑨――島田大輔さん
『中国専門記者の日中関係史』(法政大学出版局、2025年3月)

太田が中国に対する偏見を持たず、対中国強硬論に陥らなかったのは、第一に、両国の問題を日本本位に考えなかったこと、第二に、中国を特殊国家ではなく普遍国家として日本と同一視したこと、第三に常に双方の利益を考え、「互信互譲」の精神を遵守したことに理由があると考えます。しかし、朝野の中国蔑視は根強く、太田の中国認識が広く受容されるには至りませんでした。ですが、蔑視を超克した中国理解のあり方を一貫して示した太田は、近代日本の中国認識の多様性と可能性を考える上で重要であると考えます。以上が、太田の中国認識の特色です。
対して、太田の限界については、自らの主張を実行に移す政治力、実力を欠いていたことが第一に挙げられます。如何に素晴らしい考えを持っていても、それが実行に移されることがなければ、日中関係は好転しません。日中戦争中の日本陸軍への協力は、そうした状況の改善を求めて、現地に飛び込んだ結果でありました。現地陸軍には太田に好意的な将校もいたにはいたのですが、彼等の賛同をもとに成立した太田肝煎(きもいり)の中国政策も、東京の中央部の反対により頓挫しています。
また、一旦醸成された既成事実を批判せず、その既成事実を所与の前提として立論していったため、その中国認識はある意味では一貫していましたが、ある意味では変質を余儀なくされていた点もあります。特に、日本陸軍が行った満洲事変や華北分離工作に対しては、太田は批判的でありましたが、それら事変・工作によって作られた既成事実そのものは批判しませんでした。
それから、太田が中国共産党を一貫して敵視していた点も限界と言えるでしょう。1936年12月の西安事変の結果としての第二次国共合作に関して、日中戦争が始まるまで否定的でしたし、日中戦争が始まってからも、真の敵は中国共産党と述べ、その撃滅と国共分離を主張しています。太田は、反共リベラルと言ってよい思想的傾向がありました。しかし、個人的な思想はともかく、中国分析にまで中国共産党嫌いが反映されるというのは、中国への見方を歪(ゆが)めるものだったと思います。戦後の中華人民共和国の成立に対応できなかったのは当然と言えるでしょう。
問5 最後に、この記事をご覧の方に、特に近現代の日中関係史に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。
(島田)この中国学.comに先日寄稿された、中村元哉先生(東京大学教授。本書のもとになった博士論文の副査を務めていただいてもいます)の記事「中国近現代史研究者への逆風と活路――一次史料をめぐって」でも述べられていた通り、近年中国では、かつて閲覧が出来た一次史料が閲覧不可能になる、という状況になっています。一方、「抗日戦争与近代中日関係文献数拠平台」のように、かつて、中国国家図書館などでマイクロフィルムをめくるしか閲覧方法がなかった、近代中国の雑誌・新聞などがウェブで閲覧できるなど、利用状況が著しく改善している分野の史料もあります(2025年9月現在。今後こちらも閲覧できなくなる可能性はなくはないと思われます)。
特に、雑誌・新聞などのメディア史料は、日中関係史において、研究のフロンティアと言っていい状況にあります。日本語の雑誌・新聞も、各種OPACやCiNii、そして、「国立国会図書館デジタルコレクション」により、検索・入手が容易になってきております。たとえば、日本の外務省が後援していた戦前期北京の中国語新聞『順天時報』(1901~1930年)は、筆者も参加している「順天時報の会」(世話人は青山治世・関智英両氏)によって、ようやく研究が進んできております。
檔案などの一次史料のアクセスが困難な現在、研究が手薄なメディア史料を用いた研究はもっと増えていっていいと思います。不鮮明な印刷もないではないですが、基本的に活字で記されているので、読解に苦しむこともありません。本書の研究成果も、そうした研究のフロンティアに挑んだ結果でもあります。そういうアプローチもあるんだ、ということを本書から感じ取っていただけると望外の喜びです。
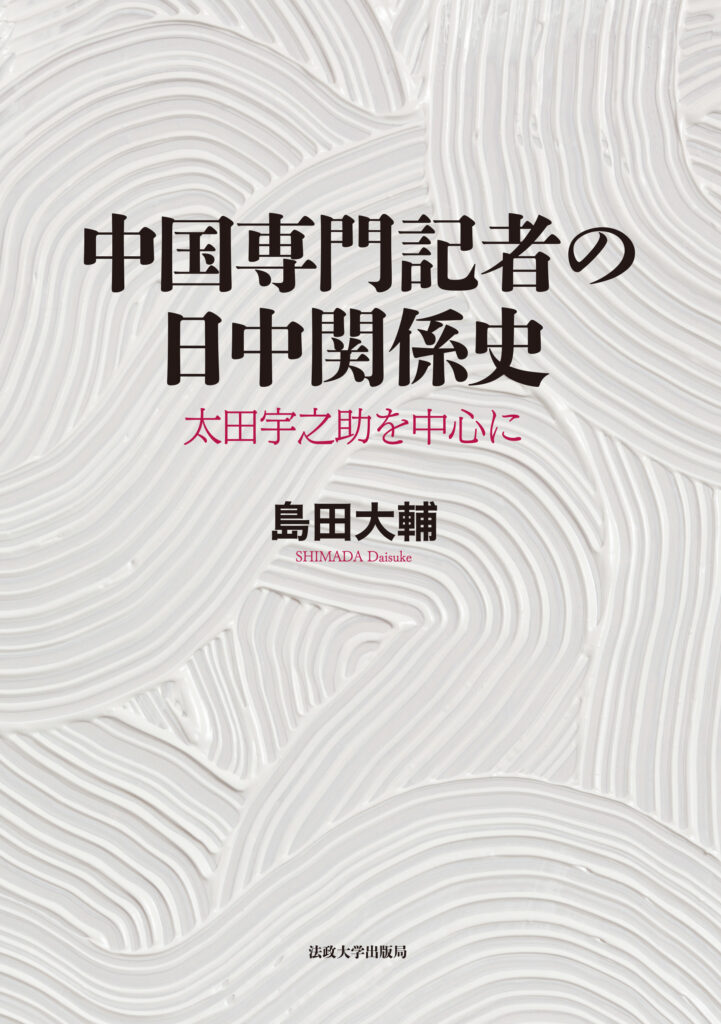
島田さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、中国専門記者という存在に興味を持たれた方は、ぜひ『中国専門記者の日中関係史』を手に取ってみてください。






