Commentary
著者に聞く⑧――田原史起さん
『中国農村曼陀羅』(東京大学出版会、2025年7月)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は農村社会学、中国地域研究の専門家で、『中国農村曼陀羅』の著者である田原史起さんにお話を伺いました。
問1 田原先生は長らく中国農村を研究されてきましたが、本書のタイトルにある「曼陀羅」「円環」というアイデアには何が込められているのでしょうか。
(田原)社会学者の鶴見和子先生の『鶴見和子曼荼羅』(藤原書店)という本からインスピレーションを得ています。ただ、中国語で使用される表記は「曼陀羅」の方なので、こちらを採用しています。また、本書は個人論文集ですが、統一的なテーマで貫かれているというよりは様々なものが混ざり合っており、その意味でも曼陀羅という位置付けが相応しく思えました。
さらに深いレベルで、曼陀羅図は農村でのフィールドワークにも関連してきます。新しいフィールドに入った当初は様々な現象が混沌として渦巻いて見えます。研究フォーカスが定まってくることで徐々に秩序を持ち始め、雑多な要素の中から中心点が現れ、他の要素がそこにつながり関連づけられていくという構造を、序章では「曼陀羅図としての農村」と表現しています。例えば第3章、貴州石村の教育ビジネスの話では、寄宿制私立小学校の創設という「事件」が曼陀羅の中心にあり、その周りを様々な要素が取り囲んで、説明を与え、事件の背後にある事情を深掘りしていく方法をとっています。
また「円環」という概念については、前著『草の根の中国』では「循環」という言葉を使いましたが、農村では何かが「回り続ける」こと、それ自体が大事なんだということをフィールドの観察から見出しています。「円環」も同じで、人や物や情報や資源が回り続けることで暮らしが維持され、問題が起きても村民が無理せず、自分たちのできる範囲で解決し、なんとか生活を回していく、せいぜいその辺りを目標にすればいいのではないか、というメッセージを込めています。
問2 執筆に当たって、特に苦労したことは何でしょうか。
(田原)この本は「執筆」と言っても、第1章だけが書き下ろしで、他は既に発表している文章を選択して組み合わせる作業でした。最初のフィールドエピソード、「豊城農村調査挫折記」は、1996年の江西省留学中に執筆し、未発表のまま30年ほど眠っていた原稿を「発掘」したものです。なので、本を作る際には特に苦労というものはなく、むしろ楽しい作業でした。あえて言えば、自分の気に入っている文章を全部、収録すると膨大な量になってしまうため、セレクトして削っていく作業が一番難しかったです。
問3 「第Ⅰ部 農村ビジネスの郷土性」では、中国各地の農村コミュニティのビジネスが取り上げられています。なかには橋や道路、小学校の建設のような「公共事業」も含まれ、なぜ国費を投じたり、地方政府がやったりしないのかという素朴な疑問が湧きます。こうしたビジネスの「合理性」はどの辺りにあるのでしょうか。
(田原)中国の農村は1960年代から70年代の人民公社時代、「自力更生」を強いられる状況の中で、政府に期待せず自分たちで問題を解決する習慣を持っています。
公共問題を解決するための資源の三領域として「公」(政府)、「共」(コミュニティ)、「私」(市場)がありますが、自力更生が主体となった中国の農村では、「共」がそのベースにありました。一方で、市場経済化が進む中で、農村住民自身による「農村ビジネス」が、商売の論理を通じて公共的な問題を解決するような流れも存在していて、とても面白いと思っています。
これが第一部の内容ですが、大事なことは、農村ビジネスというものが農民の家族主義とも結びついていることです。つまり農村から叩き上げて成功した人が地元の名士になると、郷土の歴史に名前を残したいというモチベーションから橋や道や学校など「公共的な」事業に貢献するようになります。これは純粋な公共心というより、明清時代の「郷紳(きょうしん)」に連なる歴史的なDNAとして、彼らが持っている価値観の延長線上にあるものです。
問4 「第Ⅰ部」と「第Ⅱ部 県域社会と文化心理」を中心に、社会主義化を経た中国の農村と県城を舞台とする文学作品を取り上げています。こうした手法をとった狙いは何でしょうか。
(田原)現在の中国の政権下ではフィールドワークがほとんど不可能な状態にあるため、文学作品を通じて研究する手法を思いつきました。
農村を描写した文学作品や映画は非常に豊富で、農村研究の資料として価値があります。また、世には「農村問題」を論じる政府や知識人、メディアの声は溢れかえっていますが、基層幹部や農民自身は自分の気持ちや考えを書くことがほとんどありません。そこで次善の策として、路遥や閻連科、賈平凹など農村出身の作家が農民の声を代弁してくれているような文学作品が浮かび上がってきます。第二部で試みたような文化心理の領域に関わる研究の手段としても、文学作品は大きな可能性を持っていると思います。
問5 「第Ⅲ部 比較のなかの中国農村」では、都市=農村間の人の流れや、ガバナンスの個性などについて、ロシア・インドとの比較を行っています。比較をすることによって、中国の農村のこれまで意識されなかった側面も明らかになったのでしょうか。
(田原)中国では都市が憧れの対象で、農村的要素が後進的とみなされ蔑視される傾向がありますが、ロシアとの比較によって、これは当たり前ではなく、それぞれの社会構造や社会主義の道筋、歴史的経験の違いによるものだとわかります。ロシアでは都市と農村の間の人的環流が活発であった結果、中国のような都市優位・農村蔑視の文化心理が生まれなかった点が明らかになりました。
インドとの比較では、選挙の有無が公共問題の解決の仕方(ガバナンス)や、ひいては両国の農村住民の政治的性格の違いに影響を与える点が見えてきました。
中国人や中国研究者に、中国には競争選挙がない、という点を指摘しても、「それがどうした?」という反応をされます。当たり前すぎるのでしょう。インドでは1952年の第1回総選挙以来、70年以上も競争的な選挙が実施され、ガバナンス資源の多くは選挙を通じて村に引き込まれます。投票により自分たちの生活が変わる経験を繰り返しているので、農村の人々は政治化されています。
一方、中国では選挙による政権交代のオプションがないからこそ、経済活動に特化し家族の発展に注力する「家族主義」が生まれています。しかし、政治参加を通じて生活を変えようとする発想が人々にないのは、国際的に見れば決して「当たり前」ではないのです。家族主義や関係(コネクション)主義が発展するのは決して単なる「文化」の問題ではなく、政治システムがもたらした帰結でもあります。
このように比較研究によって、中国だけを見ていては気づかない、現象の新しい説明の仕方が可能になるのです。
問6 本書では直接の比較対象にはなっていませんが、日本の農村に対する気持ちも強く感じました。「農村問題の解決」ではなく「農村を通じた問題の解決」という意味で、(大げさな言い方かもしれませんが)農村の持つ可能性について、本書を通じてどのような知見が得られたのでしょうか。
(田原)序章と「あとがき」にも記した通り、私は広島県の農村出身で、故郷は正真正銘の田舎です。
最近思うのは、逆説的ですが、「可能性が小さい」ことこそが農村の「可能性」なのではないかと。農村は都市に比べて選択肢が限られていますが、だからこそ工夫が生まれ、制限された状況の中で、覚悟を決めて主体的に生き方を考える力が育まれるのではないか。
例えば、東京では中学受験をする子どもが多くおり、学校の選択肢が多すぎて悩んだ挙句、公立中学に行ったら人生終わりだ、みたいな考えをする親がいて、子どもに勉強を強制したりして不幸な状況が生まれることがあります。地方の農村ではそもそも中学受験などという選択肢が存在しません。ある意味限られた、制限された環境からスタートすることは、人間であれば多少の差こそあれ共通しているわけです。
なんの制約もない、無限の可能性に恵まれた人などそうそういるものではありません。逆に制限があればこそ工夫して、主体的に生きることにもつながります。農村という場に意味があるとしたら、そういった点を思い出させてくれる点にあるのではないでしょうか。
問7 最後に、この記事をご覧の方に、特に農村を研究対象とすることに興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。
(田原)序章で述べた通り、農村研究には「方法としての農村」と「問題としての農村」という二つの側面があります。
「方法としての農村」について、ある地域の特徴にアプローチする際、とりわけ中国やインドやロシアのような広大な農村を抱える国の特質を理解するには、社会のベース、基層である農村から接近する必要があるということです。マンションに住み、自家用車に乗り、ホワイトカラーの職を持つ都市の中産階級のメンタリティは国を超えて似通っていますが、農村の家族や村落にはその地域の文化や社会的結合の特徴がより明確に表れてきます。農村は地域研究の題材の宝庫と言えます。
次に「問題としての農村」ですが、一国の中で農村は単なる都市部の残滓(のこりかす)ではなく、貯水池、安定装置、待避場所、あるいは新しい価値創造の場所でもあります。現実に、農村は高齢者や障害者、独身男性、貧困層、被差別者など社会的弱者が集中する場所でもあり、そうした人々が生きる場所としての農村の可能性を探求することは実践的な面でも重要なテーマです。毛沢東は知識青年の「上山下郷」に際して、「広大な農村には大いなる可能性がある」(広大農村、大有可為)とのスローガンを用いました。
都会育ちの読者の方には地味で魅力に乏しい分野に見えるかもしれませんが、その分、農村研究は競争者の少ない「スキマ産業」でもあり、手付かずの研究テーマが多く転がっているはずです。
付記:本書に関して、著者によるブックトークの映像が公開されました(https://www.youtube.com/watch?v=ccet-hiwyoc)。こちらもあわせてご覧ください。
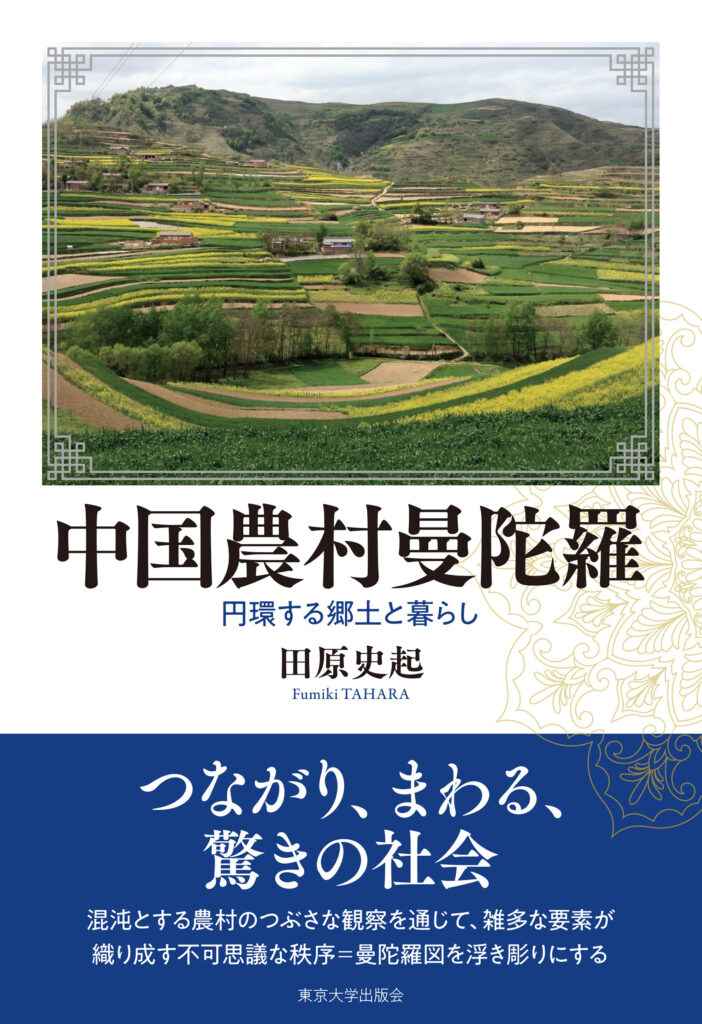
田原さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、都市とは異なる農村社会の秩序に興味を持たれた方は、ぜひ『中国農村曼陀羅』を手に取ってみてください。






