Commentary
著者に聞く⑦――岩間一弘さん
『中華料理と日本人』(中央公論新社、2025年6月)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は東アジア近現代史・食の文化交流史の専門家で、『中華料理と日本人』の著者である岩間一弘さんにお話を伺いました。
問1 そもそも、なぜ中華(中国)料理の歴史に興味を持たれたのでしょうか。下世話な質問になってしまいますが、何か思い入れのある中華(中国)料理はありますか。
(岩間)中華料理は、多くの中国研究者にとってそうであるように、私にとっても元気の源です。仕事でストレスがたまったときや気分転換したいときには、横浜中華街で本格中華を、あるいは池袋北口で「ガチ中華」を思いきり食べると、すぐにリフレッシュできます。さらに中華料理は、日本にいても海外にいても、夕食のおかずのローテーションには欠かせない存在です。
思い返してみますと、私は学生時代から、身近で具体的なものを出発点にしながら、都市史や中国史、日中交流史、さらには東アジア史といったより広いテーマへと視野を広げていたようです。何度も上海に長期留学した経験もあり、中華料理に関わる文化や歴史を研究テーマにすることは、ある意味で必然だったようにも思われます。
また、私たちの世代は、日中間の平均収入の格差が大きく、円高元安の時代に中国に留学していたため、庶民的な家庭料理から高級な宴会料理まで、さまざまな美味しい料理を存分に味わうことができました。これはとても恵まれた経験だったと思います。私はけっして美食家でもなければ、味覚が鋭いわけでもありませんが、中華料理に関してだけは、少し舌が肥えたように思います。
思い入れのある料理を挙げるとすれば、1995年に初めて中国に長期留学したときによく食べていた、紅焼肉(中国版・豚の角煮。上海ではとくに「紅焼小排〔小さいスペアリブ〕」)、西紅柿炒鶏蛋(トマトと卵の炒め物)、酸辣湯(スアンラータン、スーラータン)などでしょうか。日本で慣れ親しんでいた中華料理とは異なる、現地の「家常菜」(家庭料理)を初めて知り、毎日のように飽きずに食べていました。
もちろんそれと同時に、小さい頃から食べ慣れている餃子、肉まん、ラーメンといった日本式の中華料理も、日々の食事に欠かせないメニューです。本書では、日本の人々が特定の中華料理を「定番」として親しみ、強い思い入れを抱くようになった経緯を、東アジアの近現代史の文脈のなかで考えています。
問2 ここで用語について整理させてください。例えば、前著の『中国料理の世界史』では中国の料理を「中国料理」と呼んでいます。「中国料理」と「中華料理」とでは、何がどのように違うのでしょうか。
(岩間)「中国料理」と「中華料理」の違いについては、講義でもよく質問されるのですが、実のところ厳密に定まった用法があるわけではありません。例えば2019年に刊行した『中国料理と近現代日本』では、1960年代から本格的な料理を提供する大店舗が「中国料理」と称し、個人経営店の簡易な「中華料理」と差別化していたことに注目し、全体を通して「中国料理」で統一しました。
また2021年の『中国料理の世界史』でも、現代中国では「中国菜」「中餐」「中華美食」など多様な呼称が用いられ、「中華料理」という言葉がとくに日本の中華料理だけを指す場合もあることから、混乱を避けるために「中国料理」で統一しました。
しかし1990年代以降、「中華料理」という呼称の方が「中国料理」よりも一般的に使われるようになっています。実際、本書では主に日本の中華料理を扱っており、しかも本格的な高級料理ではなく、軽食や惣菜といった日常的な料理が中心ですので、「中華料理」という言葉の方がふさわしいと考えました。
くわえて、もう一つ重要な点として、1936年に東京の中華料理店を論じた中国の雑誌記事に、「支那の二字にはひどく侮辱する意味が含まれており、華僑の経営する店では皆“中華料理”と呼ぶことで愛国心を示している」と記されていました。
これまで、日本では日中戦争以降に「支那料理」から「中華料理」へと呼び名が変わったと考えていましたが、戦前からすでに中国人経営者が意識的に「中華料理」と名乗っていたことがわかったのは、意味ある発見だったと思います。
問3 執筆に当たって、特に苦労したことは何でしょうか。また、それをどのように克服されたのでしょうか。
(岩間)一つ目は、中華料理に込められた日本人の思いのようなものを、文献史料から読み解こうとした点です。
しかし、定番の中華料理であっても、そうした精神面に言及した史料はあまり多くありませんでした。さらに、個人的な体験や感想にとどまらず、より広い世相や社会の変化と結びついた思いが語られるケースは、非常に限られていました。
本書で取り上げた肉まん、ジンギスカン、餃子、ウーロン茶、シュウマイ、ラーメンなどは、料理を作る人・食べる人・語る人々の思いや、当時の時代状況を探るうえで、貴重な例となりました。
二つ目は、やや無謀だったのかもしれませんが、日本の中華料理とその社会的背景を、日本史の枠にとどめず、世界史のなかに位置づけようとしたことです。
そのため、欧米のフード・スタディーズ系のジャーナルに論文を投稿させていただいたり、イギリスの大学で発表させていただいたりしながら、分野も国籍も異なる研究者の方々からいただいたフィードバックをもとに議論を深めようとしました。
専門分野が異なる研究者から、英語で容赦なく批判されることもあり、しんどい思いもしましたが、日本国内ではなかなか得られない有意義な視点に触れることができ、大きな刺激となり、良い学びの機会にもなりました。
問4 章ごとに個別の料理を紹介する叙述の方法が、本書の内容をわかりやすく、魅力的にしていると思います。ただ、第2章で取り上げた「ジンギスカン」は、中華料理と結びつかないのですが、当初は中華料理(あるいは「支那料理」)として紹介されたのでしょうか。
(岩間)ジンギスカンについては、ゼミの学生からも、なぜ東アジア史の研究に必要なのかと尋ねられたことがありますが、実は1940年代頃までは完全に中華料理として認識されていました。ところが、1950年代に餃子と並んで全国的に普及し始めると、そのルーツはしだいに忘れられていきました。
数ある中華料理のなかでも、ジンギスカンほどドラマチックな経歴をもつ料理は珍しく、もし人物だったら映画の主人公になっていたかもしれません。20世紀初頭の北京で、日本人が羊肉の炙り焼きに「成吉思汗」(ジンギスカン)という勇ましい名前を付けたことによって、この料理の運命は大きく変わりました。のちに満洲国の名物料理とされ、日本陸軍によって戦意高揚のための宣伝にも利用されました。
現在では、北海道の郷土料理として親しまれ、北海道遺産にも認定されています。時代や地域によって意味づけが大きく変わってきた料理の一例として、ジンギスカンはとても象徴的な存在だと思います。
問5 中国料理が世界中で食べられるのは、中国からの移民の持ち込んだ食文化が、現地の食文化とも融合したことが要因と言われます。一方で日本の中華料理は、満洲(現在の中国東北部)などからの引揚者や、中国大陸での従軍経験者のような日本人も重要な担い手となった点が、大きな特徴と言えるかもしれません。同様の事例は世界でも見られるのでしょうか。
(岩間)日本の中華料理の普及には、大きく分けて二つの系統があります。一つは、華僑・華人がチャイナタウンを拠点に広めたもので、もう一つは、日本人自身が中国大陸や台湾で知った料理を国内で広めたものです。とくに日本では、第二次世界大戦以前から、日本人が調理する中華料理が多く見られたのが特徴的です。
前著『中国料理の世界史』でも紹介しましたように、中華料理は各地の食材や嗜好に応じて自在に変化できる柔軟性をもち、それを強みとして世界に広がってきました。例えば、中国の麺料理は、東アジアや東南アジアの各国で独自の「国民食」へと進化しています。日本のラーメン、韓国のチャジャン麺(炸醤麺)、ベトナムのフォー、タイのパッタイ、フィリピンのパンシット、マレーシアやシンガポールのラクサなどが代表例です。
また、第二次世界大戦後の日本では、中国大陸からの引揚者が、餃子やラーメンなどの中華料理を広めていきました。こうした動きは、イギリス人が旧植民地インドから持ち帰ったカレーや、オランダ人がインドネシアから持ち帰ったライスターフェルと共通する点があります。つまり、日本の中華料理のなかには「植民地食」と呼べるものがあり、それはヨーロッパにも類例が見られます。
さらに、日本人が中華料理を好んで食べるだけでなく、料理人としても受け入れやすかった背景には、東アジア共通の食文化があると考えられます。例えば、米を主食とし、穀醤系の調味料を使い、箸を用いるといった共通点が挙げられます。日本によく似た現象は韓国でも見られます。1970年代以降、韓国人の中華料理店経営が広がり、黒くて甘いチャジャン麺や、赤くて辛いチャンポンといった、韓国独自の中華料理が確立されました。
とはいえ、中華料理の世界的な普及において、華僑・華人の貢献がきわめて大きいことは言うまでもありません。1980年代の日本では、ラーメンの発明や輸出に代表される日本人の創意工夫を称賛する「ラーメン・ナショナリズム」とも呼ばれる風潮が強まりました。しかし、ラーメンが日本の国民食となり、さらに世界食へと発展するには、日本以外のアジア系の人々の存在が不可欠であったことも、忘れてはならないと思います。
問6 私たちの胃袋を満たし、癒やしてくれる中華料理が、植民地や戦争の歴史と深く関わることがわかり、ギクリとさせられる部分もあります。それと同時に、こうした中華料理が郷土料理として日本に根付いているのも事実です。食文化の継承や活用という面で、本書の執筆の過程で意識されたことはありますか。
(岩間)日常生活のなかで慣れ親しんでいる中華料理の受容が日本帝国の盛衰と関わっていたことは、海外の研究者によって指摘されています。しかし、それがどこまで正しいと言えるのか具体的に検証されることがあまりなく、日本ではそのような議論自体がほとんど無視されてきたのではないかと思います。
中華料理を舌、心、頭で味わうとしましたら、「おいしい」「心地いい」「面白い」だけではすまされない、より現実的な側面にも目を向けなければなりません。それは歴史の暗部にも関わり、自省的な議論も必要になります。
こうした話題は、日本の読者に感情的な反発や拒否反応を起こしてしまうのではないかと、私自身、恐れていました。けれども、近現代の日本食文化の形成は、帝国主義(植民地主義)やポスト帝国主義(ポストコロニアリズム)の視点を抜きにして十分に論じることはできない、という結論に至り、覚悟を決めました。
帝国や戦争があったからこそ、ダイナミックな文化交流が起きたのも事実です。日本の中華料理は、その最大の産物の一つです。正の歴史も負の歴史も、ともに忘れたり隠したりせず、正確に知り、伝えることが重要です。
ノスタルジアを楽しんだり、文化遺産を大事にしたりすることはもちろん大切です。しかし、それらを歴史と混同してはならないと思います。これはけっして自然にできることではなく、日本の中華料理の歴史を書きながら、難しさを改めて実感しました。
また、ご指摘のように日本では多くの中華料理が、「郷土料理」「遺産」「資産」「ご当地人気料理」「100年フード」などに公式に認定されています。これらの日本の食文化を未来へ継承していく制度は、法的な保護や教育支援の仕組みを強化することが課題とされています。そこにくわえて大切なのが、料理や食べ物にまつわる伝説や美化された物語だけでなく、きちんとした史実を伝えていくことだと思います。
問7 最後に、この記事をご覧の方に、特に日本と中国との文化交流史に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。
(岩間)私たちの学生時代と比べると、現在ではインターネットが急速に発展し、調査や研究が格段にやりやすくなりました。しかしその一方で、言論空間の性質そのものも変化し、私たちの書いた文章が、時として日本や中国の匿名的なネット空間において、多様な反応や解釈の対象となることも増えてきました。
私のように食文化史を扱う研究であっても、中国のネット上では「日本人が勝手なことを言っている」といった批判的な反応が広がり、議論を呼んだことがありました。私の本の中国語版では、一部が削除されることもありました。一方、日本のネット上では、「中国側の主張を無批判に受け入れている」といった否定的な意見が寄せられたこともあります。
日中関係が緊張するほど、日中間の交流にたずさわる人たち、つまり中国を知る日本人と日本を知る中国人は、困難な立場に立たされがちです。日中交流やその研究では、いまだ共通の土台が十分に築かれておらず、多くの課題が残されています。
例えば、わりと最近の授業でも、戦前の史料に出てきた「支那」という言葉を、日本人学生が無意識に何度も口にし、中国人留学生が驚いた様子で顔をこわばらせていた、という出来事がありました。日本では、アジアに詳しい人であっても、「支那」という言葉が中国の人々に強い拒否感を引き起こす可能性があることに無自覚な場合があります。一方で、中国の人々のなかには、日本人が過去の歴史についてまったく反省も謝罪もしていないと考えている人もいます(編集部:「支那」「中国」呼称が中国人にとって持つ意味については、本サイトの石井剛「中国学とSinology」もあわせてご参照ください)。
近年では、さまざまな圧力や検閲を恐れて、核心的な問題にますます踏み込みづらくなっていると感じます。日中交流は、日本の中華料理や中国でも人気になった日本料理など、注目すべき実質的成果を生み出し、両国の人々の生活を豊かにしてきました。もちろん無理をすべきではありませんが、それでもなお「実事求是」、つまり事実に即して真理を追究する、情熱と冷静さを併せ持った姿勢が、今、日中交流史研究においていっそう求められていると感じています。
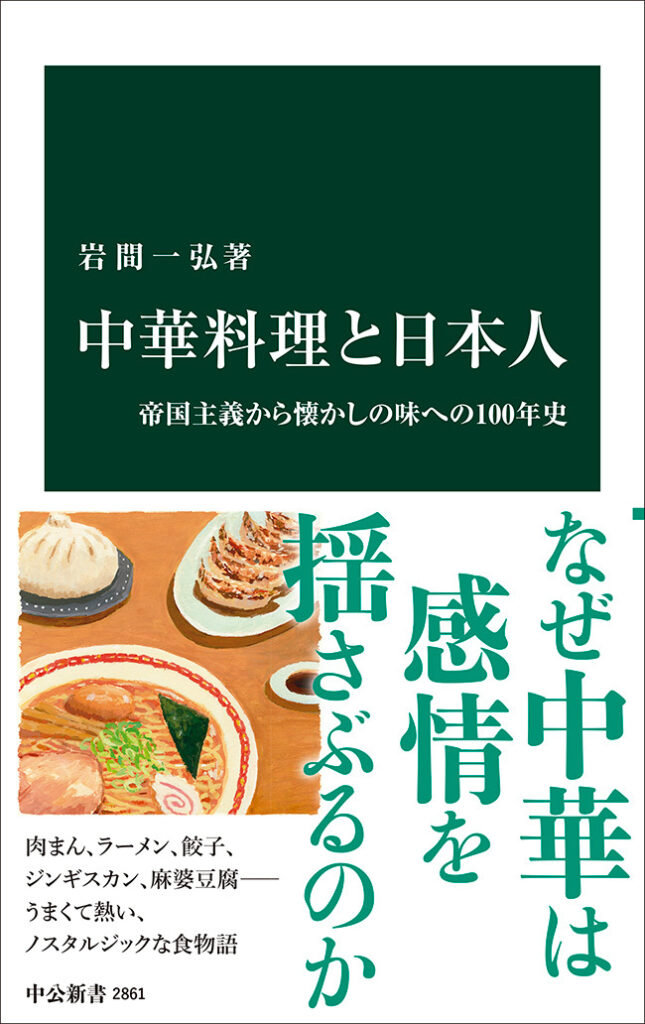
岩間さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、身近な食文化である中華料理の歴史に興味を持たれた方は、ぜひ『中華料理と日本人』を手に取ってみてください。






