Commentary
著者に聞く⑦――岩間一弘さん
『中華料理と日本人』(中央公論新社、2025年6月)

帝国や戦争があったからこそ、ダイナミックな文化交流が起きたのも事実です。日本の中華料理は、その最大の産物の一つです。正の歴史も負の歴史も、ともに忘れたり隠したりせず、正確に知り、伝えることが重要です。
ノスタルジアを楽しんだり、文化遺産を大事にしたりすることはもちろん大切です。しかし、それらを歴史と混同してはならないと思います。これはけっして自然にできることではなく、日本の中華料理の歴史を書きながら、難しさを改めて実感しました。
また、ご指摘のように日本では多くの中華料理が、「郷土料理」「遺産」「資産」「ご当地人気料理」「100年フード」などに公式に認定されています。これらの日本の食文化を未来へ継承していく制度は、法的な保護や教育支援の仕組みを強化することが課題とされています。そこにくわえて大切なのが、料理や食べ物にまつわる伝説や美化された物語だけでなく、きちんとした史実を伝えていくことだと思います。
問7 最後に、この記事をご覧の方に、特に日本と中国との文化交流史に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。
(岩間)私たちの学生時代と比べると、現在ではインターネットが急速に発展し、調査や研究が格段にやりやすくなりました。しかしその一方で、言論空間の性質そのものも変化し、私たちの書いた文章が、時として日本や中国の匿名的なネット空間において、多様な反応や解釈の対象となることも増えてきました。
私のように食文化史を扱う研究であっても、中国のネット上では「日本人が勝手なことを言っている」といった批判的な反応が広がり、議論を呼んだことがありました。私の本の中国語版では、一部が削除されることもありました。一方、日本のネット上では、「中国側の主張を無批判に受け入れている」といった否定的な意見が寄せられたこともあります。
日中関係が緊張するほど、日中間の交流にたずさわる人たち、つまり中国を知る日本人と日本を知る中国人は、困難な立場に立たされがちです。日中交流やその研究では、いまだ共通の土台が十分に築かれておらず、多くの課題が残されています。
例えば、わりと最近の授業でも、戦前の史料に出てきた「支那」という言葉を、日本人学生が無意識に何度も口にし、中国人留学生が驚いた様子で顔をこわばらせていた、という出来事がありました。日本では、アジアに詳しい人であっても、「支那」という言葉が中国の人々に強い拒否感を引き起こす可能性があることに無自覚な場合があります。一方で、中国の人々のなかには、日本人が過去の歴史についてまったく反省も謝罪もしていないと考えている人もいます(編集部:「支那」「中国」呼称が中国人にとって持つ意味については、本サイトの石井剛「中国学とSinology」もあわせてご参照ください)。
近年では、さまざまな圧力や検閲を恐れて、核心的な問題にますます踏み込みづらくなっていると感じます。日中交流は、日本の中華料理や中国でも人気になった日本料理など、注目すべき実質的成果を生み出し、両国の人々の生活を豊かにしてきました。もちろん無理をすべきではありませんが、それでもなお「実事求是」、つまり事実に即して真理を追究する、情熱と冷静さを併せ持った姿勢が、今、日中交流史研究においていっそう求められていると感じています。
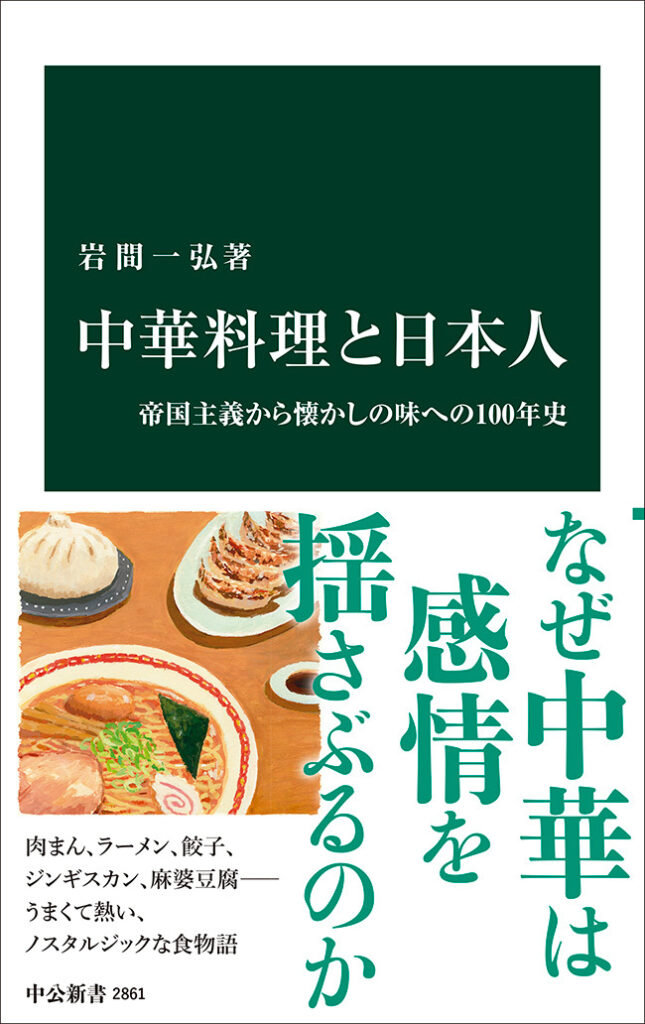
岩間さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、身近な食文化である中華料理の歴史に興味を持たれた方は、ぜひ『中華料理と日本人』を手に取ってみてください。






