Commentary
著者に聞く⑥――黄喜佳さん
『中国共産党中央局の研究』(東京大学出版会、2025年3月刊)
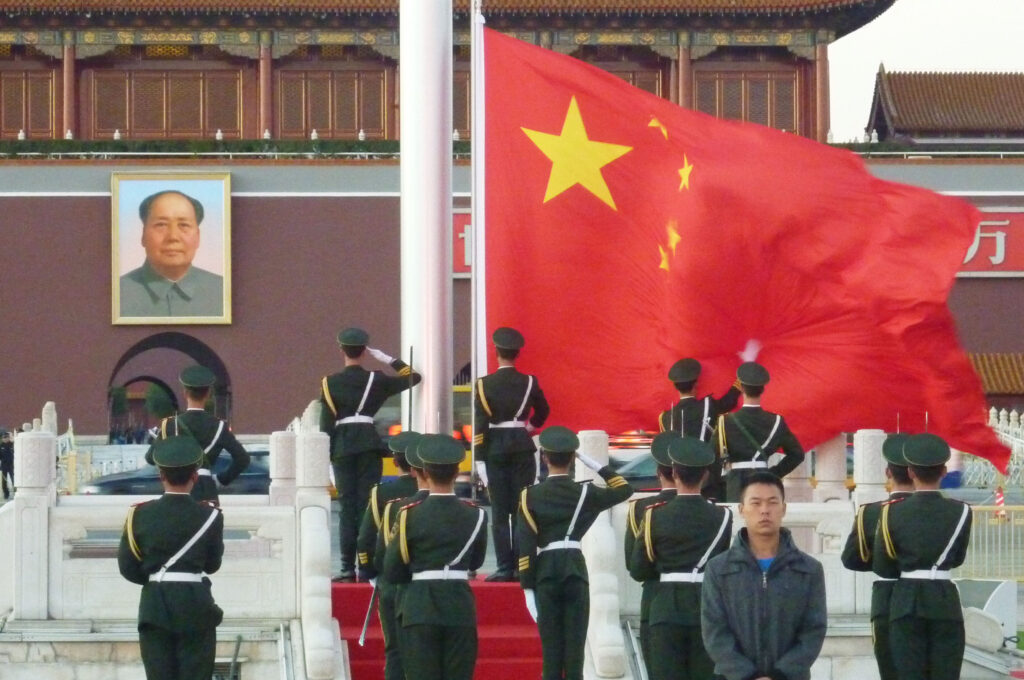
中国学.comでは、現代中国および中国語圏の関連研究の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は中国政治論・現代中国政治外交史の専門家で、『中国共産党中央局の研究』の著者である黄喜佳さんにお話を伺いました。
問1 そもそも中国共産党中央局(以下、中央局)とは、どのような組織なのでしょうか。なぜ中央局に興味を持たれたのでしょうか。
(黄)まず、「中央局」という呼び方について説明したいと思います。私が本書やその基となった博士論文を執筆した際に、この組織を「中央局」と呼ぶべきか、あるいは「中央の地方局」と呼ぶべきかについてかなり悩んでいました。なぜならば、やはり「中央」という語を使うかどうかによって、この組織に対する第一印象もかなり変わると思ったからです。例えば、よく中央局と混同されるものとして、中国共産党の最高意思決定機構である「中央政治局」があります。ここで言う「中央局」とは、それとは別の組織です。
中央局は1949年から1966年の間に、複数の省の党、政府、軍隊を統括する六つの党組織(東北、華北、西北、華東、中南、西南)として存在した組織です。前身となる組織は1920年代から設立されていましたが、ここでは中央局とはどのような組織かを説明するために、①党規約、②メンバーの構成、③実際の活動という三つの側面から見ていきましょう。
まず①について、1920年代に中国共産党は中国国民党の弾圧を受けて、各地の組織が崩壊に追い込まれました。それを背景として1928年に採択された中国共産党の党規約では、中央局は実際の必要に応じて設立される党中央の派遣機構であると明記されています。この規定の意図は、中央局と地方党委員会の区別をつけることにありました。中央局の存続期間や具体的な活動については記述がありませんが、あえて明記を避けたのは、柔軟に組織を活用するためであったと考えられます。つまり、中央局は当初、臨時的な「中央からの特使」と位置づけられたわけです。
ところが、中央局の性質は日中戦争と国共内戦の間に変化しつつありました。中央局の存続期間が延びただけではなく、戦争の長期化によってその機能は党組織の管理から軍事活動や政府部門に対する指導(中国語では「領導」、以下同じ)にまで拡大しました。つまり②について、この時期から、中央局は中央から派遣される名義上の代表でありながらも、人事上も組織上も地方党組織と多くの重複が見られるようになります。こうして、中央局は中央の派遣機構でありながらも、地方党委員会の人事と組織を基盤とする、中央と地方の両面性を持つ機構になりました。このことは③に関わることですが、当時の実際の活動を詳細に見れば、中央局は常に中央・地方の間を仲介し、中華人民共和国建国(1949年)後の多くの政治事件においてパワーバランスを取る役割を果たしてきたことが分かります。
また、特に説明しなければならないことは、中央局の名称は時代や目的に応じてしばしば変わっていたことです。例えば、1949年までは「地名+中央局」(例えば晋察冀中央局)、建国後は「中共中央「地名」+局」に改めて統一されました。その名称の統一にも、もちろん党中央の意図が反映されています。そのため、この組織を何と呼ぶかは悩ましい問題なのですが、しかし結局は、当時の状況を重視するためにも、本書で主に取り上げた1950、60年代の公式文書でよく使われる「中央局」の呼び方に従うことにしました。読者の方々には、そうした言葉に込められた、当時の党中央の政治意図を感じ取っていただければと思っています。
中央局の話を始め出すとなかなか話が止まらないのですが、私自身が中央局に興味を持ったきっかけはなぜか、というご質問への回答に戻りたいと思います。私は台湾出身ですが、日本に留学に来てから現代中国の政治を本格的に勉強し始めました。最初は右も左も分からない状態でしたので、ひたすら1949年から1966年までに発表された重要な公文書を収録した『建国以来重要文献選編』や『毛沢東年譜』を読んでいました。そこで、文書の伝達の対象はほとんどが「各中央局、各省、市、自治区党委」となっていることに気づきました。さらに、中央局書記を意味する「大区書記」もその時代の指導者の年譜や伝記に頻繁に登場しています。ところが、中央局はこれほど多くの文書で言及されているにもかかわらず、省レベルの政府ほどは注目されていませんでした。それはなぜか、という単純な疑問と好奇心から私はこの研究課題に着手したのです。
問2 「集権と分権を架橋する広域統治機構」というサブタイトルが、中央局の基本的な性格を表していると思われます。成立直後の中華人民共和国でこのような組織が必要とされた背景は何でしょうか。
(黄)成立直後の中華人民共和国は、一部の地域で続いていた軍事行動や、全く異なる事情を持つ各地方において新たな政治、経済体制を築き上げるという深刻な課題に直面していました。そのいずれの課題に対しても、中央局の存在は不可欠でした。先ほどの話とも関連しますが、中央局は戦争期間中にあっても、複数の省にまたがる党、軍隊、政府機構を指導するのに重要な役割を果たしてきました。各種の機能が高度に融合されていた中央局の組織構造は、依然として戦争状態を脱しきれない状況において、中央にとって必要とされた一つ目の理由として挙げられます。
また、中央指導部としては、集権的な体制の構築よりも、随時柔軟な調整を行える体制を目指していたことが二つ目の理由です。例えば一般的には「統一」「集中」などの言葉が党中央指導部によって積極的に評価されていると思われがちですが、建国当初の中央指導部は、実際には高度な集権制を構築することを前提とはしていませんでした。
現代中国の政治史では、1949年から52年を建国直後の復興期、53年から57年の第一次五カ年計画を中央集権の時期と区分しています。こうした区分には、必然的に中央集権に向かうとする歴史観が反映されていると考えます。そのため、建国直後の地方制度の中核であった中央局は、最初から廃止されるべき、やむを得ない暫定措置にすぎないと説明されてきました。しかし実際には、中央指導部は中央集権的な管理制度のみに頼るのではなく、効果的な統治システムの運営を保つために、地方の利益を向上させ得る中央局の機能を保持し続けようとしていました。その後、建国直後に起こった権力闘争としてよく知られている「高崗・饒漱石事件」(54年)の影響によって、しばらくの間中央局の活動は中止しましたが、3年足らずのうちに、また類似した枠組みが復活しました。このことにも、中央局のような組織は単なる暫定措置ではなく、中央指導部にとって重要な統治手段としてみなされていたことが表れています。
問3 執筆に当たって、特に苦労したことは何でしょうか。また、それをどのように克服されたのでしょうか。
(黄)特に苦労したことは、何よりも中央局の活動を裏づける資料の収集でした。そもそも最初は、どのような資料が存在しているのかを把握することも困難でした。何とか手がかりを得て、執筆開始後に香港やオーストラリアに足を運ぶと、中央局に関する資料が存在していたことを発見しましたが、その時の驚きや喜びの気持ちはいまだに忘れられません。最近になって、多くの公式の資料集、伝記、公文書、海外の流出資料集などが出版されるようになってきましたが、そうした資料群をどのように解読するか、編集側の意図した読み方に翻弄(ほんろう)されないように、色々と比較や考察をすることにも苦労しました。
また、先ほども申し上げたように、中央局には中央委員会の一部という組織上の位置づけもあり、それに関連する資料は北京にある中央檔案館(公文書館)に保管されています。そのレベルの資料は、関係者の紹介なしでは決して手の届かないものです。今から思えばお恥ずかしい限りですが、修士課程の頃の私は、中国の各地の檔案館に電話し、どのようにすれば中央局の檔案を読めるか、台湾人の身分で制限されることがあるかどうか、向こうのスタッフも困惑するような質問をたくさんしました。結局、実際に檔案館を訪れた際には、自分の身分や研究テーマに関しては何も聞かれず、ほかの方々と同じくパソコンを操作し、キーワードを入力すれば様々な檔案を調べることができました。もちろん、中央局に直接関わる資料は読めなかったのですが、地方党委員会の公文書で間接的に中央局の活動の一部を知ることもできました(編集部:中央檔案館の公文書管理については、楊奎松氏の回想録「中国中央公文書館、その謎めく内部を探訪する」もご覧ください)。

問4 日本でも一時期、道州制の議論が活発になったことがありました。ただ、中央・地方の権限(裁量権)をめぐる対立を乗り越えるのは、至難の業のようです。中央局の場合、政治史の各局面でどのような役割を果たしたと評価できるのでしょうか。
(黄)現代中国の中央・地方の間の政治力学の角逐については、中央(しばしば毛沢東個人)によって主導されてきたとみなされてきました。その結果、多くの政策論争の帰結は、集権化、分権化という単線的な制度変更の結果として説明されてきました。それに対して、中央局という組織の存在は、多様な政治勢力が常に折衝に当たり曖昧な空間を残さなければならなかった、当時の政治的な現実を反映していると思います。政治史の各局面において、異なる政策主張を持つ勢力に不満があったとしても、中央局の運用次第で自らにとって有利な状況を作り出すことが可能になり、各政治勢力の利益分配の折衷策として機能していたと考えます。
例えば大躍進運動(1958年~)の収拾において中央局が果たした役割があります。かつて大躍進運動の破綻(はたん)が判明した段階において、運動の収拾をめぐる様々な政治勢力の角逐がありました。特に、運動中には多くの政治的な権限や利得を得て、活躍していた地方指導者がいましたが、中央は指導者たちを全面的に否定するのではなく、その協力を仰ぐ必要に迫られました。そこで中央は各勢力の均衡策を果たし得る組織として、中央局に目をつけたのです。結果的に中央局が再建されたことで、地方は弱体化せずに、むしろ地域統合のためのより強力な指導力を獲得することに成功しました。それと同時に、その組織の枠組みがあることで、指導者の個人的な行動が牽制されることになりました。このように、大躍進運動の後退をめぐる中央指導部や、中央、地方の間に起こり得る対立は中央局の成立によって当面は解決できたことが分かります。
ほかにも中央局の役割を説明するために、本書では第一次五カ年計画の体制構築、大躍進運動の発動、1960年代の戦争準備計画である三線建設の開始をめぐる政策論争などの事例を取り上げましたが、ここでは各事例の詳細な説明は割愛します。
問5 中央局は文革の混乱期に活動を停止し、現在は組織として存在していません。現在の中国の統治機構から見て中央局の遺産はどの辺りにあり、このような組織が存在していないことによる課題は、どの辺りにあるとお考えでしょうか。
(黄)改革開放以降もかつての中央局のように、複数の省にまたがり、既存の行政地域を打破するための広域統治の枠組み自体は導入されてはいたものの、その制度効果は十分に発揮できていないと言われています。最近の例としては、1997年のアジア金融危機を機に、中央は計画経済期の行政区画に基づいて設置された人民銀行の省級分行(支店)を廃止し、複数の省にまたがる大区分行を全国に九つ(天津、済南、南京、上海、武漢、広州、西安、成都、瀋陽)設立しました。大区分行の運営は地方から独立し、人民銀行の本行(本店)の直接的な指示を受けたとされます。この措置は、省級の地方政権の影響力をできるだけ排除し、人民銀行の独立を強化することによって、地方金融機関の監督強化を成し遂げようとするものでした。しかし結局、大区分行は地方の協力を得られない状況が続き、想定された制度効果を発揮できたとは言えません。
その原因について、広域統治機構の側面から考えてみましょう。人民銀行の大区分行は表面的な制度においては過去の中央局と類似していますが、その設立の趣旨からすれば、過去のように制度上の「中央性」と実質的な「地方性」という両面性を兼ね合わせていた中央局とは根本的に異なっています。もちろん、改革開放以降、中央では地方統治に関して、様々な制度や規範の整備が進められた傾向が見られますが、地方の政治上の権限や自主性は制度化されないままです。さらに、地方に対してかつてのような広域統治機構を通じた政治、行政上の幅広い裁量権が与えられることもなくなりました。
一方で、中央局は地方の行政だけでなく、毛沢東時代の経済、国防戦略を執行する中核的な機構でもありました。つまり、1949年以降の長期間にわたり、中央局のような組織の存在を通じて、中国の地方制度と国家戦略は高度な連動性を保ってきたのです。もちろん、改革開放以降、毛沢東時代のような全国を範囲として想定する戦争準備体制は解消されました。しかし、こうした戦略の基本的な考え方が、ある程度中央指導部の中で残っているとすれば、そのことも中央局が残した遺産だとは言えると思います。特に近年において、中国を取り巻く国際情勢の緊張感が高まる中で、各戦区と地方政府の連携にいかなる変化が起きているかという側面から、もしかすると今後はまた中央局と類似する組織の復活もあり得るのではないかと注目しています。
問6 最後に、この記事をご覧の方に、特に現代中国の政治史に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。
(黄)インタビューの回答を考えながら、やはり改めて現代中国の政治史を勉強することよりも辛くて、同時に楽しいことはないと思いました。辛いことは、資料のなさに途方に暮れる絶望、そして実態が掴めない無力感です。しかしながら、辛ければ辛いほど、その苦痛を乗り越えた時の達成感や喜びもひとしおであると思います。また、資料の発見なども重要ですが、現代中国政治の「特殊論」にならずに、時にはほかの国にも目を向けて中国で起こったことの「普遍性」にも目を配ることが重要だと思います。
最後に、現代中国の政治史に興味を持ち、頑張っている学生のみなさん、一つ一つの資料との出会いを大事にしてください。ある時には、誰かが残したたった一言でさえ、天から降りてくるような大事なヒントになるかもしれません。中国を理解し、自らの中国像を作っていくことは、私にとっても永遠の課題です。みなさんが中国政治に興味を持って勉強をしてくださること、そしてこれからの活躍を心から期待しています。
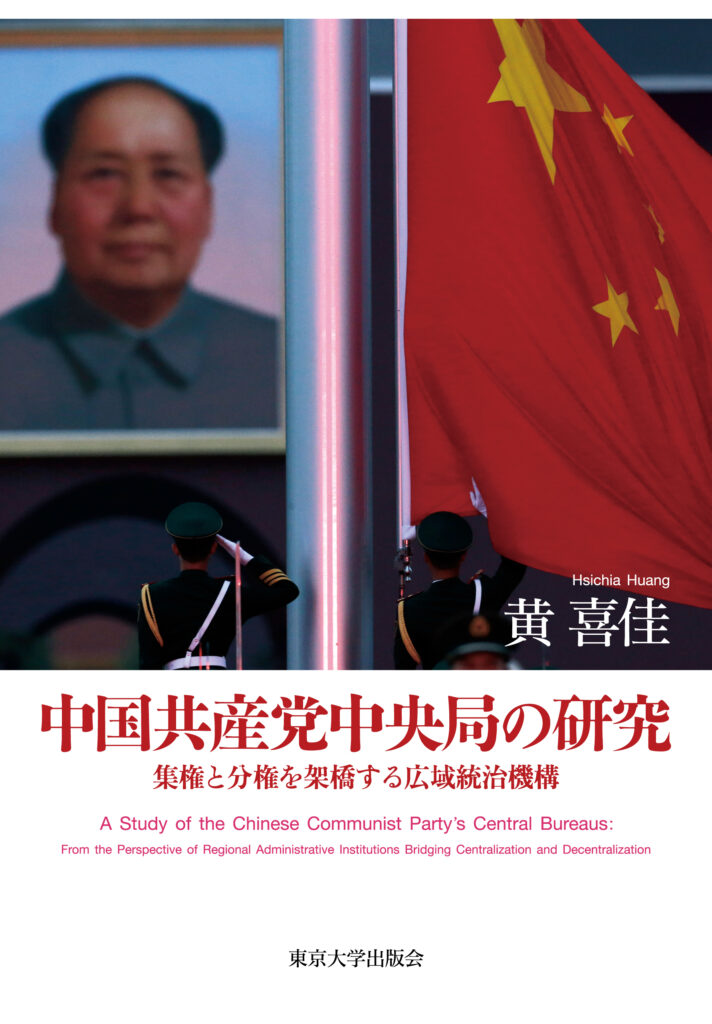
黄さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、現代中国の中央・地方関係に興味を持たれた方は、ぜひ『中国共産党中央局の研究』を手に取ってみてください。






