Commentary
著者に聞く⑥――黄喜佳さん
『中国共産党中央局の研究』(東京大学出版会、2025年3月刊)
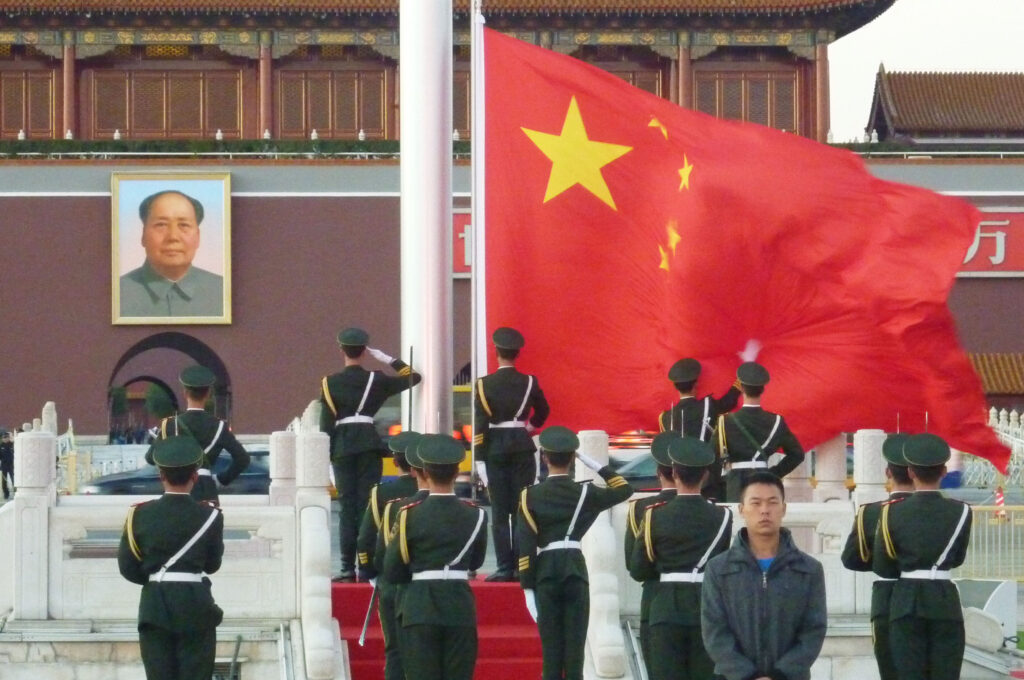
問5 中央局は文革の混乱期に活動を停止し、現在は組織として存在していません。現在の中国の統治機構から見て中央局の遺産はどの辺りにあり、このような組織が存在していないことによる課題は、どの辺りにあるとお考えでしょうか。
(黄)改革開放以降もかつての中央局のように、複数の省にまたがり、既存の行政地域を打破するための広域統治の枠組み自体は導入されてはいたものの、その制度効果は十分に発揮できていないと言われています。最近の例としては、1997年のアジア金融危機を機に、中央は計画経済期の行政区画に基づいて設置された人民銀行の省級分行(支店)を廃止し、複数の省にまたがる大区分行を全国に九つ(天津、済南、南京、上海、武漢、広州、西安、成都、瀋陽)設立しました。大区分行の運営は地方から独立し、人民銀行の本行(本店)の直接的な指示を受けたとされます。この措置は、省級の地方政権の影響力をできるだけ排除し、人民銀行の独立を強化することによって、地方金融機関の監督強化を成し遂げようとするものでした。しかし結局、大区分行は地方の協力を得られない状況が続き、想定された制度効果を発揮できたとは言えません。
その原因について、広域統治機構の側面から考えてみましょう。人民銀行の大区分行は表面的な制度においては過去の中央局と類似していますが、その設立の趣旨からすれば、過去のように制度上の「中央性」と実質的な「地方性」という両面性を兼ね合わせていた中央局とは根本的に異なっています。もちろん、改革開放以降、中央では地方統治に関して、様々な制度や規範の整備が進められた傾向が見られますが、地方の政治上の権限や自主性は制度化されないままです。さらに、地方に対してかつてのような広域統治機構を通じた政治、行政上の幅広い裁量権が与えられることもなくなりました。
一方で、中央局は地方の行政だけでなく、毛沢東時代の経済、国防戦略を執行する中核的な機構でもありました。つまり、1949年以降の長期間にわたり、中央局のような組織の存在を通じて、中国の地方制度と国家戦略は高度な連動性を保ってきたのです。もちろん、改革開放以降、毛沢東時代のような全国を範囲として想定する戦争準備体制は解消されました。しかし、こうした戦略の基本的な考え方が、ある程度中央指導部の中で残っているとすれば、そのことも中央局が残した遺産だとは言えると思います。特に近年において、中国を取り巻く国際情勢の緊張感が高まる中で、各戦区と地方政府の連携にいかなる変化が起きているかという側面から、もしかすると今後はまた中央局と類似する組織の復活もあり得るのではないかと注目しています。
問6 最後に、この記事をご覧の方に、特に現代中国の政治史に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。
(黄)インタビューの回答を考えながら、やはり改めて現代中国の政治史を勉強することよりも辛くて、同時に楽しいことはないと思いました。辛いことは、資料のなさに途方に暮れる絶望、そして実態が掴めない無力感です。しかしながら、辛ければ辛いほど、その苦痛を乗り越えた時の達成感や喜びもひとしおであると思います。また、資料の発見なども重要ですが、現代中国政治の「特殊論」にならずに、時にはほかの国にも目を向けて中国で起こったことの「普遍性」にも目を配ることが重要だと思います。
最後に、現代中国の政治史に興味を持ち、頑張っている学生のみなさん、一つ一つの資料との出会いを大事にしてください。ある時には、誰かが残したたった一言でさえ、天から降りてくるような大事なヒントになるかもしれません。中国を理解し、自らの中国像を作っていくことは、私にとっても永遠の課題です。みなさんが中国政治に興味を持って勉強をしてくださること、そしてこれからの活躍を心から期待しています。
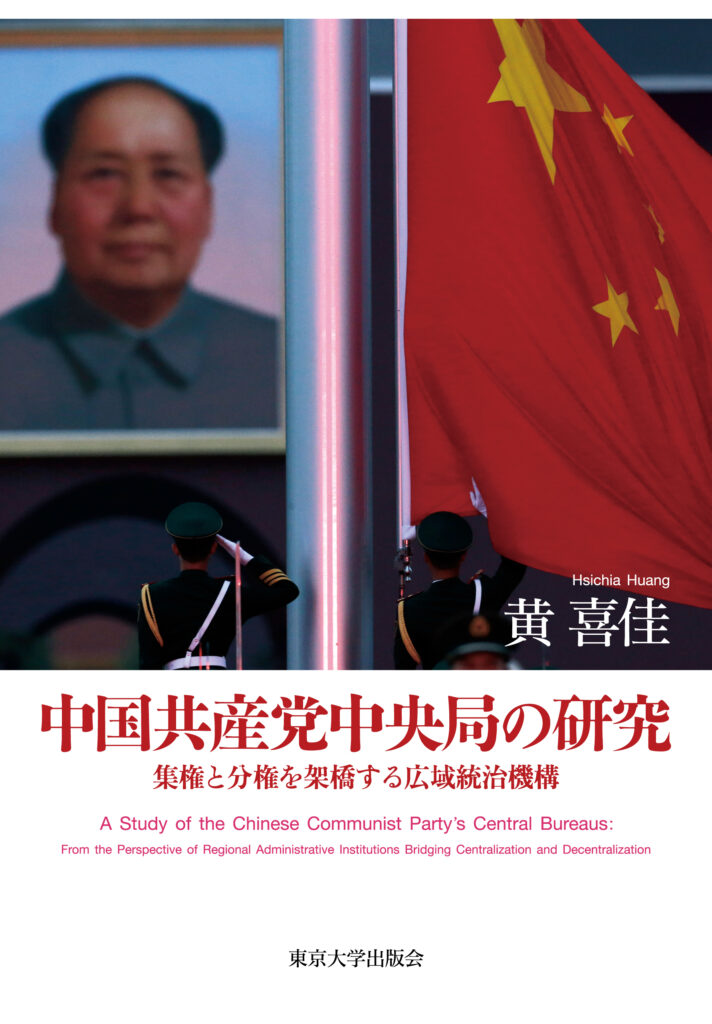
黄さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、現代中国の中央・地方関係に興味を持たれた方は、ぜひ『中国共産党中央局の研究』を手に取ってみてください。






