Commentary
著者に聞く⑥――黄喜佳さん
『中国共産党中央局の研究』(東京大学出版会、2025年3月刊)
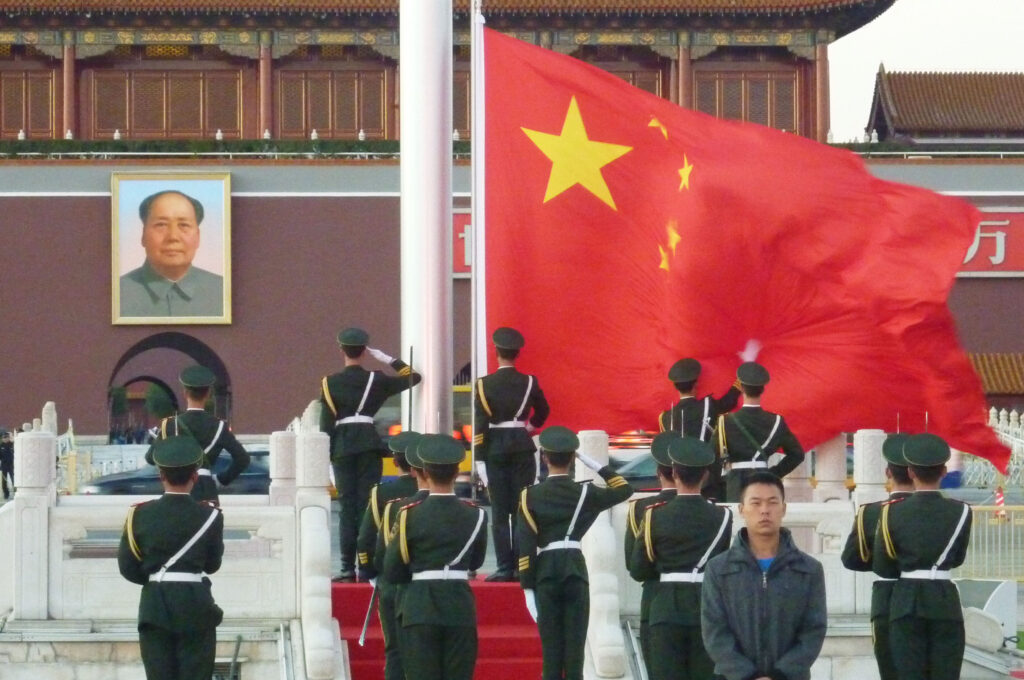
問3 執筆に当たって、特に苦労したことは何でしょうか。また、それをどのように克服されたのでしょうか。
(黄)特に苦労したことは、何よりも中央局の活動を裏づける資料の収集でした。そもそも最初は、どのような資料が存在しているのかを把握することも困難でした。何とか手がかりを得て、執筆開始後に香港やオーストラリアに足を運ぶと、中央局に関する資料が存在していたことを発見しましたが、その時の驚きや喜びの気持ちはいまだに忘れられません。最近になって、多くの公式の資料集、伝記、公文書、海外の流出資料集などが出版されるようになってきましたが、そうした資料群をどのように解読するか、編集側の意図した読み方に翻弄(ほんろう)されないように、色々と比較や考察をすることにも苦労しました。
また、先ほども申し上げたように、中央局には中央委員会の一部という組織上の位置づけもあり、それに関連する資料は北京にある中央檔案館(公文書館)に保管されています。そのレベルの資料は、関係者の紹介なしでは決して手の届かないものです。今から思えばお恥ずかしい限りですが、修士課程の頃の私は、中国の各地の檔案館に電話し、どのようにすれば中央局の檔案を読めるか、台湾人の身分で制限されることがあるかどうか、向こうのスタッフも困惑するような質問をたくさんしました。結局、実際に檔案館を訪れた際には、自分の身分や研究テーマに関しては何も聞かれず、ほかの方々と同じくパソコンを操作し、キーワードを入力すれば様々な檔案を調べることができました。もちろん、中央局に直接関わる資料は読めなかったのですが、地方党委員会の公文書で間接的に中央局の活動の一部を知ることもできました(編集部:中央檔案館の公文書管理については、楊奎松氏の回想録「中国中央公文書館、その謎めく内部を探訪する」もご覧ください)。

問4 日本でも一時期、道州制の議論が活発になったことがありました。ただ、中央・地方の権限(裁量権)をめぐる対立を乗り越えるのは、至難の業のようです。中央局の場合、政治史の各局面でどのような役割を果たしたと評価できるのでしょうか。
(黄)現代中国の中央・地方の間の政治力学の角逐については、中央(しばしば毛沢東個人)によって主導されてきたとみなされてきました。その結果、多くの政策論争の帰結は、集権化、分権化という単線的な制度変更の結果として説明されてきました。それに対して、中央局という組織の存在は、多様な政治勢力が常に折衝に当たり曖昧な空間を残さなければならなかった、当時の政治的な現実を反映していると思います。政治史の各局面において、異なる政策主張を持つ勢力に不満があったとしても、中央局の運用次第で自らにとって有利な状況を作り出すことが可能になり、各政治勢力の利益分配の折衷策として機能していたと考えます。
例えば大躍進運動(1958年~)の収拾において中央局が果たした役割があります。かつて大躍進運動の破綻(はたん)が判明した段階において、運動の収拾をめぐる様々な政治勢力の角逐がありました。特に、運動中には多くの政治的な権限や利得を得て、活躍していた地方指導者がいましたが、中央は指導者たちを全面的に否定するのではなく、その協力を仰ぐ必要に迫られました。そこで中央は各勢力の均衡策を果たし得る組織として、中央局に目をつけたのです。結果的に中央局が再建されたことで、地方は弱体化せずに、むしろ地域統合のためのより強力な指導力を獲得することに成功しました。それと同時に、その組織の枠組みがあることで、指導者の個人的な行動が牽制されることになりました。このように、大躍進運動の後退をめぐる中央指導部や、中央、地方の間に起こり得る対立は中央局の成立によって当面は解決できたことが分かります。
ほかにも中央局の役割を説明するために、本書では第一次五カ年計画の体制構築、大躍進運動の発動、1960年代の戦争準備計画である三線建設の開始をめぐる政策論争などの事例を取り上げましたが、ここでは各事例の詳細な説明は割愛します。






