Commentary
著者に聞く⑤――鈴木隆さん
『習近平研究』(東京大学出版会、2025年1月刊)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の研究者の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は現代中国政治の専門家で、『習近平研究』の著者である鈴木隆さんにお話を伺いました。
問1 そもそもなぜ習近平という人物の研究を始められたのでしょうか。また本書の着想を得たきっかけを教えていただけますか。
(鈴木)理由は大きく言って3つあります。
第一に、拙著『習近平研究――支配体制と指導者の実像』(以下、『習近平研究』)のあとがきにも書いたのですが、学生時代から政治家の評伝を読むのが好きだったことです。具体的には、日本の吉田茂、ソヴィエト連邦や中華人民共和国では、レーニン、スターリン、トロツキー、毛沢東、鄧小平などの伝記です。さまざまなキャリアの人が、自分の来歴を語る『日本経済新聞』の名物企画「私の履歴書」も楽しみです。ただし、先に挙げた著作の多くが欧米の研究者の手になる業績であり、日本人の作品が少ないことに残念な思いを抱いていました。ごく小さな部分とはいえ、そうしたナショナリスティックな心情が、『習近平研究』の執筆動機に含まれていることを、わたしは否定しません。
第二に、2012年に最初の単著『中国共産党の支配と権力――党と新興の社会経済エリート』(慶應義塾大学出版会)を刊行して以降、研究活動に取り組む中でわたしは、中国政治における3つの主要な行為主体、すなわち、①支配政党、②最高指導者、③国民集団に着目して、自身の中国政治研究を発展させていきたいと考えるようになりました。前著と『習近平研究』によって、①と②は一定の成果を残すことができました。今後は、③のテーマを追究して、自分なりの「中国政治研究の三部作」を完成させたいと願っています。
第三に、なぜ習近平だったのかという点について。2016年にわたしは菱田雅晴氏との共著で、『超大国・中国のゆくえ3 共産党とガバナンス』(東京大学出版会)という本を発表しました。その準備作業の過程で、初歩的なレベルですが、習近平の著作群を読んでみたところ、江沢民や胡錦濤に比べて政治的個性の強い人物という印象を持ちました。中国の国家社会主義体制のリーダーとして興味深い人物であり、直感的に、習近平という「キャラの立った」政治家であれば面白い本が書ける気がしました。
問2 習近平の経歴について基本的なことを伺います。一時はライバルと目された薄熙来や李克強に比べて、どのような点が特徴的なのでしょうか。
(鈴木)李克強と比べた場合、習近平は政治的血筋の良さが指摘できます。「紅二代」の代表的人物であり、中華人民共和国建国に功績のあった党や軍のエリート家庭出身です。血統に由来する自負と責任感は、習近平の政治認識を理解するうえできわめて重要です。今日、最高指導者である習近平にとって、みずからの政治的責務をまっとうすべき相手の中には、現世に生きる中国国民はもちろん、しかし領土や主権、歴史認識、そして国際政治での覇権追求といった特定の政治課題においては、生者と同等、ときにはそれ以上に、死者――すでに鬼籍に入っている革命の先達も含まれるのです。
薄熙来については、習近平と薄熙来はともに支配体制の門閥出身の点で共通していますが、政治行動の面で違いがあります。しばしば言われるとおり薄熙来は、出世のため民衆の歓心を買うことに注力したポピュリストでした。自身の政治的業績を社会に向けて宣伝することにも熱心でした。自己PRへの強い意欲は、文化大革命終了後、中国社会科学院でマスメディア学を専攻した経験に由来しているのかもしれません。
一方、習近平は、最高指導者になる前の、四半世紀の長きに及ぶ地方指導者時代には、表面的には地味で目立たない存在であろうとし、手柄をひけらかさない奥ゆかしい人物との評判でした。しかし拙著で指摘したとおり、実際には習近平も各任地での統治の実績を、おおやけには目立ちにくい各種の方法を通じて、他の統治エリートに向かって集中的かつ積極的にアピールしていました。この点、ポピュリスト的傾向が強い薄熙来に対し、習近平は徹底したエリート主義者と言えるでしょう。
問3 本書には同時代研究の側面と、政治史の側面の両面があるかと思います。執筆にあたって、特に苦労したことは何でしょうか。また、それをどのように克服されたのでしょうか。
(鈴木)まず、研究者としてのわたし自身の政治意識において、同時代研究と歴史研究は、分析対象として扱う時期が異なるだけで、どちらも政治学の概念と方法を用いて分析するうえで本質的な違いはありません。同時代の政治家であれ、書物でしか知らない政治家であれ、自分が直接対面して深く掘り下げた話し合いができない点では変わりません。外国人の地域研究者であるわたしにとっては、習近平も毛沢東も、自分の内面の存在感はさほど大きな違いはないのです。
次に、事象の解釈と評価については、中国政治史上での「タテ」の特殊性と、世界史あるいは同時代の国際政治における「ヨコ」の一般性という2つの観点から考えるように努めています。一般性や普遍性に関しては、新たな着眼点や理解のヒントを得るため、自分の専門分野以外の新書などを多く読むように心がけています。
話のついでに、資料についても一言ふれておきましょう。歴史研究に比べると、同時代研究は、確かに資料環境に恵まれています。言い換えると歴史研究では、「誰も見たことがない、使用したことがない」という資料発掘の意義が高く評価されがちです。実際、『習近平研究』の場合も、多くの「内部資料」を活用している点がセールスポイントの1つです。
しかし、本音を言えばわたしは、研究資金やコネクションの面で入手や閲覧の苦労をすることなく、みなが公平に使用できる一般的な公開資料を使って、新たな事実の発見や、先行業績とは異なる解釈・視座の提示を行うほうが――いくらか語弊のある言い方ですが――「王道にして上の上」の研究だと思っています。お金をかけてレアな「素材」を使った料理が美味しいのは当たり前。近所のスーパーで安く簡単に手に入る材料を、「調理法」を工夫して人に喜びを与える料理を作る――それがわたしの理想とする研究のスタイルです。いわんや、重要な問題が眼前にあるにもかかわらず、資料が新たに公開されなければ論文が書けないというのは、政治学徒としては、社会的責任の放棄と言われても仕方ありません。
誤解のないように強調しておきますが、お金と時間、労力をかけて貴重な一次資料を追求する努力を否定するつもりは毛頭ありません。わたし自身、常にそのように努めています。ただしその場合も、自分が所有する希少価値の高い資料は、後学の人びとのために、最終的には社会に広く公開すべきです。わたしも、『習近平研究』の執筆にあたって入手した内部資料は、いずれ大学図書館などに寄贈して学界の共有財産にするつもりです。
問4 中華圏でも英語圏でもない、隣国である日本で習近平を研究する強みは何でしょうか。反対に、留意点もあれば伺いたいです。
(鈴木)習近平の個人研究を具体例に挙げて説明しましょう。
拙著『習近平研究』と同じく、習近平という政治指導者を真正面から論じた英語圏の代表的研究として、オーストラリアの元首相ケヴィン・ラッドの研究が挙げられます(Kevin Rudd,On Xi Jinping: How Xi’s Marxist Nationalism is Shaping China and the World, Oxford University Press, 2024. 以下、『Xi Jinping』)。中国語圏の成果としては、『不合時宜的人民領袖――習近平研究』(台湾独立作家出版、2023年。以下、『人民領袖』)という本があります。著者の鄧聿文(とう いつぶん)はかつて、中国共産党の中央機関が発行する日刊紙の記者でした。
鈴木・ラッド・鄧の筆になる上記3冊を比較すると、日本・欧米諸国・中国文化圏における中国政治研究の「色合い」――政治家という特異な人間集団をめぐるさまざまな謎を解明するための基本的な視座、分析方法、叙述のスタイルの違いが明瞭にみてとれます。
鄧『人民領袖』が、「文史哲」と総称される文学・史学・哲学を重視する中国文化の伝統的な人間理解の仕方を引き継いで、政治家の心理や性格、個人と集団をめぐる愛憎、それらに由来する権力闘争などに注目するのに対し、ラッド『Xi Jinping』において、政治の営為の理解は、徹頭徹尾、欧米の社会科学的な概念と方法によって貫かれています。その結果、最高指導者になる前の習近平の個人史や中国の政治文化的要素は、分析の射程から基本的に捨象されます。中国近現代思想史の碩学(せきがく)であった故・野村浩一氏は、かつて欧米の中国研究の印象を「サバサバしている」と述べたことがありますが、ラッドの著述はまさしくその表現にふさわしいでしょう。
一方、鈴木『習近平研究』は、東西文化の融合を特色とする日本文化の影響の下、そうした「ドロドロ」と「サバサバ」の折衷的な作品となっています。欧米由来の社会科学的分析を基礎として、前近代の王朝支配の政治的伝統や、指導者の政治的死生観などの「東洋」的な政治文化にも配慮しています。こうした柔らかな政治感覚が日本の研究者の強みでもあり、欧米流のいわゆる「科学志向」から見れば弱みなのかもしれません。ただし、この点に関するわたしの立場は、「方法/調理法」はあくまで「対象/素材」が決めるもので、その逆ではないというものです。
また、以上とは異なる角度から、『習近平研究』と日本文化とのかかわりにも言及しておきましょう。わたしの理解では、本を書くことと、論文を書くことはいくらか意味が異なります。論文は、個別の問いに対しその答えを導き出せばそれでよいのですが、書籍の場合はそれに加えて、「内的に統合された1つの物語の世界」を創り出さなければなりません。その際にわたしが参考にしたのは、『荒木飛呂彦の漫画術』(集英社、2015年)でした。周知のように荒木氏は、代表作『ジョジョの奇妙な冒険』の作者であり現代日本の巨匠漫画家の一人です。同書は、漫画を「総合芸術」と語る作者が自身の作品を題材として漫画作成の技法を解説した本です。この点でも、鈴木『習近平研究』は日本文化の産物と言えます。
実際、「読ませるものを書く」という方法論において、荒木『漫画術』は多くの示唆に富んでいます。荒木氏によれば、漫画作品の「基本四大構造」は「キャラクター」、「ストーリー」、「世界観」、「テーマ」ですが、わたしが思うにこれらは、政治家の評伝を物す際にもほぼそのまま適用が可能です。『習近平研究』で言えば、「キャラクター」は習近平、「ストーリー」は政治家・習近平の成長物語、「世界観」は現代中国の政治史的背景です。書籍全体を貫く「テーマ」は、マキャベリの『君主論』を現代中国に置き換えて政治家論、リーダーシップ論を語るというのが拙著の内幕です。
問5 率直に申し上げて、今後の中国で習近平の個人崇拝がさらに進むと、晩年の毛沢東や現在のプーチンのような問題、例えば権力の暴走や後継者の不在といった問題が解決できなくなるのではと考えてしまうのですが、これらについていかがお考えでしょうか。
(鈴木)習近平が「第二の毛沢東」や「第二のプーチン」、あるいは「第二のブレジネフ」になる危険性は間違いなくあります。それらのリスクをはじめ、権力継承の問題についても、『習近平研究』(特に第八章と終章)で詳しく解説していますので、ぜひ、そちらを参照してください。
問6 最後に、この記事をご覧の方に、特に現代中国の政治外交史に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。
(鈴木)まず、「これから中国政治研究をしてみたい、中国政治研究ってどんなものだろう」と考えている学部生や社会人の皆さんには、ともかくも「研究は楽しい」という点を強調したいと思います。むろん、実際の研究活動では苦しいことも多々あります。しかしそれ以上に楽しく面白い発見があります。自分の体験で言えば、それまでボンヤリとした「曖昧な認識のラフスケッチ」でしか見えていなかった世界が、ある日、はっきりとピントの合った「明瞭な理解のビジョン」を得る感覚があります。こうした知的快感の獲得は、人生のさまざまな場面の中でもそう多くはないでしょう。手前味噌で恐縮ですが、とりあえず騙されたと思って、拙著を読んでみてください。
次に、中国政治研究にすでに取り組んでいる大学院生の皆さんには、もう少し具体的なアドバイスを3つだけ記しておきます。
第一に、博士論文のテーマ選定にあたっては、自分の感じる面白さにこだわりを持ち、その理由を深掘りしてみること。そうした内発的探究心に加えて、実際の研究活動に活かすことのできる自分の強み(性格、言語能力、研究蓄積など)を折にふれて見つめ直してみること。さらに、社会問題への観察眼と言語的明晰さの2つのセンスを磨き続けること。
第二に、「資料をひたすら読んでいる」、「勉強熱心で他人の研究に詳しい」だけで、本人のアウトプットがなければ学界への貢献にはなりません。論文はともかく書き慣れることが大切であり、まずは原著論文2本と先行研究のレビュー論文1本の発表を目指しましょう。目標はホームランですが、クリーンヒットでもバントヒットでも、ともかくバットを振る勇気、塁に出たという事実がなければ始まりません。その後、3~5本の論文発表とそれらを総合した博士論文で、あなたの本領を発揮すればよいのです。
第三に、研究者としてのプロ意識に基づき、自身の社会活動全般の優先順位を決め、健康で自己規律のある生活を維持すること。性格的に自己PRが好きではない人、他者との対面コミュニケーションが得意ではない人も、大丈夫、安心してください。大学院生にとって最も重要な社会貢献の「名刺」は、あなたが発表した学術論文や研究書であって、SNS上での気の利いた発言ではありません。優れた研究成果は誰かが必ず発見してくれますし、本質的に言って、専門家の業績評価は専門家でなければできません。
最後に、いつなんどき研究上のアイデアや良い文章表現が頭に浮かぶかわかりません。手帳を持ち歩いてメモ魔になる癖をつけておくとよいでしょう。わたしの場合、気分転換と体力維持のため習慣にしている散歩の途中やその終了直後に、それらを思いつくことが多いので、散歩には手帳とペンを常に携帯しています。研究活動とは体力そのものです。心身の健康維持に努め、ともに世界の中国理解に貢献していきましょう!
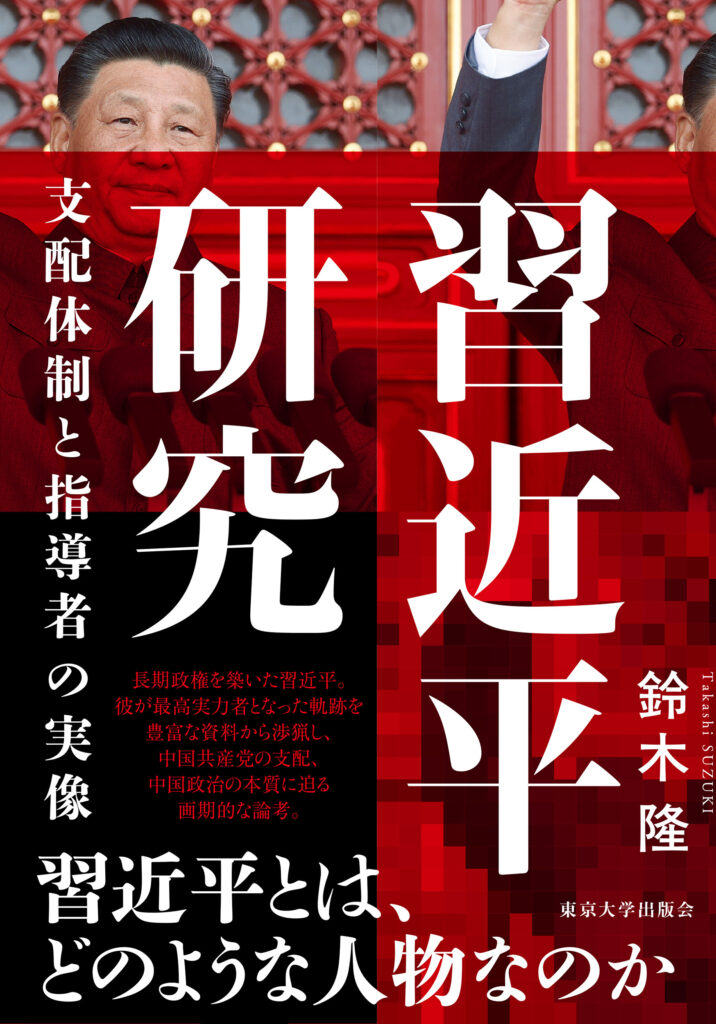
鈴木さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、本書に興味を持たれた方は、ぜひ『習近平研究』を手に取ってみてください。






