Commentary
著者に聞く③――片山ゆきさん
『十四億人の安寧――デジタル国家中国の社会保障戦略』(慶應義塾大学出版会、2024年9月刊)

中国学.comでは、現代中国および中国語圏の研究者の中から、近年注目すべき著作を出版された著者にインタビューを行います。今回は中国の社会保障制度・民間保険の専門家で、『十四億人の安寧』の著者である片山ゆきさんにお話を伺いました。
問1 そもそもなぜ中国の社会保障制度に興味を持たれたのでしょうか。また本書の主な課題を教えてください。
(片山)中国の社会保障制度に興味を持ったきっかけは、日本の対中ODA(政府開発援助)で、中国の農村部の年金制度の再構築をするプロジェクトに参加したからです。2000年代初頭の中国は経済の高度成長の下、社会保障格差の問題が大きくクローズアップされていました。特に都市と農村の社会保障格差は大きく、その是正が求められていたのです。そこで未整備であった農村の年金制度を改革すべく、日本による制度構築に関する技術援助がされることになりました。当時は、年金のみならず医療保険制度、生活保障制度など社会保障は多くの課題を抱えていました。しかし、こういった中国の社会保障制度は、現在においても日本では幅広く知られていません。そこで本書では中国の社会保障制度とはどのようなものなのか、また、その独自性ゆえどのような課題を内包しているのか、どう持続可能なものにしようとしているのかという課題を設定しました(編集部:関連記事として丸川知雄「中国は介護保険制度を導入すべきか」、劉生龍「高齢化に直面する中国」もご参照ください)。
問2 執筆に当たって、特に苦労したことは何でしょうか。また、それをどのように克服されたのでしょうか。
(片山)特に苦労した点は、日本や欧州とは異なる中国の社会保障制度のあり方やメカニズムを明らかにする点です。中国の社会保障制度は、公的制度からの給付を小さくとどめ、その代わりに民間保険やNPOの活動、家族・共同体などさまざまなリスク保障を幾重にも重ね(多層化)、ミックスする「福祉ミックス体制」を採用しています。特に習近平政権以降、医療保障分野で民間保険会社の活用が進んでおり、民間保険会社に社会保険を補完する商品を開発させ、新たに出現した生活上のリスクを間接的に保障させる手法をとっています。つまり、政府は直接コントロールする範囲を限定すると同時に、民間保険会社を通じて間接的にコントロールする範囲(給付・サービス)の拡大を果たしています。このような社会保障制度のあり方、つまり、政府(監督管理側)と市場の関係性はその他の分野でも見られ、中国を理解する上で重要な鍵となると言えます。
問3 副題の「デジタル国家」には、日本に暮らす私たちにとっては便利さと不安が交錯するイメージがあります。テクノロジーを活用した社会保障制度の整備は、中国の一般の人々に肯定的に受け入れられているのでしょうか。
(片山)中国で社会保障、特に医療保障分野においてデジタル化が急速に浸透したのは新型コロナウイルス禍が広がった2020年あたりからです。コロナの蔓延(まんえん)でオンライン診療や健康に関するサービスが無料で提供され、多くの人が活用したことから一気に普及した背景があります。政府もオンライン診療を前倒しで保険適用とするなど速やかな対応がとられました。こういった背景から、テクノロジーを活用した社会保障制度の整備は、どちらかと言えば肯定的に受け入れられていると思われます。ただし、急速にデジタル化が進んだため、高齢者のデジタル・デバイド(情報格差)の問題が引き起こされたのも事実です。このような状況に対処するために、現在では「人」を介したサポートも併せて重視されています。
問4 特に参考にした先行研究や研究方法は何でしょうか。
(片山)中国出身で、現在日本で教鞭(きょうべん)をとられている李蓮花先生の研究に大きな影響を受けました。中国を含む東アジアの社会保障制度をエスピン・アンデルセンの福祉レジーム論においてどのように分類するのかは長年議論がされています。これに対して、李蓮花先生は既存の福祉国家論と東アジアの社会保障制度の現実の間に大きなギャップがあるとし、さらに、福祉国家を国家、市場、家族などに基づいて分類した福祉レジーム論で東アジアを位置づけようとした場合でも、混乱が生じている点を指摘しています。また、社会保障制度を支える民間保険会社など企業(民)からの分析は、ある意味で顧みられてこなかった「死角地帯」とし、この視点が本書の重要な基礎となっています。研究・分析については、現在進行形で動く民間市場のリスク保障商品を対象とし、消費者という「民」の視点を反映する上でもアンケート調査を中心とした分析となりました。
問5 分析手法について、多様な統計データに加え、アンケートを行った章もあります。これらのデータを扱う上で、注意すべき点は何でしょうか。
(片山)アンケートはITプラットフォーマーがオンライン上で提供した医療保障スキームについて、中国国内で実施しました。調査の主な内容は、この医療保障スキームが中国において急速に普及した理由、加入者の特性、加入理由、加入効果、社会保険や民間保険への影響です。注意を払った点としては、調査結果の偏りを可能な限り小さくすることです。調査対象者の性別、年代、地域の割付は中国の国勢調査に基づいて調整し、可能な限り多くの回答(有効回答件数1400)を確保することに努めました。また、中国国内の実査では調査タイトルによる回答への影響を回避するため、生活調査の一環として実施しました。なお、アンケートは当初、2020年2月に予定をしていたのですが、新型コロナの拡大により、実査が半年ほど延期となりました。よって、再開する際は感染状況が落ち着き、アンケート調査結果への影響がある程度小さくなった時期に実施するなどの配慮も必要でした。
問6 デジタル化の進展による社会保障制度の整備は、日本にとっても重要な課題です。本書の事例の中で、日本とも課題を共有できる点や適用可能な戦略があれば教えてください。
(片山)本書では中国の内容を中心としており、あえて日本への示唆やインプリケーションを記載しておりません。それは、日本と中国では社会保障制度のあり方そのものやデジタル化の過程、その手法が大きく異なっているからです。しかし、人々が使用する社会保険関連のサービスに目を向けてみるとヒントがあるかもしれませんね。例えば、中国では地方政府が運営している公的医療保険についてアプリを開発しています。ユーザーはアプリ上で健康管理、病気になった際は市内の病院や医師の情報の検索、診療・入院の予約、医薬品の配送、リハビリの管理、医療費や薬代の決済など、健康な状態から病気にかかって治るまでの一連の健康サービスを手配することができます。また、こういった情報は匿名化されて、地方政府の医療政策にも反映されるなど政策と医療・健康情報の活用に好循環が見られます。これはあくまで一例ですが、地域の人々の医療・健康情報が比較的速やかに政策に反映されるのは、日本の地域医療の今後を考えた場合、1つのヒントになるかもしれません。
問7 本書刊行後に取り組んでいるプロジェクトやテーマなどがあれば、教えていただけますか?
(片山)中国でも高齢化、長寿化が進み、社会保障制度の中でも高齢者の老後保障問題が大きな問題となっています。老後保障の大きな柱である公的年金制度は2035年に積立金が枯渇すると推計されており、年金財政は厳しくなりつつあります。個人年金などの民間保険は普及し始めた段階にあります。中国では日本のiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)に当たる個人養老金制度も開始されたばかりです。その一方で、老後の収入源の1つとされる高齢者の就労は進んでおりません。よって、現在取り組んでいるテーマとしては高齢者の就労に関する問題です。施策がどのように進むのか、高齢者や社会の意識がどのように変化していくのかなどに注目しています。
問8 最後に、この記事をご覧の方に、特に中国に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。
(片山)昨今は国の安全保障、社会の安定といったワードが目立ちますが、その分析としては外交や内政、国の統治において大量に発出される政策、制度面に目が行きがちです。一方、それを支える民間企業や市場といった現在進行形で動く現場からの視点から捉えると、また、別の側面や見方が浮かび上がってきます。中国に興味を持ち、研究するのであれば複眼的な視点からの分析がより大切になるかもしれません。中国研究は今後さらに重要度を増すと考えられます。より積極的な研究への参加を応援しています。
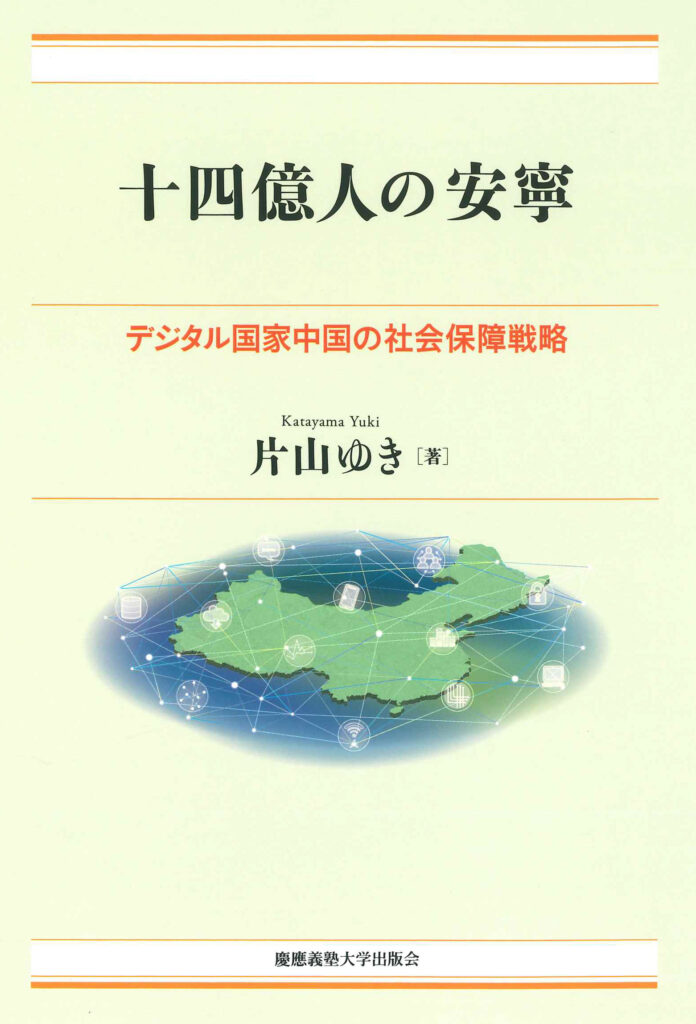
片山さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、中国の社会保障制度のあり方に興味を持たれた方は、ぜひ『十四億人の安寧』を手に取ってみてください。






