Commentary
著者に聞く③――片山ゆきさん
『十四億人の安寧――デジタル国家中国の社会保障戦略』(慶應義塾大学出版会、2024年9月刊)

問6 デジタル化の進展による社会保障制度の整備は、日本にとっても重要な課題です。本書の事例の中で、日本とも課題を共有できる点や適用可能な戦略があれば教えてください。
(片山)本書では中国の内容を中心としており、あえて日本への示唆やインプリケーションを記載しておりません。それは、日本と中国では社会保障制度のあり方そのものやデジタル化の過程、その手法が大きく異なっているからです。しかし、人々が使用する社会保険関連のサービスに目を向けてみるとヒントがあるかもしれませんね。例えば、中国では地方政府が運営している公的医療保険についてアプリを開発しています。ユーザーはアプリ上で健康管理、病気になった際は市内の病院や医師の情報の検索、診療・入院の予約、医薬品の配送、リハビリの管理、医療費や薬代の決済など、健康な状態から病気にかかって治るまでの一連の健康サービスを手配することができます。また、こういった情報は匿名化されて、地方政府の医療政策にも反映されるなど政策と医療・健康情報の活用に好循環が見られます。これはあくまで一例ですが、地域の人々の医療・健康情報が比較的速やかに政策に反映されるのは、日本の地域医療の今後を考えた場合、1つのヒントになるかもしれません。
問7 本書刊行後に取り組んでいるプロジェクトやテーマなどがあれば、教えていただけますか?
(片山)中国でも高齢化、長寿化が進み、社会保障制度の中でも高齢者の老後保障問題が大きな問題となっています。老後保障の大きな柱である公的年金制度は2035年に積立金が枯渇すると推計されており、年金財政は厳しくなりつつあります。個人年金などの民間保険は普及し始めた段階にあります。中国では日本のiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)に当たる個人養老金制度も開始されたばかりです。その一方で、老後の収入源の1つとされる高齢者の就労は進んでおりません。よって、現在取り組んでいるテーマとしては高齢者の就労に関する問題です。施策がどのように進むのか、高齢者や社会の意識がどのように変化していくのかなどに注目しています。
問8 最後に、この記事をご覧の方に、特に中国に興味を持っている学生さん(大学生、大学院生)にメッセージをお願いします。
(片山)昨今は国の安全保障、社会の安定といったワードが目立ちますが、その分析としては外交や内政、国の統治において大量に発出される政策、制度面に目が行きがちです。一方、それを支える民間企業や市場といった現在進行形で動く現場からの視点から捉えると、また、別の側面や見方が浮かび上がってきます。中国に興味を持ち、研究するのであれば複眼的な視点からの分析がより大切になるかもしれません。中国研究は今後さらに重要度を増すと考えられます。より積極的な研究への参加を応援しています。
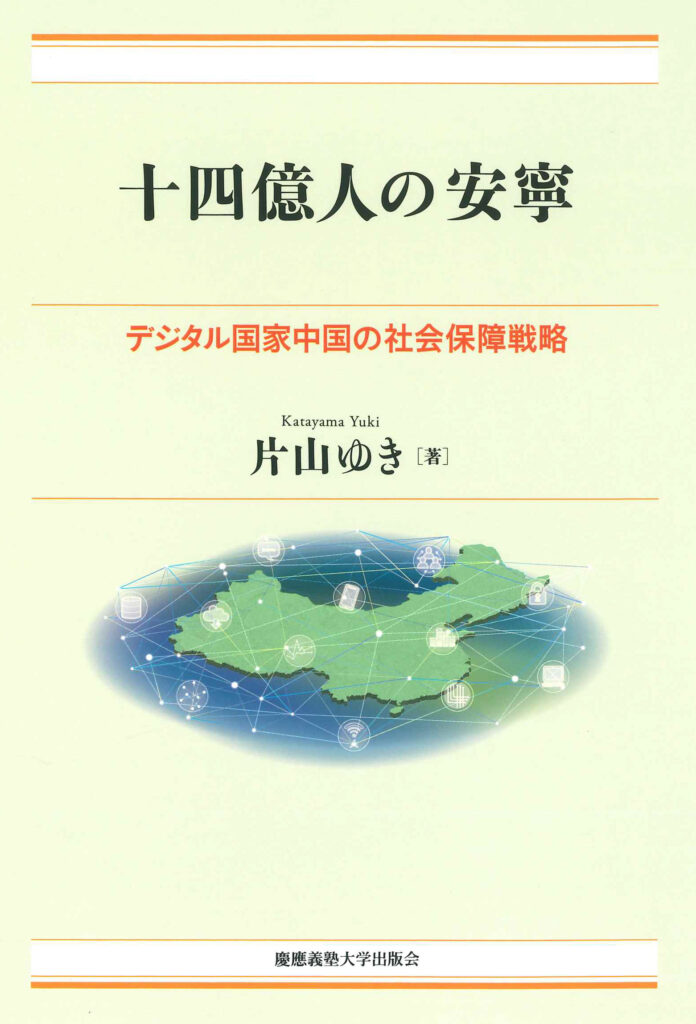
片山さん、ありがとうございました。この記事をご覧になって、中国の社会保障制度のあり方に興味を持たれた方は、ぜひ『十四億人の安寧』を手に取ってみてください。






