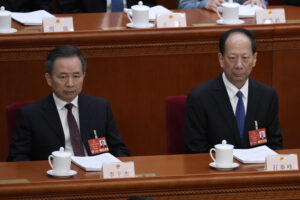Commentary
習近平及びその時代をどう理解するか
2025年以降の政治的「地殻変動」に備えるために

2025年以降、世界も日本も本論の終わりで触れるように、大きな構造変化に置かれていくことは間違いない。こうした中でほぼ同時期に、中国情勢はどのように予測できるか。確固たる見通しは持てないが、今後10年程度の成長力は大きく低下するだろう。理由は、➀住宅需要の減退、不動産業の低迷など総需要の減少、②過剰投資と投資効率の低下、③過剰債務問題、④「国進民退」(国有企業のシェア拡大と民営企業のシェア縮小)問題、⑤人口減少と少子高齢化の急速な進展といった構造的な要因のためである。
ではこれらの問題を抱える中国の最高指導者であり続けている習近平をどのように理解するか。まず権力の掌握の特徴である。習近平は、中国のみならず世界が注目する人物の一人である。しかし彼の経歴は地方での活動が長く、父親が元国務院副総理(副首相)の習仲勲であったにもかかわらず、世間的に注目されるようになったのは、2000年の福建省長の就任から2002年11月浙江省の党委員会書記に就任した頃であり、50歳に近い年齢で比較的遅かった。しかし、その後の出世は早く、わずか10年の歳月で、共産党のトップである総書記のポストに就(つ)くに至った。しかもトップの座に就くや自らの権力基盤を固めることに全力を挙げ、2017年の第19回中国共産党大会の特徴として、習近平への権力の集中、権威の強化などが進み、まさに習近平指導体制の確立が見られた。
「政治的ビヘイビア」から見た習近平
なぜ比較的短期間でこのような強大な権力体制を築くことができたのか。〈習近平個人の政治的ビヘイビア(ふるまい)〉に絞って考えてみると、以下の4つが特徴的である。
「豹変する」指導者
第1は、「君子は豹変(ひょうへん)する」(『易経』)という言葉がピッタリの指導者ではないかと考える。習は中央に登場した時、軍とか政治グループに強力な後ろ盾を持っていなかった。そこで、ポスト胡錦濤の最高指導者になるにあたって、最も依拠したグループは江沢民派であった。当時の香港情報で習近平を中央指導部に抜擢(ばってき)した功労者は、江沢民の側近中の側近、曾慶紅であるとの報道が複数筋から伝えられた。同時に中国社会科学院の中では当時、「習近平は江沢民派」というのが定説となっていたと言われる(ただし、私は当時からこれに異論を唱えていた。天児慧『中国共産党論』NHK出版新書、2015年、115-116ページ)。事実、習近平が共産党総書記になった18回共産党大会(2012年)の入場式に、習近平は曾慶紅と二人で談笑しながら入場し、両者の関係の緊密性を誇示していた。しかし習近平と江沢民派との蜜月はこの時までであった。
習は下記で見るように、江沢民派と言われる指導者たちを次々と追い詰め、失脚を余儀なくさせた。習近平のこのような処置に江沢民、曾慶紅らは強い不満、怒りを示したが、劉源、王岐山ら他の太子党(たいしとう)と呼ばれる指導者グループ、江沢民らに足を引っ張られ続けてきた胡錦濤ら共青団(きょうせいだん。中国共産主義青年団の略称)グループの支持を得て、反腐敗闘争を有利に進め、江沢民グループの党、軍の指導部からの排除に成功した。しかし、ついでターゲットとしたのは、江沢民グループの排除に多大な貢献のあった胡錦濤及び彼の基盤・共青団である。18回党大会の時点で、胡錦濤は党・軍内で自ら就(つ)いていた主要ポストを習近平に譲り恩を売り、後継者と自他共に認めていた李克強を、そして共青団組織を守り抜こうと尽力した。しかし李克強は19回党大会(2017年)で国務院総理(首相)のポストは維持しながらも、自ら得意としてきた経済分野での実質的な指導は骨抜きにされた。さらに20回党大会(2022年)では党、政府の指導ポストを剥奪(はくだつ)された。将来性を期待されていた胡春華、バランス感覚の鋭い汪洋らも全て指導部から排除された。
「機を見るに敏」の指導者
第2に、〈「機を見るに敏」の指導者〉と言えた。これは上で触れた政敵打倒の時にも十分に使われた。そして「腐敗汚職反対」を掲げ、大々的なキャンペーンを繰り広げ、ライバルと見られていた主要な政治指導者を失脚に追いこんでいった。江沢民派の周永康(公安、石油派のトップ)、徐才厚・郭伯雄(ともに中央軍事委員会副主席)、孫政才(重慶市党書記)、令計画(胡錦濤系・共青団)らに容赦のない鉄槌(てっつい)が下された。そして2017年の第19回共産党全国大会までに、ほぼ習近平独裁体制を固めるに至った。
「決断力と実行力」を兼ね備えたリーダー
第3に、〈「決断力と実行力」を兼ね備えたリーダー〉である。「大きな虎も小さなハエも徹底的にやっつける」との主張は、反腐敗闘争の時の習近平の有名な言葉であった。ちょうど反腐敗闘争が盛り上がりつつある時、鋭い社会批評を行っていた文化人・梁曉声が、習近平の反腐敗への取り組みは、断固としたもので本物であると称(たた)えた一文を発表している(『朝日新聞』2015年8月7日)。コロナ拡大期の「ゼロコロナ政策」決定の時も、強い決断力を持って全国主要都市に向けて強力に一斉にロックダウンを実施し、コロナの拡大を押しとどめようとした。さらには「ゼロコロナ政策」からの転換の時にも「機を見るに敏」と「決断力と実行力」を合わせた特徴がよく表れている。上海では厳しいロックダウンの実施によってゼロコロナ政策を厳格に推進していたが、地方財政は逼迫(ひっぱく)し、庶民生活は困窮する事態となり、不満が爆発寸前の状態であった。習近平が「ゼロコロナ政策」の放棄を決断したのは、このタイミングを捉えての時であった。まさに「機を見るに敏」の特徴であった。
派閥の形成
第4に、〈習近平派閥の形成〉である。ではもともと基盤の弱かった習近平は、どのように自らの派閥を形成していったのか。「圏子(チュエンズ)」という伝統的な人々のつながりを重視する考え方がある。圏子内の人間とみなされた人々には特別な配慮が示され、圏子外の人々に対しては敵もしくは利用すべき対象として徹底して対応する。多くの中国人にも共通しているが、習近平の場合は特にこの傾向が強く見られる。党の主要人事など、これまでの実績などほとんど無視し、自分との距離感を最優先して人事が決められるという傾向が特徴的であった。とりわけ福建・浙江・上海での活動の中で形成された人脈は重要であった。特に第20回共産党大会では政治局常務委員には李強、蔡奇、黄坤明、何立峰ら習近平チルドレンと言われる人々の露骨な大抜擢(だいばってき)が目立った。付言すれば、李強は、本来ならば上海で陣頭指揮を執ったコロナ政策の失敗の責任を取らされ辞任しても不思議ではなかった。しかし習にとって忠実な側近であった李強は、圏子内の人間として守り抜かれ、それどころか20回党大会では、党内ナンバー2として総理のポストにまで上り詰めた。李強と習近平の関係について、『習近平研究』の中で鈴木隆は、両者の関係は「相当に親密であり、経済社会政策に関して、習近平は李強の意見や提案をかなりの程度受け入れている可能性がある」(435ページ)と指摘している。
権力の正統性をどのように確保したか
もう一点、検討されておくべき〈権力の正統性〉については、どのように考えられるのか。もともと権力の正統性とは、権力を行使する人が統治を確立し、それが統治される人々に何らかの形で受け入れられていると判断される状態を指す。西側民主主義諸国は普通選挙によって正統性が制度化されていると判断されるが、普通選挙を行わない独裁・専制国家での正統性はやや曖昧である。一般的には政権担当者が、国家的な困難克服の方針を提起したり実践したり、社会を良くする方向で仕組みを作ったりし、一般国民がそれを支持していると何らかの形で判断される状況が見られる時、正統性を確保していると考えられる。毛沢東時代は「民族の解放と国家の独立」がメインテーマとなり、それを実現した毛沢東と中国共産党が民衆からの正統性を勝ち得た。「広義の」鄧小平時代では、文革の大混乱と貧困からの脱出を強く希望した民衆に答えるべく、社会秩序と生産力の回復=「安定」と「豊かさ」の追求を前面に打ち出し、民衆からの圧倒的な支持を得た。
では習近平時代の正統性はどのように確保されたのか。鈴木隆によれば、正統性の3本柱として「豊かさ」「便利さ」「偉大さ」を上げているが、「豊かさ」「偉大さ」は習近平時代の固有の主張ではなく、共産党の長きにわたっての主張であると言える。その意味で共産党統治の正統性主張の根拠にはなっている。しかし「便利さ」が統治の正統性の根拠になっているのかどうか、全面ロックダウンを強行した「ゼロコロナ政策」などを想起すると筆者には疑念が残る。むしろ習近平が全力で取り組んだ「腐敗撲滅(ぼくめつ)」の方が、「中華民族の偉大な復興」と共に習近平政権の正統性になっているのではないか。
習近平の民主主義観
最後に、〈習近平の民主主義観〉はいかに理解すべきか。民主主義の基本を「組織の重要な意思決定を、その組織の構成員が行うこと」と理解するならば、胡錦濤時代の2007年、第17回党大会前に実施された中央委員クラス以上のエリート層による予備選挙は、かなり民主的に実施され、その結果習近平は多数票を獲得した。この結果を踏まえて新任の政治局人事が決められ、党内序列の決定に重要な判断材料となった(習近平6位、李克強7位)。そして2012年の党総書記就任に際して、この序列は大きな影響を持った。さらに個々の組織、例えば党中央政治局、中央軍事委員会などにおいて「民主生活会」が重要な役割を果たしたと鈴木隆は着目している。特にこの生活会では周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚らに対する反腐敗闘争において効果を上げたという。共産党の「民主」が冠につく主張や組織は、得てして形だけのものと理解されがちであるが、「民主生活会」が一定の重要な役割を果たしていたことは注目すべき点である。ただし現在、このようなエリート組織内部においてさえ「民主」が保証されているか否かは不透明である。
しかし一般民衆のレベルにおいては、権力の露骨な介入によって「民主」はほとんど形骸化してしまった。胡錦濤時代には、いささか発言の自由が黙認された様々な地方新聞が出版されたり、インターネットなど非公式メディアの発達もあって言論空間が少しずつ拡大したりしていたが、習執政下で急速に引き締められ、たとえ習近平批判ではなくても、習近平とは異なった意見を主張するものに対してさえ、しばしば容赦のない鉄槌(てっつい)が下されている。特に、漢族との民族対立が続くチベット、ウイグル、自由と安定が急速に失われた香港に見られる「国家統合」の問題では、「民主的な」主張は徹底した弾圧の対象となっている。
台湾問題についてみるとここでも「民主」がキーワードになっている。すなわち蔣介石・蔣経国の独裁体制を打破し、民主主義体制を実現した今日の「民主台湾」は、共産党一党体制の大陸中国と本質的に対立する構図となっている。これに対して中国当局は、中国ナショナリズムの強調と台湾自身の歴史的、自立的な政治的経緯の軽視、とりわけ第二次世界大戦後の台湾における権威主義的独裁からの脱却の経験と1980年代半ば以降の民主化過程を全て無視している。
武力行使以外の台湾統一の方式として近年、社会経済の各種優遇政策による台湾人青年層の取り組み=恵台政策を推進し、台湾人青年の中国に対する帰属意識の涵養(かんよう)に重点が置かれている。さらには、福建省を主要舞台とする「両岸融合発展」を目指した経済、文化交流と人的往来の促進を通して一国二制度による「台湾の香港化、中国化」の推進が試みられている。しかし過去に言われていた台湾での独自の官僚機構と軍隊の保持がなくなり、「高度な自治」の範囲が狭められた。さらには長い時間をかけて徐々に台湾の人々の心に沈殿(ちんでん)し、蓄積されていった独自のアイデンティティ=台湾人意識が無視できないものになっている。したがって習近平が様々な硬軟交(まじ)えた手段で台湾を取り込もうとしても、けっして楽観できるような状況ではない。
国際社会の枠組みから中国を捉える
では変動する国際社会の枠組みから中国を捉えてみるとどのように見えてくるのか。米国の学術関係者は「米国の政治体制は約80年サイクルで変化し、2025年は新たなサイクルに入る」と指摘している(ジョージ・フリードマン等)。第一期が独立戦争(1775年~1783年)から南北戦争(1861~1865年)、第二期が南北戦争から第二次世界大戦の終わり(1945年)、そして第二次世界大戦が終わってから80年間が経過する2025年頃に第三期が終わる、という見解である。そして25年から始まる第2期トランプ政権は、米国第一主義を掲げて新しい第四期に突入するということになる。確かに、トランプ大統領の政策を見ると、①関税強化政策、②海外諸国や国際機関との非協力的姿勢、③移民の強制送還や国境への壁の建設のような外国人移民排斥運動など、歴史の歯車を逆回転させるような大きな歴史的転換を予感させる。バイデン政権末期に見られた、経済合理性に基づく日本企業による米国企業の買収に対する阻止行動は、トランプ政権にも引き継がれた。2025年は米国が保護主義・孤立主義に本格的に移行した記念碑的な年として歴史に名を残すかもしれない。
米国以外にも世界的な構造変化は多くある。一つは、他方で世界最大の人口大国となったインド経済の存在感が一層高まることが予想される。未来のフロンティアと言われているアフリカ諸国は、今後、コロナ前よりも成長率を高めると予想されているほか、21世紀を通じて人口が増加するとみられており、世界経済の中で一層注目を集める存在となる可能性がある。2025年は第三世界の集結を示したアジア・アフリカ会議(バンドン会議<1955 年>)から70年のメモリアルイヤーでもあり、これからの見通しとしてインドなどのグローバルサウスの影響力が高まっていく時代となろう。
日本を待ち受ける政治面の地殻変動
日本に目を転じても、大きな変化がある。明治維新から終戦までが約80年であるが、2025年は戦後80年である。その意味では、様々な戦後体制を見直すタイミングにあるとも言える。注目すべき変化は団塊の世代全員が後期高齢者入りすること、いわゆる2025年問題である。年金・医療・介護のニーズが高まることは避けがたく、社会保障制度改革を断行できるかが今後の日本の経済・社会の帰趨(きすう)を決めると言っても過言ではないだろう。さらに、団塊の世代が75歳を超えることは、政治にも影響を及ぼす。衆議院選挙の投票率(2021年)を見ると、70~74歳が一番高いが、75歳を超えると低下していく。昨年の総選挙では現役世代の声に耳を傾けた政党が躍進したが、今後はその傾向が強まる可能性がある。2025年以降の政治面の地殻変動に留意すべきである。
このように不安定化する国際情勢から見ても、中国がもし台湾に対して大胆な政策・行動を取るならば、国際社会において大きな不安定材料となることは疑いない。これからの中国は、鈴木隆によれば、米国に対する国力の相対的低下に伴い、既存の国際秩序に穏健かつ漸進的に適応していくとの意見と、一種の焦りの心情にとらわれて現状変更の動きを加速させるという、異なった2つの見方がある。私は、習近平本人については「穏健適応」よりも「焦慮加速」と見ておく方が無難であろう、と見通している。しかしどのような主観的、客観的な事情があろうとも、中台の「国益」から見ても、国際社会の「安定」から考えても、中国には穏健で漸進的なアプローチを維持し続けることが求められているのである。