Commentary
損保社員が見た中国ビジネスの現場
門戸をこじ開けるための苦労

上海に現代的なホテルを建設せよ
野村證券(野村中国投資)は、上海市の汪道涵(おうどうかん)市長からの要請もあり、旧フレンチクラブ(かつてのフランス租界に設けられた社交場)を全面的に建替え、高級ホテルを建設することとした。中国との関係強化を図るとともに、有望な投資プロジェクトとして、建設に取り組んだと思われる。
筆者が、本プロジェクトと関わりを持ったのは、北京駐在員事務所に赴任した1988年6月からである。当時は、北京駐在員事務所で中国本土全体をカバーしていたので、上海にもほぼ毎月のように出張し、PICCを始め中国の関係先を訪問しつつ、日系プロジェクトの保険手配についてもコンサルティングサービスを提供していた。
本件の建設工事保険は、PICCが元受であり、東京海上は再保険を引き受ける立場だった。野村中国投資がPICCに保険を付保する際の条件などにつき、助言をする役回りを務めた。投資金額は100億円をかなり上回ると推定するが、当時としては大型案件であり、東京海上としても、現場の安全管理や工事の進捗(しんちょく)状況に格別な関心を持って、プロジェクトの進行を見守っていた。
さて、当時、野村中国投資で本件の責任者となっていたのはK氏だった。筆者は上海に出張する度にK氏と食事をご一緒させてもらった。その席には、大林組の現地トップN氏も同席され、苦労話をお聞きした。たとえば、ホテル敷地内に地下壕(ごう)のようなものがあり、その処理をどうするかについて、上海側との交渉がなかなか進展しないとか、あるいは軟弱地盤のため基礎のくい打ちに大変苦労したなど常に何らかの問題を解決するよう迫られていた。その中でも、K氏やN氏は、常に前向きに問題解決を図ろうとしていた。
ホテルの施設として特筆すべきは、大宴会場となっている旧ボールルーム(舞踏場)だ。楕円(だえん)形の大広間内装は、旧フレンチクラブ時代の面影を残しつつ、絨毯(じゅうたん)が敷き詰められ、見事な佇(たたず)まいを見せている。大広間に至る螺旋(らせん)階段は優美そのものだが、工事の最中に壁板をはがしたところ、文革中に隠されていた見事な浮彫(レリーフ)が現れた。それは、そのまま保存されている。
建設工事も後半になると、ホテルマネジメントを担当するホテルオークラの幹部(A取締役他)が上海に度々来られ、ホテル従業員の採用や訓練を始めた。花園飯店は、自前で職業訓練校を設立するとともに、従業員数十人ずつを日本のオークラに送り込み、日本語会話を始めホテルサービスに関する研修に明け暮れた。仮営業前には、A氏他がホテル建物に泊まり込み、実地で研修を行った。当時の中国には「現代的なホテルサービス」といったものはほぼ存在していなかったので、その苦労は想像に余りある。A氏は、夜中にもホテル内を巡回し、問題点の把握・解決に努めていた。A氏他の指導は誠に厳しくかつ温かく、「一流のホテルサービスを中国で根付かせる」という使命感に溢(あふ)れていた。
筆者は、ホテルの仮営業開始から、何度も宿泊したが、サービスのレベルが向上する様子がよく分かった。A氏の指導は厳しかったが、従業員には大変慕われていた。
このように、K氏を始めとするオーナー・建設会社・ホテルマネジメント会社のチームワークの良さによって、艱難(かんなん)辛苦を乗り越え、花園飯店は1990年にグランドオープンを迎えた。当初は折悪しく、6・4天安門事件の影響で客足が伸びず、苦戦を強いられた。しかし、その後は、ホテル施設およびサービスのすばらしさが徐々に浸透し、上海におけるトップホテルとしての名声を確立した。
花園飯店は、現在も、日本人を始めとする外国人観光客やビジネスマンに好評を得ている。同ホテルの口コミには「安心して泊まれる」「料理が美味しい」など好意的な意見が多い。所有権が錦江グループに移行した後も、ホテルのマネジメントは、オークラニッコーホテルマネジメントが担当しており、日本流のサービスを継続している。日本人スタッフを常駐させ、日本流のサービスを継続することは、錦江グループからの要望だった。
【特別掲載】


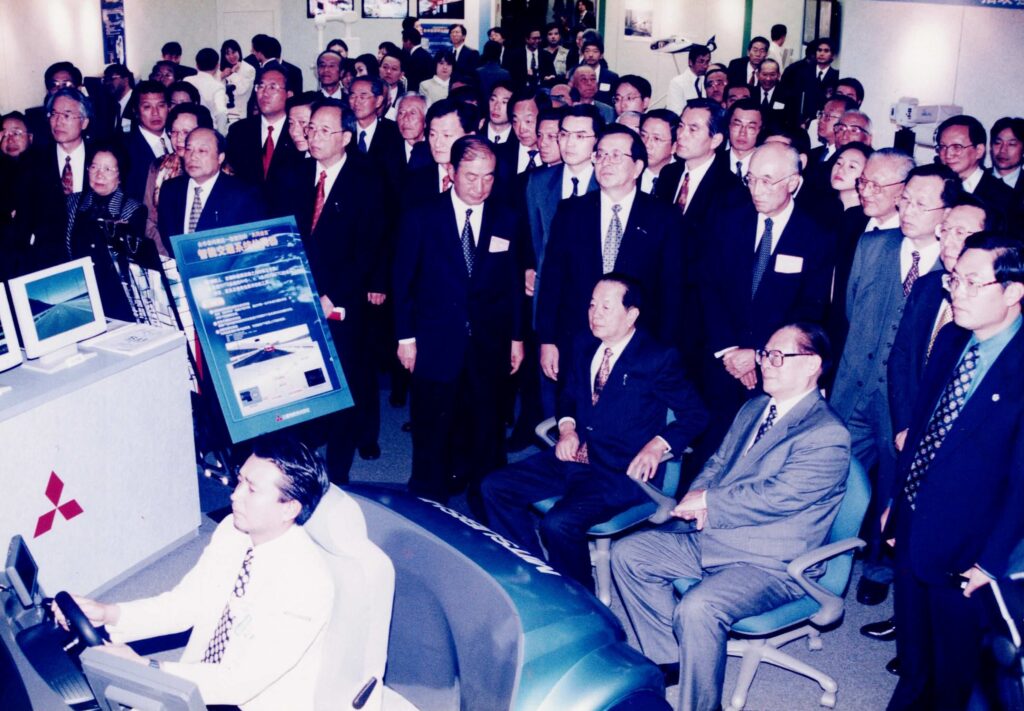
参考文献
小原篤次・神宮 健・伊藤 博・門 闖編著(2019)『中国の金融経済を学ぶ』ミネルヴァ書房。
六四回顧録編集委員会編(2020)『証言 天安門事件を目撃した日本人たち』ミネルヴァ書房。






