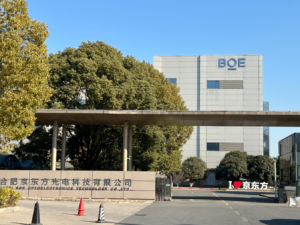Commentary
中国が中程度の経済成長を維持するためになすべきこと

解題
2024年12月7日~8日に清華大学国情研究院と東京大学中国イニシアティブとの共催による「第4回清華大学・東京大学発展政策フォーラム」が東京で開催された。今回のテーマは「競争と協力――グローバルな不確定性のもとでの日中経済貿易関係」である。
12月8日には東京大学にて公開シンポジウムが開催された。そのシンポジウムで行われた講演の概要を順次紹介する。
「3つのi」戦略への転換
中国のGDPは2012年から2023年の期間に年平均6.1%の速度で成長した。世界銀行の『世界開発報告』2024年版によると、中所得国の段階に入った国は、「1つのi」戦略から「2つのi」戦略、「3つのi」戦略へと転換していく必要があるという。「1つのi」戦略とは投資(investment)主導の成長という意味であり、中国でいうと1978年以前がこの段階に当たる。「2つのi」とは投資と導入(infusion)の主導という意味であり、中国の場合は1978年から2008年がこの段階に当たる。「3つのi」戦略とは投資、導入に加えてイノベーションを重視する段階であり、中国は2008年以降この段階に入った。
中国のGDP成長に対する資本成長の寄与度は下落傾向にあり、2010年までは6%ポイントを上回ることもあったが、2023年には1.5%ポイントとなっている。一方、最終消費の寄与度は2020年以降コロナ禍の影響で大きく変動している。固定資本投資がGDPに占める割合は低下傾向にあり、2010年には53.1%だったのが、2023年には39.9%へ下がった。なかでも不動産開発への投資は2015年には対GDP比13.9%だったのが2023年には8.8%へ下がった。不動産投資の絶対額も2022年、2023年と対前年比で10%ずつ減少した。これまで中国経済を牽引する機関車であった投資、特に不動産投資がいまでは中国経済の足を引っ張っている。
内需拡大のための一連の政策
可処分所得のうちどれぐらいが消費支出に回るかという限界消費性向を見ると、2020年に下落、2021年に回復、2022年に下落、2023年に回復というW字の変化を見せている。この変化は国内の旅行業の収入と一致した動きである。
大方の一致した見方として現在の中国経済は有効需要の著しい不足という状態にある。そこで2024年には内需拡大のための一連の政策が打ち出された。3月7日には国務院から設備の更新、消費財の買い替えを促進する措置が打ち出された。5月17日には新たな不動産政策として住宅ローン金利の下限撤廃、頭金比率の引き下げなどが行われた。9月末には包括的な拡張政策として内需拡大、不動産価格の下落阻止などの方策が実施され、11月には地方政府の「隠れ債務」の問題に対して、それを地方債に置換できる枠が6兆元拡大された。
かつての日本の経験から見た現在の中国
日本経済は1973年から1992年まで年平均3.6%で成長したが、中国も今後20年間4~5%ぐらいの中成長を維持したいと考えている。一人当たりGDPを購買力平価で換算すると、日本は1990年にはアメリカの79.83%だったのが2022年には62.83%へ引き離されている。一方、中国は1990年にはアメリカの3.7%にすぎず、2022年でも30.06%であり、まだ1990年の日本よりずっと低いレベルにある。一方、人口の構造を見ると、0~14歳の人口が総人口に占める割合において2022年の中国は1990年代初めの日本と同レベルにある。また、65歳以上の高齢者が総人口に占める割合を見てもやはり1990年代初めの日本の水準にある。
アメリカとの貿易摩擦を経験した点も現在の中国と1990年代までの日本とは共通している。第一次トランプ政権のもとで2018年から中国からの広範な輸入品に対して関税が上乗せされ、中国が報復を行い、米中は貿易戦争に突入した。米中貿易額と中国のGDPの比率を見ると、実は貿易戦争の開始前から下落傾向にあり、貿易戦争開始後さらに下がった。ただ、中国経済は貿易戦争に対する一定の耐性を持っている。「デカップリング」といわれるが、実際には第三国経由の取引が活発化している。一方、日本経済が日中貿易および日米貿易に依存する度合は上昇傾向にある。日中の貿易関係を深めることによってアメリカの第2次トランプ政権からの新たなショックに対する耐性を高めることができる。
日本のGDPに占める建設業と不動産業の割合を見ると、1990年代初めのバブル崩壊後に顕著に下落したのは建設業であり、不動産業はむしろ上昇傾向にある。中国の不動産業がGDPに占める割合は最近のピークである2020年でもまだ7%程度であり、日本に比べてまだ低い。2021年以降、中国の不動産業がGDPに占める割合は6%以下へ急落し、不動産価格も2021年5月から下落が始まり、すでに3年半にわたって下落が続いている。この先、中国の不動産価格がバブル崩壊後の日本のように18年間にもわたって下がり続けるのか、あるいはサブプライムローン問題が出て以降のアメリカのように5年程度で下げ止まるのかは大きな関心事である。私は5年内に不動産価格は下げ止まると予測している。一つの理由は政府が不動産価格を安定させる政策を打ち出していることであるが、もう一つは中国の都市化率はまだあと10%程度は上昇する余地があるからだ。
国家の債務に目を転じると、中国の中央政府の債務の対GDP比は国際比較でいうとまだ低い。地方政府の債務を加算してもまだ高いといえる水準にはない。中国のGDP成長率が政府債務の金利より高い限りは政府の債務はそれほど気にする必要はない。
長期の問題として気にすべきことは人口の動態である。日本の1990年から今日までの状況を見ると、人口の高齢化が進展し、それとともに政府の債務が増加し、一人当たりGDPではアメリカとの差が開いていった。
3つの大きなチャレンジと2つの転換
中国はこれから3つの大きなチャレンジに立ち向かう必要がある。第一は人口転換、第二に外部のショック、そして第三に金融リスクである。中国経済は2つの転換を行う必要がある。第一に、消費需要主導に転換すること、第二にイノベーション駆動型の成長への転換である。中国のGDPのうち最終需要が占める割合は日本と比べて低すぎる。貿易額とGDPの割合も低下傾向にある。
供給面ではイノベーション駆動型への転換が急務である。クラリベイト社が2024年の世界のトップ・イノベーター100社を選定したが、そのうち日本企業が38社、アメリカ企業が17社であったのに対して、中国は16社(うち台湾が11社、大陸が5社)であった。一方、特許出願から見た科学技術クラスターの数を見ると、中国が26か所、アメリカが20か所となっている。過去20年間、中国は科学技術経費、科学技術の研究者、論文数などにおいて飛躍的な成長を遂げてきた。デジタル経済、新エネルギー、戦略的新興産業における成長は目覚ましい。ただ、そうした新産業の成長が不動産価格下落のマイナスを補うに足るほどではない。
中国経済の現在を理解するには多面的な視点が必要である。中国政府は過去10年間に経済成長の方向を変えるために新しい概念を打ち出してきた。2014年には「経済発展の新常態」、2015年には「供給サイドの構造改革」、そして2023年には「新しい質の生産力」を打ち出し、イノベーション主導型成長への転換を目指している。
(2024年12月8日の東京大学における講演に基づいて丸川知雄が記録をまとめた)