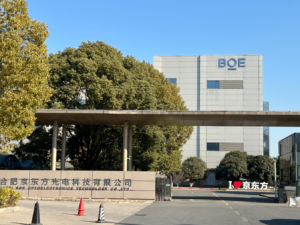Commentary
現場なき中国研究への回帰か?
米国で見た高度なデータ解析の潮流と遠ざかる現地調査

2022年8月、米国ケンブリッジ市に研究滞在する機会を得た。私は中国経済研究をしているが、ゼロコロナ政策のもとで中国に入国することが難しくなり、この機会に米国の大学で先端的な研究動向に触れてみようとの思いからだった。2022年8月から2023年7月までハーバード燕京(イェンチン)研究所、続いて2024年6月までハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所に滞在し、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)を中心とする各種の研究会に参加した。このエッセイでは学園都市・ケンブリッジ市から見た中国研究の雑感を述べたい。
米国社会の緊張と関心
滞在中、現地で感じた対外関係の最大の関心事は、言うまでもなくイスラエル・パレスチナ情勢だった。下院議会での証言をきっかけにハーバード大学のクローディン・ゲイ学長が辞任した(2024年1月)。キャンパスの中心地にあたるハーバードヤードでは抗議活動が続き、卒業式の開催も危ぶまれた。ロースクール前には、親イスラエル派の団体の車両が親パレスチナの行動をとった学生の顔写真を張り付けて抗議し、上空には大学当局を批判する横断幕を掲げたプロペラ機が旋回する異様な雰囲気が続いた。学生だけでなく、教職員の意見も大きく分断されており、思い切ってランチの際に話題を切り出すと堰(せき)を切ったように議論になることもあった。キャンパスで広がりを見せるパレスチナへの同情の中で、イスラエル出身の大学院生は「ここにはもう私たちの居場所はない」と肩を落としていた。

ケンブリッジ市は平均的な米国の都市では全くない。あくまでもそこからの観察だが、総じて現地社会が中国問題に関心を持つことは稀(まれ)だった。おそらく唯一の例外は、2023年2月に偵察気球が飛んできた時である。この時ばかりは地元ニュースでも盛んに取り上げられ、聴講していた中国関係の授業でも話題になった。ある種の熱気を感じた時期だったものの、それもすぐに過ぎ去っていった。人々の主要な関心事は生活を圧迫するインフレであり、改善しない庶民向け住宅事情であり、近隣の治安であった。
研究インフラの構築と活用
中国研究に目を向けると、現地で私が特に感心したのは、ある種の研究インフラの構築を重視している点である。系統的かつリアルタイムに中国情報を収集するインフラが複数形成されている。中国の対外直接投資データであればアメリカンエンタープライズ公共政策研究所、対外融資であればボストン大学、対外援助であればウィリアム・アンド・メアリー大学にてデータが収集されている。例えばボストン大学のケビン・ギャラガー教授らは、こうしたデータインフラを基に先端的な科学論文を多数刊行している。話を聞いた別のある拠点の場合、プロジェクトを維持するのに、年間で数百万ドルの予算を確保していた。それだけの資金を確保し、基礎的な情報を収集し、系統的に分析しているわけである。
キャンパスでは広い意味での社会科学研究にかかわる新世代の台頭も感じ、研究手法の発展は著(いちじる)しかった。米国の研究大学院における大学院生を含む若手の研究者には大規模なデータを用いた機械学習(特に深層学習)を導入する動きが広がっている。学部あるいは修士段階で計算機科学を専攻していた経済学や政治学の大学院生が増えているようにも思われた。滞在時期がちょうどChatGPTのリリース(2022年11月)と重なったこともあり、現地で大規模言語モデルをいかに社会科学研究に活用できるか、という熱気を感じられたことも印象的であった。この他、人工衛星による夜光データを用いた米中貿易摩擦の中国への影響に関する地理的推計、歴史的な発明文書から長期イノベーション指数を構築する取り組み、収集した県レベルのゼロコロナ政策の強度を基にしたコロナ下の政治経済分析、中国人民解放軍の公開人事情報に基づく軍内の昇進メカニズムの推計など、現地で触れた研究はいずれも刺激的だった。

現地から遠ざかる中国研究
中国研究が難しい時代に入りつつあることも感じた。インターネットを通じて各種データを得られる中で、中国に足を踏み入れずに飛び切りの実証分析をする研究者もいる。少数の突出した才能を持つ研究者のまわりにそうした成果が集中している。しかしこれを真似することは容易ではなく、一般にはやはり現場感覚が必要である。現地の院生が企画するインフォーマルな中国政治に関する研究会もあり、毎週発表が繰り広げられていた。ただ、その研究会を以前から知る人に言わせると、近年では参加者が減り、退潮が著しいとのことだった。背景には中国人の大学院生を含めて現地調査が困難化し、中国政治を分析することがあまりにセンシティブになってきたことがある。結果、中国人留学生が問題意識を持っていても、政治的なリスクの低い分析方法論(例えば政治学方法論)にシフトする傾向があるようだった。
より広く米国における戦後中国研究の趨勢(すうせい)を大づかみに理解する上では、2024年にJournal of Contemporary Chinaにデイビッド・シャンボー教授が書いた論考「米国における現代中国研究の進化:原点回帰か?」が示唆に富む。彼は米国における中国研究は多分に中国自体の変化やディシプリン(政治学等)の発展からの影響を受けた受動的な分野だとみる。その上で研究者を6世代に分類し、最初の世代は冷戦初期のクレムリノロジー(ソ連で公になった数少ない情報を基に政治情勢などを分析する手法。ソ連共産党の中枢がモスクワのクレムリン宮殿にあったことに由来する)に類似したアプローチだったと位置付ける。そして現在、再び現地調査が困難化していることを踏まえ、ある種、冷戦期共産圏研究のように外部から中国を知ろうとするような時代に回帰しつつある、と指摘する。これは日本の中国研究にとっても他人事ではない問題提起である(日本に拠点を置く中国研究者が中国で拘束されてきた事例については本ウェブサイト「中国の国益を損なう「国家安全」重視路線」を参照)。
必ずしもこの趨勢(すうせい)のみで説明できるわけではないが、何人かの著名な中国研究者は、より中長期的(あるいは歴史的)な分析に向かっているようにも思われる。スタンフォード大学の許成鋼(Chenggang Xu)上級研究員、MITの黄亜生(Yasheng Huang)教授、ハーバード大学の王裕華(Yuhua Wang)教授らの近著がそれにあたる。彼らはいずれも同時代の政治経済学的な分析で成果を上げてきた研究者である。これら著作の傾向が一致するのは、一つには現状の権威主義的体制の起源を探る研究が求められているからだろう。加えて、中国大陸の現状分析を続けることが過去10年以上の間に徐々に難しくなってきていることも一因にありそうだ。滞在中、香港のある有力大学から著名な中国政治研究者がボストンに移ってきた。香港を拠点とする代表的な中国研究者の一人だったため、これも情勢の変化を感じさせる出来事だった。
ある時、ワシントンの戦略国際問題研究所から著名なチャイナウォッチャーの一人であるスコット・ケネディ上級顧問がケネディ・スクールに来た。長年の研究蓄積の上に立つ彼の分析と観察は際立ったものだったが、多くの聴衆が関心を持っていたのは、要するにコロナ後に中国を現地訪問した際の感想であった。冷戦期にあったと聞く、見聞録的講演会の趣(おもむ)きがあった。逆に北京の大学から講演に来る研究者も少数ながらいたものの、その内容は北京におけるポリティカル・コレクトネス(政治的正しさ)に基づいて発言内容が厳しく制限されていたように感じた。当該研究者が中国国内で話している内容と、ハーバード大学での講演内容は大きく違った。

地域研究者の減少、そしてこれは日本でも進んでいる
危惧されるのは米国での中国を含めた特定地域の研究を志す若手地域研究者の減少である。これは日本でも同様である。米国には改革開放初期からアジアの現場を踏み、長年の観察を続けてきた研究者がいる。しかし中長期的には先細りが懸念されていた。報道によれば中国へ留学に行くアメリカ人学生がとりわけコロナ後に激減し、2023年時点でわずか700人となっており、ある学者は1980年代の熱気との落差を嘆いていた。確かに中国の経済成長率は鈍化しており、国連人口推計によれば人口は今後30年で2億人減少する。若者は中国問題へのニーズの低下を機敏に感じ取っているのかもしれない。現地に行かずにビッグデータ分析をすることも可能だろう。しかし、中国を理解しようとする人の母数が減ると、中長期的には広い意味での中国理解と中国研究に根深い影響を与えるだろう。これもまた他人ごとではない。
中国研究を巡る情勢変化の中で、シャンボー教授が言う冷戦期に似た研究への回帰、すなわち「原点回帰」はあまり心躍(おど)る話ではない。日本を拠点として何ができるだろうか。全く同じ位置に戻るだけの円周上の原点回帰ではなく、せめて螺旋(らせん)状の前進を目指したい。冷戦期に比べれば圧倒的情報量が利用可能ないま、それは十分可能だろう。そのためには質的調査・情報を引き続き活用しなければならない。その上で、大規模なデータセットの構築をはじめとする研究インフラの基盤強化が求められる。当然ながら数理モデルや深層学習を含む先端的手法の導入も進める必要がある。その先に、今の時代に即した問題意識と分析技術に根差した、立体的かつ緻密な中国理解があり得るのではないだろうか。
注:本稿は「「現場」なき中国研究への回帰か?」『外交』Vol.87(2024年9/10月号), 104-107頁に掲載されたものを加筆修正したものです。