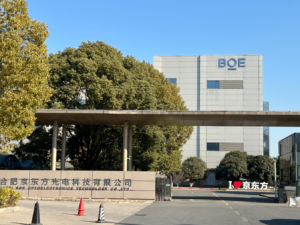Commentary
現場なき中国研究への回帰か?
米国で見た高度なデータ解析の潮流と遠ざかる現地調査

2022年8月、米国ケンブリッジ市に研究滞在する機会を得た。私は中国経済研究をしているが、ゼロコロナ政策のもとで中国に入国することが難しくなり、この機会に米国の大学で先端的な研究動向に触れてみようとの思いからだった。2022年8月から2023年7月までハーバード燕京(イェンチン)研究所、続いて2024年6月までハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所に滞在し、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)を中心とする各種の研究会に参加した。このエッセイでは学園都市・ケンブリッジ市から見た中国研究の雑感を述べたい。
米国社会の緊張と関心
滞在中、現地で感じた対外関係の最大の関心事は、言うまでもなくイスラエル・パレスチナ情勢だった。下院議会での証言をきっかけにハーバード大学のクローディン・ゲイ学長が辞任した(2024年1月)。キャンパスの中心地にあたるハーバードヤードでは抗議活動が続き、卒業式の開催も危ぶまれた。ロースクール前には、親イスラエル派の団体の車両が親パレスチナの行動をとった学生の顔写真を張り付けて抗議し、上空には大学当局を批判する横断幕を掲げたプロペラ機が旋回する異様な雰囲気が続いた。学生だけでなく、教職員の意見も大きく分断されており、思い切ってランチの際に話題を切り出すと堰(せき)を切ったように議論になることもあった。キャンパスで広がりを見せるパレスチナへの同情の中で、イスラエル出身の大学院生は「ここにはもう私たちの居場所はない」と肩を落としていた。

ケンブリッジ市は平均的な米国の都市では全くない。あくまでもそこからの観察だが、総じて現地社会が中国問題に関心を持つことは稀(まれ)だった。おそらく唯一の例外は、2023年2月に偵察気球が飛んできた時である。この時ばかりは地元ニュースでも盛んに取り上げられ、聴講していた中国関係の授業でも話題になった。ある種の熱気を感じた時期だったものの、それもすぐに過ぎ去っていった。人々の主要な関心事は生活を圧迫するインフレであり、改善しない庶民向け住宅事情であり、近隣の治安であった。
研究インフラの構築と活用
中国研究に目を向けると、現地で私が特に感心したのは、ある種の研究インフラの構築を重視している点である。系統的かつリアルタイムに中国情報を収集するインフラが複数形成されている。中国の対外直接投資データであればアメリカンエンタープライズ公共政策研究所、対外融資であればボストン大学、対外援助であればウィリアム・アンド・メアリー大学にてデータが収集されている。例えばボストン大学のケビン・ギャラガー教授らは、こうしたデータインフラを基に先端的な科学論文を多数刊行している。話を聞いた別のある拠点の場合、プロジェクトを維持するのに、年間で数百万ドルの予算を確保していた。それだけの資金を確保し、基礎的な情報を収集し、系統的に分析しているわけである。